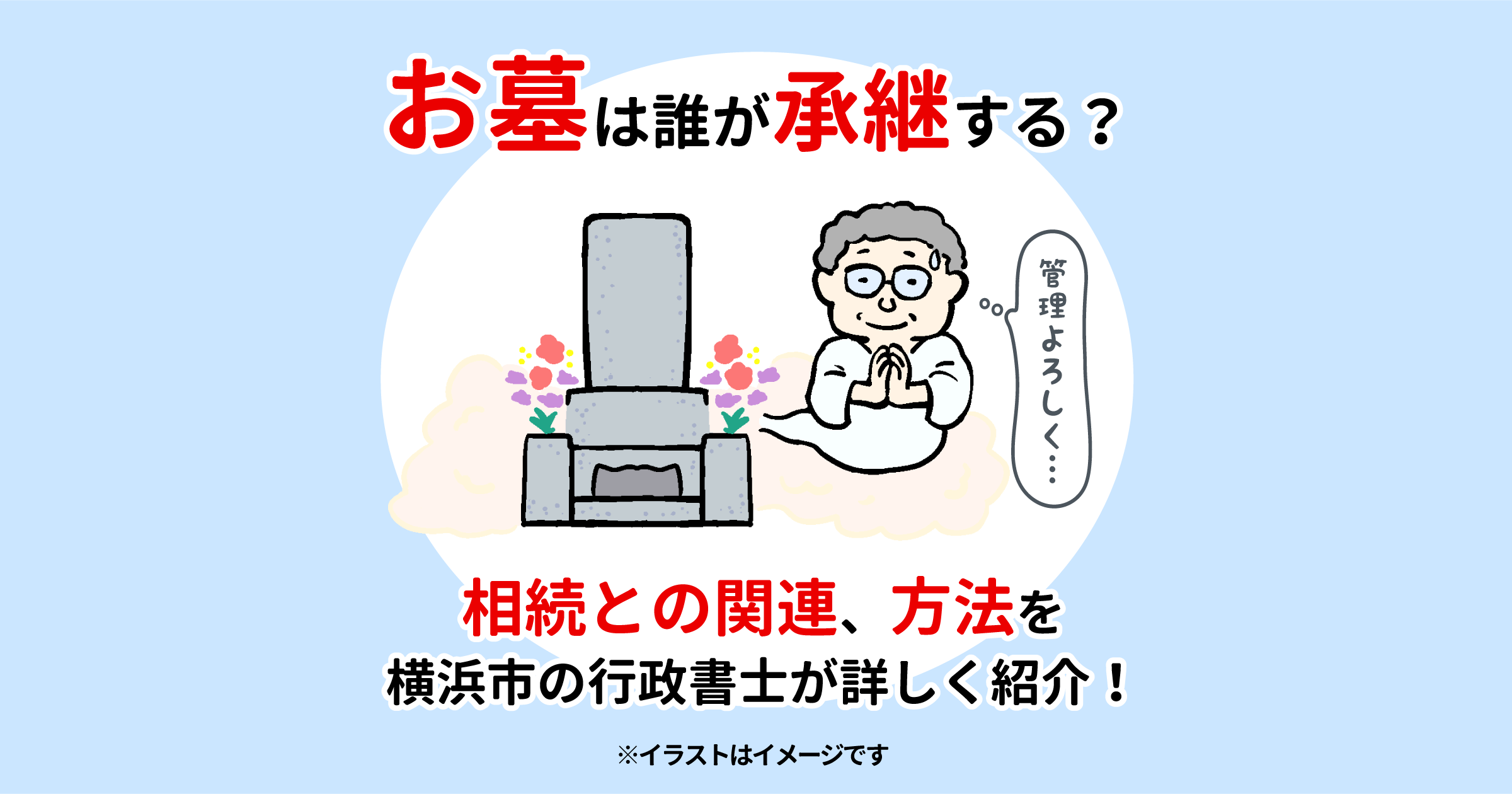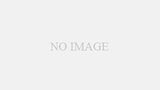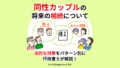「お墓は誰が相続するの?そもそもお墓も相続財産なの?」
「お墓を相続する人は法律で決まっているの?」
「実家のお墓や仏壇を承継するが、知っておくべき方法や注意点はある?」
日本では亡くなられた方を見送った後、お墓に納骨をすることが一般的です。全国には形状や宗派は違えども、多くのお墓があります。
では、お墓は誰が相続するものでしょうか。もしお墓を相続するとしたら、名義変更のような手続が必要なのでしょうか。今回の記事ではお墓の相続について方法や注意点を、相続手続に詳しい行政書士が解説します。
お墓は相続財産ではない
まず前提として、お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産には含みません。
被相続人が生前に、「自身のお墓や仏壇は内縁の方に管理してほしい」と遺言書を残した場合、相続人ではない内縁の方でも祭祀財産を承継できます。
なお、祭祀財産には3つの種類があります。系譜・祭具・墳墓です。いくつか例を見てみましょう。
- 仏壇
- 墓地や墓石
- 家系図や家系譜
- 位牌
系譜には家系図などが挙げられ、祭具には仏壇や位牌類などが挙げられ、祠や鳥居など、移設が簡単ではないものも含まれます。墳墓とはお墓のことを意味し、墓石や墓地を指します。
もちろん、日本で信者数が少ない宗教で必要なものも、祭祀財産に含まれます。たとえば、キリスト教の場合はイエス像や十字架、家庭内の祭壇などが祭祀財産となります。
そして祭祀財産は相続財産の対象ではない以上、相続人間で遺産のゆくえを話し合う「遺産分割協議」からも対象外となります。
たくさん財産を相続する方が祭祀承継者となることもできれば、相続放棄をした方が祭祀承継者となることもできます。
合わせて読みたい:お墓や位牌は誰が継ぐ?相続や遺言書との関係を行政書士が解説!
お墓を引き継ぐのは祭祀承継者
お墓は相続財産ではない以上、引き継ぐのも相続人ではありません。
お墓を引き継ぐのは、祭祀承継者です。
祭祀承継者とは、お墓や仏壇など信仰にまつわるものを引き継ぐ人を意味します。
では、祭祀承継者はどのように決めるのでしょうか。
まず祭祀に関係する財産は「祭祀財産」と呼び、先述したとおり原則として相続財産の対象にはなりません。法定相続人が承継する義務もなく、民法第897条第1項および第2項によって、以下のように定められています。
第1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。第2項
民法第897条第1項および第2項
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
そして、祭祀財産を承継する人は、以下のようにまとめられます。
- 慣習にしたがって承継する
- 被相続人の指定(遺言や口頭)に従って承継する
- 慣習が分からない際には家庭裁判所が決める
一般的にはお墓や仏壇の管理は暗黙の了解で、被相続人と同居していた家族や、慣習にしたがって長男・長女が引き継ぐことが多いでしょう。原則1名が祭祀を主宰する人としてすべての祭祀財産を引き継ぎますが、複数の祭祀財産を分けて承継することも可能です。
祭祀承継者が家族内で決まらない場合は、家庭裁判所で決められます。
合わせて読みたい:お墓の相続(継承)はどうなる?遺言書でお墓の承継人を指定する方法
なお、先に触れたように、祭祀財産については相続財産には含まないため、相続放棄をしても承継できます。被相続人に債務があり、放棄をする場合はお墓や仏壇も相続放棄しなければいけないのか、と不安な方も多いでしょう。墓地や代々使用してきた数珠なども相続財産ではないため、相続放棄後も祭祀承継者として引き継げます。
合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!
お墓を承継するための手続き
墓地や寺院などによって手続き方法は異なりますが、お墓を承継する際には一般的に墓地の管理者に対して引き継ぎの手続きを行う必要があります。
これが一般的に、お墓の名義変更と呼ばれるものです。
祭祀承継が決定したら今後は誰が墓地を含むお墓を管理するのか、書類などを提出する必要があるということですね。
お墓の承継(相続)で必要な手続をもう少し細分化すると、次のような例が挙げられます。
- 所有者の名義変更手続き
- 墓地の使用許可証
- 承継理由(被相続人の死亡がわかる書類の提出)
近年墓石・墓地とは異なりマンション型の納骨堂なども登場していますが、基本的な承継手続きは同じです。
なお、これらお墓の相続手続(承継手続)も、行政書士に依頼できます。横浜市の長岡行政書士事務所でも相続手続の一環としてサポートしているため、ぜひお気軽にご相談ください
墓じまい・お墓承継のお悩みも
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
お墓は不要でも相続放棄できない
お墓が不要となった場合には、どのように扱うべきでしょうか。
実はお墓は相続財産に含まれない以上、相続放棄をすることはできません。
お墓は新しい祭祀承継者へと名義変更をしていないと管理者が不在となってしまうため、一定の期間を開けて撤去される可能性があります。遺骨も行き場を失うため、合祀されてしまいます。
お墓が不要となった場合、基本的には「墓じまい」をする必要があります。墓じまいとは墓石を撤去し、使用していた墓地を管理者側へ返還する手続きです。
関連記事:お墓じまいとは?改葬方法や相続に合わせた手続について行政書士が解説!
お墓が祭祀承継者の近くに立地しておらず、管理の手が行き届かない場合は墓じまいを行い、お近くにお墓を新設したり、納骨堂へ移設することがおすすめです。専門家に相談しながら進めると良いでしょう。
実はお墓じまいは、行政書士の専門分野の一つでもあります。お墓じまいをする際には「改葬許可証」というものが必要となり、行政への手続が発生するためです。
横浜市の長岡行政書士事務所では、お墓じまいのサポートにも対応しています。もしお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
墓じまい・お墓承継のお悩みも
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
お墓を円満に承継する3つのコツ
さて、最後にお墓を円満に承継する3つのコツを紹介します。
- あらかじめ祭祀承継者を決めておく
- 管理・処分の方法を家族で話し合う
- お墓の移転も検討する
それぞれ具体的に紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
あらかじめ祭祀承継者を決めておく
祭祀財産は、長年大切にしてきた家系図や位牌なども含まれます。複数の親族で祭祀財産を管理すると、飛散や破損などが心配される場合は、あらかじめ終活の一環として遺言書を使い祭祀承継者を決めておくこともおすすめです。
祭祀承継者は誰でもなれます。ご近所に住まわれている親族や、内縁の方なども可能です。
もしまだ相続が発生していないタイミングなら、誰か信頼できる方を指定しておくといいでしょう。
管理・処分の方法を家族で話し合う
近年お墓や仏壇は管理が難しいと感じる人が多く、墓じまい以外にも仏壇処分を検討する人も多くなっています。しかし、長年大切にされてきた祭祀財産を処分することには、反対の意見を持つご家族も多いでしょう。
そこで、墓じまいをはじめとする祭祀財産の管理や処分の方向性については、早めに家族で話し合うことがおすすめです。管理者が1名だと負担が多い場合は、複数の親族の協力を依頼したり、仏壇を入れるスペースがない場合は買い替えも検討してみましょう。
祭祀財産は相続税の課税対象ではないため、生前にお墓や仏壇を買い替えることは、相続税の節税効果もあります。
ただし、過度に高い祭祀財産の購入は相続税が課税されるおそれもあるためご注意ください。
お墓の移転も検討する
お墓は維持したい、でも遠すぎて管理が難しい…このような場合には、お墓の移転も考えてみましょう。お墓は手続きを行うと移転できる場合があります。遺骨の移転をともなう場合は行政機関への手続きを要する場合があるため、早めに調べておくことがおすすめです。
埋蔵・収蔵されている遺骨などを、他の墓地・納骨堂に移す行為は「改葬」と呼ばれており、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定に従い、「改葬許可申請」という手続きが必要です。
行政書士は「改葬許可申請」を扱えますので、横浜市の長岡行政書士事務所にお気軽にご連絡ください。
なお、横浜市の場合、新しく墓地を購入するなど改葬先を決めた上で手続きを進める必要があります。詳しくは以下リンクをご一読ください。
参考URL 横浜市 改葬(遺骨の移動)の手続き
お墓の相続(承継)やお墓じまいは長岡行政書士事務所にご相談ください
この記事ではお墓の相続について、祭祀承継者や祭祀財産についても触れながら詳しく解決を行いました。お墓などの祭祀財産は相続財産には含まれないため、相続放棄をしても承継できる一方で、放棄をすることができません。
お墓を引き継ぐ手続や、お墓じまいをする手続は、どちらも行政書士の専門分野です。もしお墓についてお悩みの方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しています。