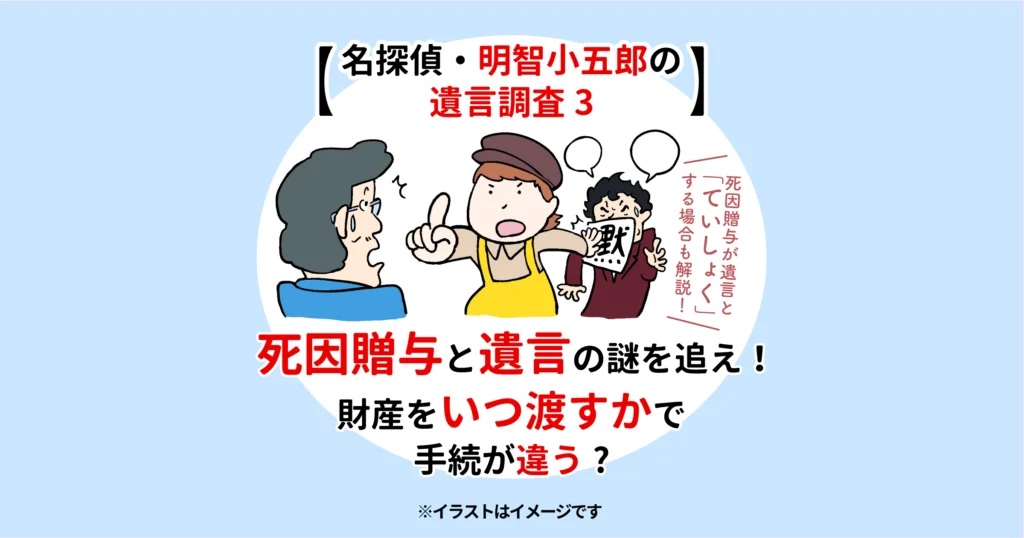「遺言書に書かれている内容に不備があったら無効になってしまい、遺言書の内容を実現できない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、遺言書に不備があると、その内容を実現できないこともあります。
しかし状況によっては、「死因贈与」という形で手続を進められることもあるのです。
この死因贈与とは、遺贈とは異なるものなので、少し注意しなければなりません。
そこで今回は死因贈与の概要や遺贈との違い、活用シーンについて、難しい話になりすぎないよう物語風に解説します。
死因贈与とは
死因贈与とは、自分自身が亡くなった時に財産を贈与する契約です。
遺言書については、本人が自分の意思で用意できます。
しかし死因贈与は契約ですから、自分の一方的な意思表示だけでは成立せず、通常の契約と同じように、相手方(財産をもらう側)の意思が一致している必要があります。
死因贈与の活用シーン
死因贈与の活用シーンの代表例は、遺言書に不備があった場合です。
分かりやすく場面を想像してもらうために、とある名探偵の物語風に進めていきます。
やあ、みなさん。お元気でいらっしゃいますか?
ぼくは名探偵として知られる明智小五郎先生の事務所で働く、助手の小林です。
遺言書に不備がある、という相談がうちの探偵事務所に舞い込んできたので、順を追って状況を紹介しますね。
X氏「私は長男で妹が一人いますが、先日、母が亡くなりましてね。父はすでに他界しており、母は自宅で一人暮らしをしておりましたが、高齢のため介護が必要な状態で、私の妻が実家に通い、介護をしてきたんです」
小林「それは奥様、大変でしたね」
X氏「母は生前、言っていました。『Y子さん(妻)には世話になっているから、A銀行の預貯金はY子さんに残したいんだよ』って。妻も了承しており、母の死後、自宅に保管してあった遺言書にもその旨が記載されていたんです」
小林「自分がお世話になったから、お母様からのお礼なんでしょうね。ねえ、明智先生」
明智「ふん。そんな美談で終わればいいがな」
小林「ちょっと、先生!」
X氏「美談…確かに。明智先生の言う通り、そのあとが問題でした。私の妹が、その遺言書は押印がされておらず無効だと言い出したんですよ。それで、法定相続による手続きをすべきだとまで主張してきました」
明智「よっしゃ、ビンゴ!」
小林「そこ喜ぶところじゃないですって。でも押印がなかったのかあ…それは痛いなあ。自筆証書遺言は、遺言を作成する人が、全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することが求められていますから、これらのうちどれか一つを欠いても無効になっちゃいます」
X氏「妹は、ちょっとお金で困っているところがあったそうでしてね。ですので、起死回生のチャンスだとでも思ったのでしょうか。明智先生、このような場合、母から伝えられていた妻への遺贈は認められないのでしょうか…」
明智「…わからん」
X氏「わからんって、そんなご無体な」
小林「あ、すみません。先生は名探偵なんですけど、本当にわからないんです。この事務所では経理兼総務兼行政書士兼雑用兼先生のご機嫌取りという名の調教兼先生が推理を外した時のフォロー役を、ぼくがやっていますので」
X氏「…働き方改革、ちゃんとできてます?」
明智「心配するな。ここでは私が神であり、法律だ。したがって妻への贈与は認めん。なぜなら事件的におもしろくなくなるからだ」
X氏「そ、そんな…」
小林「うん、もうハッキリ言っちゃう。おい明智、黙っといて。Xさん、心配しなくていいですからね」
X氏「小林さんも大変そうですね…」
小林「そうなんですよ。だから最近、明智先生と親しい長岡真也先生がいる、横浜市の長岡行政書士事務所への転職をこっそり考えているくらいでしてね…」
明智「…小林くん、愚痴なら本人がいないところで言いたまえ」
小林「ひとまず整理すると、お母様から生前に伝えられた『A銀行の預貯金はY子さんに遺す』という約束は、死因贈与にあてはまる可能性があります」
X氏「死因贈与?」
小林「つまり、自分自身が亡くなった時に財産を贈与する契約です。契約ですから自分の一方的な意思表示だけでは成立せず、通常の契約と同じように、相手方の意思が一致する必要があります」
X氏「つまり合意が必要というわけですね」
小林「はい。この合意は書面で残さなくても、口頭でも有効に成立します」
X氏「でも、自筆証書遺言が無効なんだから、妹の主張は正しくて、遺言による妻への預貯金の遺贈は認められないってことになるわけですよね」
小林「そうとも限りません。今回は遺言者が生前に特定の人へ財産を残したいという意思を明らかにしていますし、その特定の人もその意思を受け入れて両者がその状態を認識しています。遺言としては無効であっても、死因贈与として有効とする裁判例もあるんです」
死因贈与と遺言が抵触する事項がある場合はどうなる?
小林「ちなみに…いま見せていただいている遺言書を見る限りは、今回の死因贈与契約の内容と、遺言の内容は抵触してはいないようですね」
X氏「テイショク?」
小林「抵触というのは矛盾するかどうかってことです」
X氏「ああ、なるほど」
小林「例えば、明智先生が死因贈与契約で『不動産●●』を小林に贈与する」としていたとしましょう」
明智「絶対しないがな」
小林「例えですよ!でも遺言書で『不動産●●』をお友達の長岡先生に贈与する」としていたとしましょう」
明智「絶対しないがな」
小林「長岡さん、泣きますよ…そんなにつれないと。あ、そうだ、明智先生、ちょっとこれ電話で聞いてみてください」
明智「また上司をこき使う気か? まったく…」
小林「ほら、テキパキ動く!Xさん、失礼しました、こちらのことで。ともかく、この場合、明らかに、ひとつしかない『不動産●●』について矛盾していますよね?」
X氏「確かに抵触している状態ですね」
小林「この場合は日付が新しいものが優先されるんです。民法でそう決められており、死因贈与についても『贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する』と明記されているんです」
X氏「ふうむ、いろいろあるんですね」
合わせて読みたい:遺言書が2枚以上出てきたらどうする?複数枚の遺言の優先順位について行政書士が解説!
死因贈与は相続税の対象?
小林「あと、お伝えしておいた方がいいのは、死因贈与と遺言による相続手続きですね。そもそも死因贈与は贈与税ではなく相続税になるんです。つまり、遺言による遺贈の場合と同じです」
X氏「えっ? 贈与契約なのにですか?」
小林「ええ。死因贈与によって財産を受け継いだ場合は、通常の相続税の申告と同じように、相続が発生してから10か月以内に相続税申告書の提出と相続税の納税が必要です。
不動産の相続の場合は、不動産の所有者変更に伴って登記と名義変更を行いますが、その際、登録免許税を納め、それに伴い不動産取得税がかかります。
死因贈与の対象となる財産が不動産の場合には、この不動産取得税と登録免許税の税率が遺贈とは異なっており、死因贈与の方が高く設定されています」
X氏「なんだかいろいろややこしいなあ…」
小林「そうですよね。ですので、自分一人で考えず、専門家に相談しないと、こんがらがっちゃうと思います」
X氏「ちなみに、その税金って高いんですか?」
小林「相続税の計算には、「相続税の2割加算」という制度があるんです。配偶者と一親等の血族以外の人が相続や遺贈により財産を取得した場合、相続税が2割増し(1.2倍)になる制度で、死因贈与の場合もこれがあてはまります」
関連記事:相続税額の2割加算とは?対象者や計算方法について税理士が解説!
死因贈与と遺贈の違い
それでは最後に、死因贈与と遺贈、それから通常の相続との違いについてまとめてみましょう。
| 比較項目 | 相続 | 遺贈 | 死因贈与 |
| 概要 | 被相続人の死亡で生じる権利・義務の承継 | 遺言による贈与 | 贈与者の死亡で効力が生じる贈与契約 |
| 財産をもらう人 | 被相続人の相続人 | 遺言者で指定した受遺者(相続人以外の第三者も可) | 贈与契約の当事者(受贈者) |
| 法的性質 | 相続 | 単独行為(受遺者の合意は不要) | 契約(受贈者の合意も必要) |
| 利用方法 | 死亡により開始する | 遺言に遺贈する旨を記載する | 書面や口頭で生前に贈与契約を結んでおく |
| 効力発生時期 | 被相続人の死亡時 | 被相続人の死亡時 | 贈与者の死亡時 |
| 課税される税金 | 相続税 | ||
亡くなった方の財産を渡すという点や、相続税の課税対象という点では似ていますが、相続・遺贈・死因贈与はそれぞれ性質が異なる部分も多いため、どのように手続を進めたらいいのか分からない場合には、専門家に相談することをおすすめします。
明智「やれやれ、小林くん。ほら。電話したぞ」
小林「ありがとうございます…ほう。Xさん、関係ないことはなさそうですね」
X氏「どういうことです?」
小林「公証役場に問い合わせてみたら、お母様、自筆証書遺言を書かれた後に、公正証書遺言を遺されています。この遺言は有効ですね。日付も最も新しいようですから、ここに死因贈与のことが書かれていれば…」
X氏「…母と妻の思いをかなえられるんですね! ありがとうございます!」
小林「さあ、ではより詳しくお話をしましょうか。あ、明智先生、まだいたんですか? もう帰っていいですよ」
明智「本当に、どっちが上司かわからんな…」
横浜市の長岡行政書士事務所では、相続にかかわる手続を承っていますが、死因贈与についてもご相談いただけます。何かお悩みのことがある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。