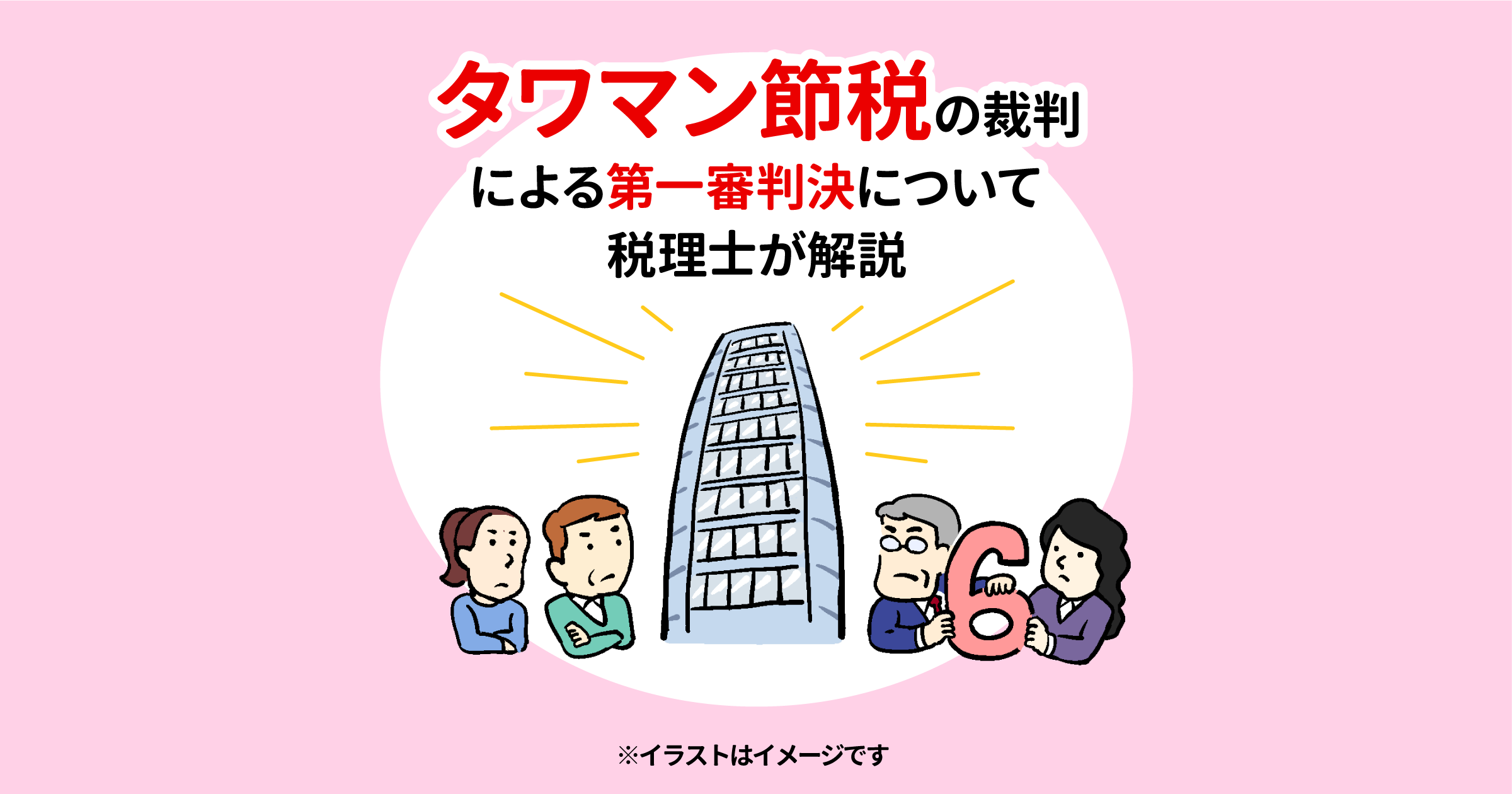相続税の算出のために財産を評価するときは、「財産評価基本通達」に則って評価することが多いです。ただし相続手続きの実務においては、財産評価基本通達による評価(原則)と財産評価基本通達6による評価(例外)のいずれで評価するか、判断しなければなりません。
関連記事:財産評価基本通達とは?「相続税法の時価」との関係や存在意義を税理士が解説
関連記事:財産評価基本通達6で争われた裁判例を税理士が解説【相続税の豆知識】
上記の記事では「財産評価基本通達6項」が適用された裁判例を検証しました。ご覧いただければ、財産評価基本通達6項が適用される局面についてイメージができるでしょう。
さて、「財産評価基本通達6項」に関連して、最高裁まで争われたタワマン節税にまつわる有名な裁判があることをご存知でしょうか。後に「タワマン節税」にメスが入った要因の一つでもある重要な裁判です。今回の記事では、この裁判の第一審判決を詳しく解説していきます。
「タワマン節税」裁判の経緯・事案概要
まずはこの「タワマン節税」裁判が、どのような経緯で争われたか順を追ってみていきましょう。
【概要】
納税者が相続により取得した土地、建物(以下、不動産という。)を評価通達により評価して申告したところ、 課税当局がこの不動産について、評価通達により評価することが著しく不適当と認められるとして、鑑定評価額に基づいて更正処分を行ったことに対し、その取消しを求めた事件
問題となった不動産
被相続人は平成24年6月に94歳で死亡して相続が開始し、納税者は遺産分割によって相続財産を取得しました。相続財産には「杉並区の不動産」と「川崎市の不動産」などがあります。これら各不動産は、被相続人の遺言により、納税者が取得しています。
杉並区の不動産
杉並区の不動産は、被相続人が平成21年1月に8億3,700万円で購入し、同日付けで銀行から6億3,000万円を借入れていています。
同銀行がその際に作成した貸出稟議書欄には「相続対策のため不動産購入を計画。購入資金につき、借入の依頼があったもの。」との記載があります。
川崎市の不動産
川崎市の不動産は、被相続人が平成21年12月に5億5,000万円で購入し、同月付けで「被相続人の妻から4,700万円」「銀行から3億7,800万円」を借り入れています。
同銀行がその際に作成した貸出稟議書には「相続対策のため本年1月に6億3,000万円の富裕層ローンを実行し不動産購入。前回と同じく相続税対策を目的として第2期の収益物件購入を計画。購入資金につき、借入の依頼があったもの。」との記載があります。
納税者は相続した後に、平成25年3月に川崎市の不動産を総額5億1,500万円で売却しています。
争点
納税者らは、相続税申告で評価通達による評価方法により各不動産を評価していますが、課税当局は評価通達による評価によると著しく不適当と認められる特別の事情があるものとして否認しています。
つまり本件の争点は相続開始時における各不動産の時価です。
そして”評価通達による評価方法”によらない評価が許されるための「特別の事情」の存否が争われています。
「タワマン節税」の第一審判決
第一審判決の「課税当局の主張」と「納税者の主張」をそれぞれ見て、最後に「裁判所の判断」について紹介します。
課税当局の主張
まず課税当局の主張を見ていきます。
各不動産の評価においては、以下のとおり、”評価通達による評価方法”によらないことが相当と認められる「特別の事情」があるとして主張しています。
各通達評価額と各不動産の時価との間に著しい乖離があること
杉並区と川崎市の不動産に係る通達評価額は、「不動産鑑定評価額」の僅か約25~26%にすぎず、著しい価額の乖離があるとしています。
そして杉並区と川崎市の不動産に係る通達評価額と「不動産購入額」を比べてみても、通達評価額は不動産購入額の僅か約23~24%にすぎず、両者には著しい価額の乖離があるとしています。
また、川崎市の通達評価額は「不動産売却額」の約26%にすぎず、著しい価額の乖離があるとしています。
各不動産に係る被相続人らの一連の行為について
被相続人及び納税者による各不動産の取得と資金借入れの一連の行為は、納税者らが「本来負担すべき相続税を免れる」という結果をもたらすもので、相続対策を目的とするものであったのではないかと指摘しています。
被相続人は、各不動産の購入資金の大半を銀行からの借入金により調達し、その借入金の総額は「各通達評価額」を上回り、課税価格を圧縮する多額のものであったから、相続において各不動産の価額を「通達評価額」で評価すると、納税者らが各不動産を取得しなかったならば負担していたはずの相続税を免れる利益を享受するという結果を招いています。
これは被相続人が相続税の負担の軽減策を採ったことによるものであり、これは「同様の軽減策を採らなかった他の納税者」との間の租税負担の公平を著しく害し、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反する著しく不公平なものであると指摘しています。
以上から、各不動産の評価について、評価通達による評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであると主張しています。
納税者の主張
次に納税者の主張を見ていきます。
納税者は、各不動産の評価を「評価通達による評価額」が正しいものとして、評価通達による評価方法によらないことが相当と認められる「特別の事情」は無いと主張しています。
各通達評価額と鑑定評価の乖離について
評価通達による「路線価方式」は合理性があるものとして広く社会に受け入れられているから、本件のように「評価通達による評価額」と「鑑定評価額」に数倍もの乖離がある場合、鑑定評価額の適正さに疑問が呈されるべきであるとしています。
また、「評価通達による評価額」と「鑑定評価額」の差が著しいと思われる場合は稀ではなく、その場合に全て評価通達6が適用されているわけではないとしています。
評価通達の位置づけ
「評価通達による相続財産の評価」は合理性があるものとして実務界において運用されており、評価通達は、行政先例法としての地位を築いているとしています。
そして、例外的に上記方法による評価額を否定し、これによらない評価を認める「評価通達6」の制定趣旨は、対象財産につき想定外の時価の下落事情が事後的に生じた場合に、評価通達が形式的に適用され、納税者の担税力が過大に測定されることの救済措置を設けた点であるとしています。
特別の事情について
評価通達6の「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる場合」とは、時価評価に影響を及ぼす「特別の事情」があり、評価通達によると実質的な課税の公平を確保できない場合を指すと解すべきであるとしています。
特別の事情は、災害、地盤沈下等の客観的事情の発生に限られなくてはならないとし、時価評価に影響を及ぼすことのない、納税者等の節税目的や租税回避の目的といった主観的要素や相続開始前後の一連の行為は、上記の特別の事情を基礎付けるものではないとしています。
裁判所の判断
課税当局の主張と納税者の主張をそれぞれ見てきたので、第一審判決の裁判所の判断を見ていきたいと思います。
特別の事情の有無
特別の事情の有無については、次の2つの観点から見ていきます。
- 著しい乖離について
- 各不動産に係る被相続人らの一連の行為
〈著しい乖離について〉
各不動産の通達評価額は、それぞれ各鑑定評価額の約4分の1にとどまっています。
そして被相続人らが各不動産を売買した価格を見ていきます。
杉並区の不動産
相続開始時から約3年半前の取引(購入)であるとはいえ、不動産鑑定評価額より購入金額のほうが8,300万円高額であり、通達評価額からの乖離の程度は、不動産鑑定評価額よりも更に大きいものであったとしています。
川崎市の不動産
相続開始時の約9か月後の取引(売却)において、おおむね不動産鑑定評価額と同程度で売却されています。
納税者らは、「評価通達による路線価方式」は合理性があるものとして広く社会に受け入れられており、「各通達評価額」と「各鑑定評価額」の乖離からすれば、各鑑定評価額の適正さに疑問があると主張しています。
しかし、各取引額が市場価格と比較して特別に高額又は低額であったことをうかがわせる事情は見当たらず、それが各鑑定評価額と概ね同じくらいとすれば、納税者らの主張は採用することができないとしています。
〈各不動産に係る被相続人らの一連の行為〉
各不動産が相続財産に含まれることとなった経緯についてみると、各借入れと各不動産の購入がなければ、課税価格は6億円を超えるにもかかわらず、各借入れと各不動産の購入がされたことにより、各通達評価額と比較して借入金債務が多額となることにより、その差額が各不動産を除く相続における財産の価額から控除され、申告による課税価格は、基礎控除の範囲内になり、相続税は課されないことになりました。
さらに銀行が各借入れに際し作成した各貸出稟議書の記載や証拠にもよれば、被相続人らは、各不動産の購入及び各借入れを、被相続人等の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将来発生することが予想される被相続人の相続において納税者らの相続税の負担を免れさせるものであることを知り、かつ、それを期待して、あえてそれらを企画して実行したと認められ、これを覆すに足りる証拠は見当たらないとしています。
評価通達6の判断
納税者らは、評価通達6に規定する「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる」場合とは、飽くまで「時価評価に影響を及ぼす特別の事情」がある場合を指すと解すべきであり、時価評価に影響を及ぼすことのない、「納税者等の節税目的や租税回避の目的といった主観的要素」又は「相続開始前後の一連の行為」は、特別の事情を基礎付けるものではないとした上で、各不動産につき、想定外の時価の下落事情は生じておらず、特別の事情はないと主張していました。
しかし、評価通達による評価方法以外の評価によって特定の納税者あるいは特定の財産について評価することが許されるか否かは、評価通達による評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の公平を著しく害することが明らかである特別の事情があるか否かという観点から判断されるべきものであるから、納税者らの上記主張はその前提を異にするものであるとしています。
まとめ
第一審判決では課税当局の主張である評価通達6により各不動産は鑑定評価額で評価することが適正であると裁判所は判断しました。
控訴審判決や最高裁判決ではどのような主張があったのか次回の記事で詳しく見ていきたいと思います。