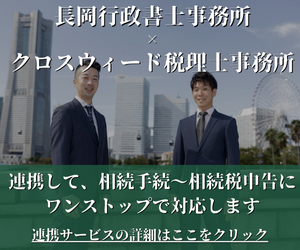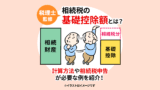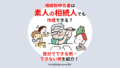へそくりと聞くと、家庭内のちょっとした秘密のように思われがちですが、税務の世界では立派な“財産”として扱われることがあります。
今回の記事では、主に、夫が亡くなった時に配偶者(妻)がへそくりを貯めていた場合について、そのへそくりが相続税申告の対象になる理由と、その対策について税理士が解説します。
へそくりの税務上の考え方
へそくりとは世間一般に「妻(もしくは夫)が生活費のやりくりで貯めた“内緒のお金”」だといえます。
自宅内で保管していれば、タンス預金の一種だといえます。
妻名義の銀行口座に、コツコツと貯めていることもあるでしょう。
いずれにせよ、妻が生活費の中から貯蓄している資金=へそくり、というケースが多いですが、ここで着目すべきは、形式的な名義よりも「資金の出所」と「実質的な管理権限」です。
たとえば、専業主婦のへそくりは、原資が夫の給与であれば、税務上は「夫の財産」と判断される可能性があります。
へそくりが相続税の課税対象となる理由
相続税は「被相続人(亡くなった人)の財産」に課税されます。
そのため妻がへそくりを貯めていても、資金の出どころが夫のものであれば、夫が被相続人となった場合には、立派な相続財産となります。
へそくりを貯めている口座名義が妻であっても、通帳・印鑑の管理実態や入金記録から、被相続人(夫)の財産と認定されることもあるのです。
このようなへそくりが、税務調査で「名義預金」として申告漏れを指摘されるケースが増えています。
関連記事:名義預金とは?注意点や対策方法を解説!【税理士監修】
へそくりを申告しなかった場合のリスク
後日、相続税の税務調査でへそくりが発覚すると、重加算税・過少申告加算税・延滞税が課される可能性があります。
本来支払うべき税金に加えて上記のようなペナルティを支払うことになるので、税負担が増えることになるということです。
へそくりの相続対策と節税ポイント
思いがけず税務トラブルを引き起こさないよう、へそくりを貯めるときは、次のポイントに注意してみてください。
- 生前贈与を活用し、夫から妻へ正式に贈与契約を結ぶ(年間110万円まで非課税)※
- へそくりの出所を明確にし、通帳・管理状況を整備する
- 相続税の申告時には、へそくりを正直に申告することが最善
※なお、相続開始日によっては、生前贈与加算の対象になる可能性がありますので、注意が必要です。
これらの方法では「へそくりとは言えない!」と思う方もいるかもしれません。
しかし、やはり相続税申告が必要な程度に財産がある方、つまり「3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)の基礎控除」を超える財産がある方は、へそくりの扱い方にも十分に注意すべきでしょう。
関連記事:相続税の基礎控除額とは?計算方法や相続税申告が必要な例を紹介!【税理士監修】
へそくりに「配偶者の税額の軽減」を活用することも可能
実は配偶者が相続する財産は、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは、相続税がかからないという制度があります。
ただし、この制度を適用するには相続税申告は必須です。
配偶者の税額の軽減を使おうとしても申告しなければ無申告扱いになるので注意が必要です。
まとめ
相続税申告は「形式」だけでなく「実質」にも着目します。へそくりという一見軽視されがちな項目であっても、申告漏れが無いように必ず申告すべきでしょう。
そのうえで、配偶者の税額の軽減などの特例を適用できるケースもあるかと思いますので、ぜひ一度税理士に相談してみてください。