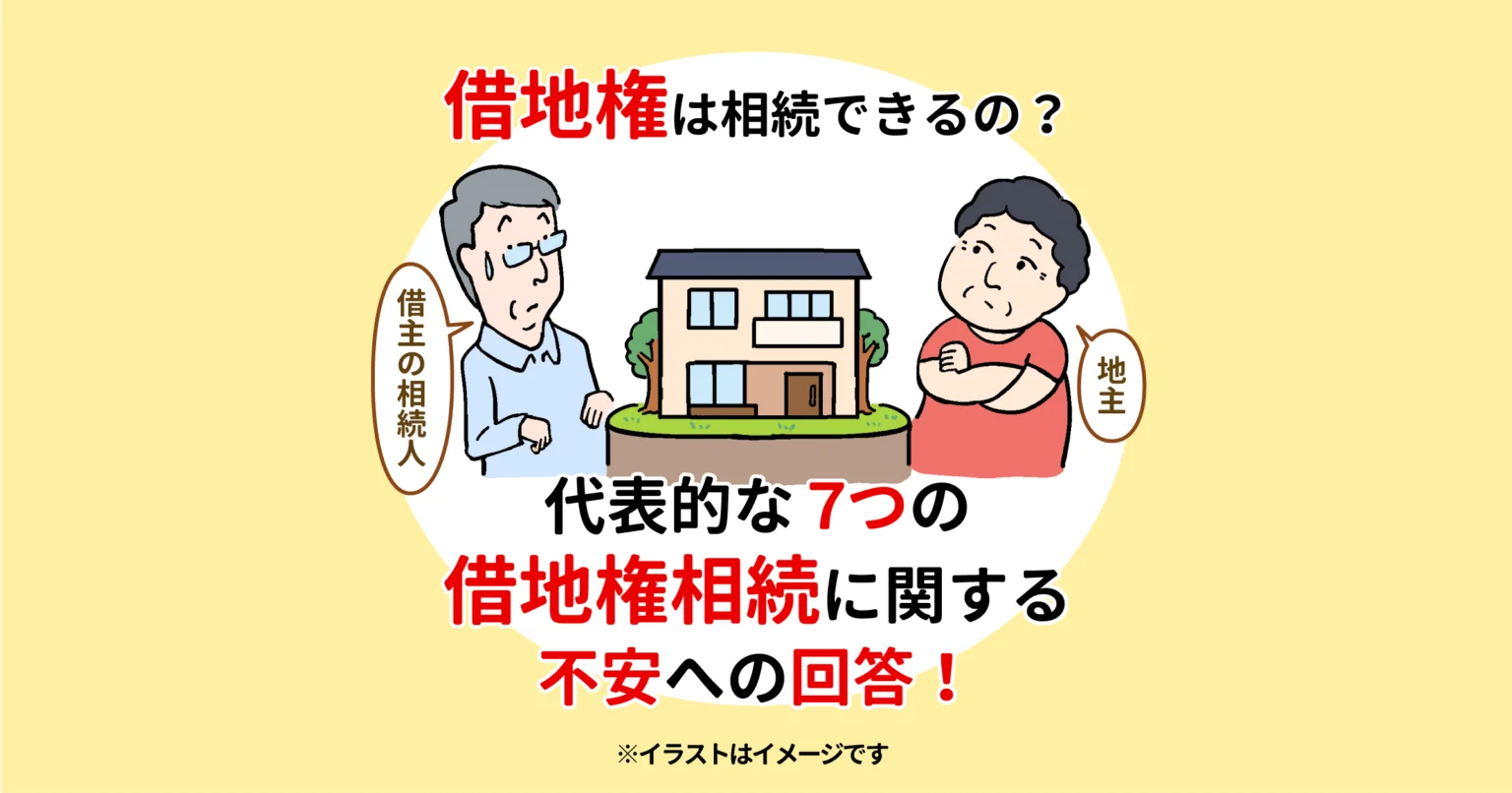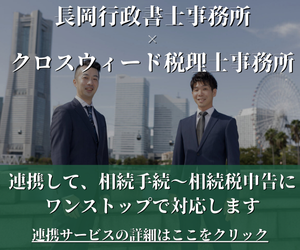「実家が借地に建っているのだが、そもそも、借地権を相続することは可能なの?」
「借地権は地主に何も言わずに相続手続を進められる?相続後に地主から色々言われそうで怖いわ」
「借地権を相続したら立ち退かないといけないの?」
借りている土地の上に建っている家を相続したあと、地主から急に土地を返せと要求されたらどうしたらいいのでしょうか。
おとなしく土地は返すべきなのでしょうか。
であれば、その上に建っている私の家はどうなるのでしょうか。
そもそも、地主から借りている土地を相続できるのでしょうか。
ちょっと考えただけでも疑問が湧いてきますね。
そこでこの記事では、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が、借地権の相続について解説します。
主の相続手続の流れや注意点を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
借地権も相続できる
結論から言ってしまうと、借地権も相続できます。
借地権は財産権の一種ですので、借主の死亡によって終了するという契約内容でない限りは、故人(被相続人)の遺産として相続の対象となります。
相続によって借地権が承継された場合には、地主の承諾は不要ですし、譲渡承諾料(名義変更料)を支払う必要もありません。
また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。地主に対して「土地の賃借権(もしくは地上権)を相続により取得しました。」と通知するだけで十分です。
仮に「被相続人と一緒に住んでなかったので土地を返してほしい」という要求が地主からあったとしても、同居の事実の有無は、借地相続とは関係ありません。
借地相続で借主が知っておくべき注意点
借地権も相続できますが、そうはいっても実際に相続が発生すると、地主(貸主)から色々と要求されることがあります。そのような場合に毅然と対応するためにも、次のポイントは押さえておきましょう。
- 借地権の相続に地主の承諾は必要ない
- 相続タイミングでの立ち退き請求は原則できない
- 相続タイミングでの借地権の地代値上げは原則請求できない
- 相続タイミングでの名義変更料や更新料は求められない
- 相続した建物の増改築は原則地主の承諾が必要
- 借地上の建物を借地権ごと売却する場合は原則地主の承諾が必要
それぞれ詳しく解説します。
借地権の相続に地主の承諾は必要ない
先ほども紹介しましたが、借地権は財産権の一種です。そのため「借主の死亡によって終了する」などの契約内容でない限りは、故人の遺産として相続できます。
ここに地主の承諾は必要ありません。
もし地主から「相続は認められない!」などといわれても、借地権は原則として相続できます。
相続タイミングでの立ち退き請求は原則できない
借地権を相続するタイミングで、地主から立ち退きを要求されることがあります。
一つの区切りとしてここで土地の貸し借りを清算したい、という心理が働くようです。
しかしながら、地主が立ち退きを請求するには法的な「正当事由」が必要です。
相続が発生したからだけでは正当事由にはならず、したがって立ち退きに応じる必要はありません。
過去の判例によると、裁判所は下記の点を総合的に判断し個別の案件ごとに立ち退き要求の正当性を審査しています。
地主が土地の使用を必要とする事情がある(東京地裁平成3年6月20日判決 等)
例えば、地主が他に土地を所有しておらず、自分が住むための家を建てるため貸している土地を返してもらう必要がある、等です。
借地契約に関する従前の経過(東京地裁昭和63年5月30日判決 等)
借地に関する従前の経過とは、「地代がしっかりと支払われ続けてきたか」「支払いの延滞や滞納などはないか」「契約更新料の授受はあったか」など、これまでの借地契約の内容を考慮するものです。
土地の利用状況(最高裁昭和56年6月16日判決 等)
例えば借地人が建物を居住用ではなく事業用として使用している場合は、借地人の生活を守るためという必要性が弱くなります。
地主が立ち退き条件として立ち退き料の支払いを申し出ている(最高裁判例昭和32年3月28日 等)
立ち退き料の支払いにより地主側の正当性が認められるわけではないですが、一つの考慮対象となり得ます。
相続タイミングでの借地権の地代値上げは原則請求できない
立ち退きとまではいかなくても、相続を契機に地主が借地権の地代を値上げしたいと要求をしてくるケースです。
借地権の相続はこれまで同条件で継承するのが原則なので、相続したからという理由で地代の値上げに応じる必要はありません。
では、地主に地代の値上げができないかというとそんなことはなく、借地借家法第11条では増額請求できる条件として以下の3点を挙げています。
- 土地の固定資産税・都市計画税の増加があったとき
- 地価の上昇があったとき
- 近隣の似た土地における地代と比較して不相当に安い地代となっているとき
ただし、相続は上記条件に含まれておりません。
増額請求の可否はあくまで双方の合意のもとで決まるのなので、もし要求された金額に納得ができないのであれば、話し合いや調停、それでも決まらなければ訴訟という順序で最終的な地代が決まることになります。
相続タイミングでの名義変更料や更新料は求められない
立ち退きや地代の値上げではないですが、相続時に地主から名義変更料(承諾料)もしくは借地権の更新料を支払ってほしいと要求されることがあります。
そもそも借地権の「譲渡」をするときは地主の承諾が必要なため、譲渡を認めてもらうために地主に名義変更料(承諾料)を支払うケースが多いためです。
しかし借地権の相続は譲渡に該当しないので、地主の承諾は必要ありません。
よって名義変更料(承諾料)もしくは借地権の更新料を支払う必要はありません。
なお、相続に伴い、借地の賃貸借契約書の名義を書き換えることは法的には必要ありませんが、相続した際はできるだけ早い段階で書き換えたほうがいいでしょう。
いずれ借地権を売却したいと考えた時に取引を滞りなく進めるためです。
相続した建物の増改築は原則地主の承諾が必要
借地契約の内容によりますが、相続した建物を増改築する場合は、原則地主の承諾が必要です。
借地契約書の中では、地主の承諾なしに借地上の建物の建て替えを禁止し、建て替えなどをする場合には事前に地主の承諾を必要とするという文言が入っていることが多いです。これを「増改築禁止特約」といいます。
増改築禁止特約が定められて、かつ地主からの承諾が得られない場合には、承諾料などについて地主と交渉する必要があります。
相続を機に建物の増改築を進めたいという方も多いとは思いますが、トラブルを引き起こさないためにもまずは借地契約の内容をチェックしてください。
借地上の建物を借地権ごと売却するの場合は原則地主の承諾が必要
遠方の実家を相続した場合などが考えられますが、借地上の建物を、借地権とセットで第三者へ売却することも可能です。
ただし、借地権には地上権と賃貸権の2種類あり、相続した借地権がどちらなのかにより、売却する場合に地主の承諾が必要かの対応が変わります。
- 地上権:地主の承諾がなくても、建物を貸したり売却できる
- 賃貸借:地主の承諾がないと、建物を貸したり売却はできない
この違いは、借地権を設定した際に地主と被相続人がどのように合意したかによります。
まずは契約書の内容をチェックし、地主の承諾が必要かを確認しましょう。
もし設定された借地権が賃借権で、売却したいのに地主の承諾が得られない場合は、買主と話がまとまっていても地主により借地契約を解除される可能性があります。
どうしても借地権の売却を地主が承諾しない場合は、借地借家法第19条により裁判所に地主の承諾に代わる許可(代諾許可)を求めることができます。
また、借地上の建物を売却する場合、買い主が住宅ローンを組むためには地主の承諾が必要です。
建物が気に入り買う気になっても、地主から承諾をもらわないとローンが組めないと知り、二の足を踏んでしまう買主は多いでしょう。
金融機関も借地上の建物の場合は地主の承諾を求めてきます。
また、ローン承諾は法律で定められているものではないため、前述の譲渡の承諾と違い裁判所に代わりの許可を求めることはできません。
借地を相続する流れ
借地を相続する流れそのものは、比較的シンプルです。
- 借地権の契約内容を確認する
- 地主へ連絡をする
- 借地権を相続する人を決める
- 借地権付き建物の名義を相続人に変更する
借地権の契約内容を確認する
まずは相続人の判断材料とするために、借地権の契約内容も確認しておきましょう。
故人が結んだ「土地賃貸借契約書」を探し、地主の情報・借地権の種類・契約期間・地代などを把握します。
また、借地権付きの建物だけではなく、借地権そのものを登記することも可能です。借地権が登記されているかどうかはケースバイケースですが、正確な情報を把握するためにも、登記の有無を確認してみてください。
地主へ連絡をする
先述したとおり、借地権の相続には、原則として地主の承諾は必要ありません。また、名義変更料も不要です。
ただし、その後も地主と円満な関係を続けるためには、相続が発生した旨は伝えておくことをおすすめします。
まだ誰が借地権を相続するか決まっていないとしても、第一報は入れておいたほうが、後々の関係にはプラスに働くでしょう。
借地権を相続する人を決める
つづいて、借地権を相続する人を決めます。
もし遺言書で借地権を継ぐ人が指定されていれば、それに従うのが前提です。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」によって、借地権を相続する人を決めます。
この流れは、借地権以外の財産と変わりありません。
借地権付き建物の名義を相続人に変更する
借地権を継ぐ人が決まったら、借地権付き建物の名義を、相続人に変更します。いわゆる相続登記です。
なお、もし建物を相続するのではなく、借地権ごと建物を売却してから相続したい場合には、原則として地主の承諾が必要となります。
このような、状況に応じた相続手続の流れが分かりづらいと感じる場合には、行政書士など相続手続に慣れている専門家に相談することをおすすめします。
借地権にも相続税がかかる
借地権を相続するときは、相続税の課税対象となることにも注意しなければなりません。
借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地が、権利のない自用地としての価額に、「借地権割合」を乗じて求めます。
借地権の相続税評価は単純ではないため、念のため税理士へ相談したほうが安心です。長岡行政書士事務所は税理士事務所とも提携しているので、お気軽にお問い合わせください。
関連記事:借地権の相続税評価について税理士が解説
借地権の相続は専門家に代行してもらえる!
借地権を相続する場合、地主からの許可は特に必要ありません。
しかし、立ち退き請求を受けたり地代の増額を求められたり、増改築や売却の場合に契約書の確認が必要であったりと知っておくべきことが多いのが実情です。
また、借地権の相続手続を進めつつ、他の銀行預貯金・自動車などの相続財産を引き継ぐ手続をするのは大変でしょう。
横浜市の長岡行政書士事務所では、相続手続全般を代行・サポートしておりますので、不安なことがある方はぜひお気軽にお問い合わせください。