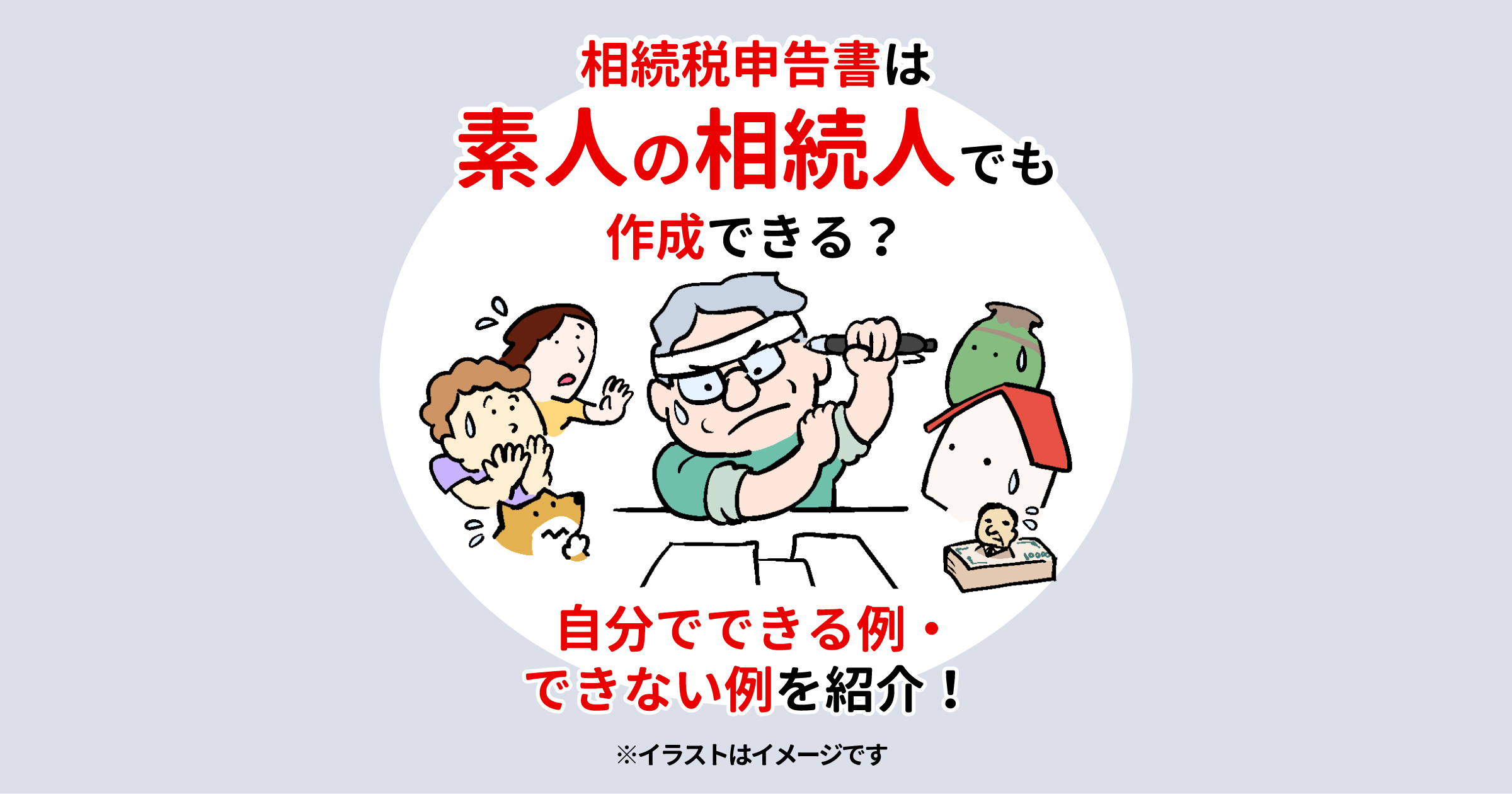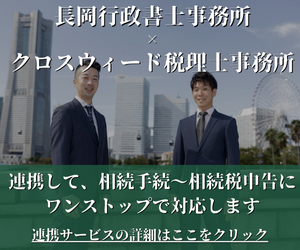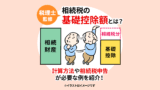相続税申告が必要な場合、自分で申告書を作成するか、税理士へ依頼するかを選ぶことになります。
もしかしたら、毎年自分で確定申告している方もいるかもしれませんが、相続税申告書も素人の相続人が作成できるのでしょうか。
今回は税理士の視点から、相続税申告書の作成を自分でできる例・できない例について紹介します。
もし、できない例にあてはまる場合は、ぜひ税理士へ相談してみてください。
前提条件として、素人が相続税申告書を作成できるといっても、相続人でもない一般の素人に作成を委託することは基本的には認められていませんので注意してください。
今回解説するのは、相続税の知識がない相続人がご自身で作成することが前提となっています。
素人の相続人がご自身で作成することもできるケース
結論から言うと、素人の相続人でも相続税申告書を作成することができるケースもあります。
相続が発生し、まずは相続人がご自身で相続税申告書の作成を試みる方はたくさんいらっしゃいます。
現実的には、相続税申告書を相続人で作成してみて、どうしても分からない部分がでてきたところで我々税理士へ相談するケースが多数見受けられます。
もし次のようなケースなら、税理士へ相談することなく、相続人だけで申告書を作成できるかもしれません。
- 財産評価が容易な相続財産のみ
- 控除・特例を適用しない
- 遺産総額が基礎控除を少し超える程度
それぞれどのような状況なのか見ていきましょう。
財産評価が容易な相続財産のみ
現預金や上場株式など、財産評価が比較的簡単な相続財産しかない場合は、相続人がご自身で相続税申告書を作成することもできるでしょう。
しかし土地などの相続財産がある場合には、財産評価の難易度はグっと上がります。
ご自身で適正な財産評価をすることは現実的ではありません。
土地の財産評価を税理士に依頼すると、不整形地の補正などをして財産評価額を減額できます。
控除・特例を適用しない
相続税の計算においては多くの控除や特例制度がありますが、これらを適用しようとすると難易度が上がります。
そのため、控除・特例を適用しないケースであれば、ご自身で相続税申告書を作成しても良いかと思います。
代表的なところを言うと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの制度があり、このような控除や特例を適用しようとすると難易度が上がりますので、ご自身での相続税申告書の作成には注意が必要です。
他の控除についても知りたい方は、「相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除について横浜市の税理士が解説」「相続税を減らすために使える「控除」の種類を税理士が解説!」もご覧ください。
遺産総額が基礎控除を少し超える程度
遺産総額が「基礎控除」を少し超える程度であれば、相続税の影響額はそこまで大きくないので、ご自身で作成することもできるかと思います。
ただし遺産総額が基礎控除を大きく超えてくると、相続税額もその分高額になることが想定されます。
控除や特例を適用して相続税額をどれだけ圧縮できるかが大事になってきますので、注意が必要です。
なお、税理士に相続税の試算を依頼して、土地の評価の減額補正をかけた結果、実は遺産総額が相続税の基礎控除以内であったというケースも珍しくありません。そのため遺産総額が基礎控除を少し超える程度だとしても、税理士へ相談することにはメリットがあります。
「相続税がかかるか知りたい」方のための資料は
こちらから無料ダウンロードいただけます。
税理士に依頼した方が良いケース
ここまでは素人の相続人がご自身で相続税申告書を作成することもできるケースを解説していきましたが、ここからは税理士に依頼した方が良いケースを解説していきます。
- 財産評価が容易な相続財産のみでない場合
- 控除・特例を適用する場合
- 遺産総額が基礎控除を大きく超える
財産評価が容易な相続財産のみでない場合
財産評価が容易な相続財産のみでない場合、とくに「土地」「非上場株式」がある場合は、税理士へ相談したほうがいいでしょう。
関連記事:相続時の財産評価とは?遺産の評価方法や注意点を解説【税理士監修】
土地があるケース
財産評価の難易度が高いものとして、代表的なものは土地の評価になります。
先ほども触れたように、土地の財産評価は単純に路線価に面積を乗ずるだけでなく、増額・減額要素があり、適正な評価をすることは難しいものとされています。
土地を正しく財産評価するには税理士に依頼した方が良いでしょう。
非上場株式があるケース
上場株式には日々市場が存在し、証券会社が財産評価の資料を提供してくれたりと財産評価は比較的容易です。
しかし非上場株式には市場が存在しないので、自らが非上場株式の評価をせざるを得ません。
よって非上場株式の財産評価は難易度が上がりますので、税理士に依頼した方が良いでしょう。
控除・特例を適用する
繰り返しとなりますが、相続税の計算には様々な控除や特例が定められています。
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などなどの控除や特例を適用しようとすると難易度が上がりますので、税理士に依頼した方が良いでしょう。
遺産総額が基礎控除を大きく超える
遺産総額が基礎控除を大きく超えるとなると、相続税額もその分高額になることが想定されます。控除や特例を適用して相続税額をどれだけ圧縮できるかが大事になってきます。
税負担を減らすためには、やはり税理士に依頼したほうが安心です。
DIYで申告するより税理士へ相談するメリットのほうが大きい
財産評価が容易な場合や、控除・特例を適用しない場合、遺産総額が基礎控除を少し超える程度の場合は、相続税申告書をDIYで作成することも不可能ではありません。
しかし先述したとおり、土地の評価の減額補正をかければ、遺産総額が相続税の基礎控除以内に収められる(相続税の納税が不要)というケースも珍しくありません。
このような計算は、やはりDIYでは難しいものです。
多くの方にとっては、DIYで申告するより税理士へ相談するメリットのほうが大きいため、相続税について少しでも悩んでいる場合はぜひ税理士へ問い合わせてみてください。