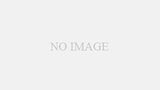「不動産以外の相続財産は遺産分割協議がまとまっている。遺産分割協議書を作って預貯金の解約を進めたいが可能だろうか?」
「亡父の遺産が多く、不動産や預貯金など、財産ごとに遺産分割協議書を作って整理したいができる?」
被相続人の相続財産(遺産)について、誰がいくら取得するか決まったら「遺産分割協議書」を作る必要があります。では、財産ごとに遺産分割協議書を作ることは可能でしょうか。
そこで、本記事では不動産と預貯金について別々に遺産分割協議書について、作成の可否や注意点を詳しく解説します。
不動産と預貯金は別々に遺産分割協議書を作成できる
結論から言うと、被相続人が所有していた不動産と預貯金については、別々の書面として遺産分割協議書を作ることが可能です。1つの書面にすべての相続財産を記載する必要はありません。
合意できた財産から遺産分割協議書を作ってOK
遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われるものです。
すべての遺産について合意に至ることが難しい場合や、一部の財産(例・預貯金など)の解約を急ぎたい場合などには、合意できた財産から順次、遺産分割協議書を作成することができます。
ただし、最終的にはすべての遺産について遺産分割協議が完了しなければ相続人への財産の分配を終えられません。部分的な協議書を作成した後も、残りの相続財産についての協議も進める必要があります。
不動産と預貯金をわけて遺産分割協議書を作るメリット・デメリット
では、不動産と預貯金をわけて遺産分割協議書を作ると、どのようなメリットがあるでしょうか。そして、知っておくべきデメリットはあるでしょうか。この章で詳しく解説します。
メリット
主なメリットは以下の4点です。
① 手続のスピードアップが可能
一部の相続財産について合意でき次第、先に遺産分割協議書を作成することで、その財産に関する手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)を先行して進めることができます。
特に預貯金は、葬祭費用や当面の生活費など、早急に資金が必要な場合に有効です。
② 部分的な合意が実現できる
相続人全員がすべての遺産について一度に合意するのは難しいケースも少なくありません。特定の相続財産をめぐって対立する場合もあります。そこで、合意形成ができる財産から協議を完了させていくことで、協議全体の停滞を防ぎスムーズな解決を目指せるというメリットもあります。
③ 納税資金を確保できる
相続税の納税資金が必要な場合、預貯金の遺産分割を先行させることで、必要な資金を早期に確保できる可能性があります。特に相続税申告が迫っている場合は、早期に預貯金だけでも先行して協議を進めることがおすすめです。
④ 不動産の売却・活用が進めやすくなる
相続した不動産を売却したり、賃貸活用や解体などを検討したりしている場合、相続登記による名義変更が必須です。不動産の遺産分割を先行させることで、不動産の売却・活用が滞りなく進められます。
デメリット
次に、遺産分割協議書をわけて作るデメリットは以下の3点です。
① 通数や必要書類が多くなる
遺産分割協議書を複数作成することになるため、その都度相続人全員の実印での押印や印鑑証明書の添付が必要になります。結果的に、作成する書類の量や手間が増える可能性があります。特に印鑑証明書は手続を求める機関によっては発行から3か月・6か月などの期限内に発行されたものを求められることがあるため注意が必要です。
合わせて読みたい:相続手続きで使う印鑑登録証明書に期限はある?行政書士が実務的に解説!
② 重複記載に注意が必要
複数の遺産分割協議書を作成する場合、それぞれの協議書にどの財産が含まれるのか、明確にわける必要があります。誤って同じ財産を複数回記載したり、記載漏れがあったりすると、後々のトラブルの原因となる可能性があります。
③ 手間が増える
各財産について個別に協議書を作成し、署名・押印や必要書類の収集を行うため、全体としての手間は増える傾向にあります。
不動産と預貯金|遺産分割協議書の作り方と注意点
実際に不動産と預貯金をわけて遺産分割協議を作る際には、どのような内容を記載する必要があるでしょうか。そこで、この章では遺産分割協議書の作り方と注意点を詳しく解説します。
不動産の遺産分割協議書の記載事項と注意点
不動産の遺産分割協議書を作る際には、主に以下を記載する必要があります。
- 被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所・本籍地
被相続人を特定するために必要です。
- 相続人全員の氏名・住所
協議に参加した相続人全員を明記します。
- 不動産の表示
登記事項証明書や権利証などに記載されているとおりに、正確な不動産に関する情報(所在や地番、地目、地積など)を記載します。
- 誰がどの不動産を取得するか
「(氏名)が次の不動産を取得する(相続する)」といった形で、取得する相続人と対象不動産を明確に記載します
- 遺産分割協議が成立した旨と日付
相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立したことを明記します。作成した日付もあわせて記載します。
- 相続人全員の署名と実印での捺印
遺産分割協議書が有効であるために必要です。署名は自筆以外に記名・代筆でも可能です。
■おもな注意点
不動産の遺産分割協議書を作成する際には、登記事項証明書などに記載されている内容を同じように記載することが非常に重要です。誤りがあると、法務局での相続登記がスムーズに進まない可能性があります。
また、不動産を共有状態で相続する場合、相続人の誰が、どのくらいの持分で共有するのかを明確に記載します。不動産を取得する相続人が他の相続人に対して代償金を支払う場合は、贈与とみなされないようにするためにも、代償金の金額や支払期日などの明記も必要です。
合わせて読みたい:代償分割すると相続税はどうなる?計算方法や譲渡所得税への影響とあわせて解説【税理士監修】
預貯金の遺産分割協議書の記載事項と注意点
預貯金の遺産分割協議書を作成する際には、主に以下の内容を記載する必要があります。
- 被相続人の特定情報
不動産と同様に、氏名や生年月日、死亡年月日、最後の住所、本籍地を正確に記載します。
- 相続人全員の氏名、住所
遺産分割協議に参加した相続人全員を明記します。
- 被相続人が所有していた口座に関する情報
金融機関名や支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人など預貯金を特定するために必要な情報を正確に記載します。
- 誰がどの預貯金を取得するか
「〇〇(氏名)が次の預貯金を取得する」といった形で、取得する相続人と対象預貯金を明確に記載します。
- 「下記の預貯金を相続人〇〇が解約し、その払戻金から〇〇円を相続人〇〇に金○○万円を分配する」といった具体的な分配方法を記載することも可能です。
- 遺産分割協議が成立した旨と日付
相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立したことを明確に記載します。あわせて、日付を記載します。
- 相続人全員の署名と実印での押印
協議書が有効であるために必要です。署名は自筆以外に記名・代筆でも可能です。
■口座ごとに分割する場合の注意点
一般的に金額などでわけることが多いですが、預貯金口座の遺産分割協議書を作る際には、金融機関から発行される残高証明書や通帳などで、口座情報を正確に確認し記載します。口座番号などが一文字でも異なると、金融機関での手続きができない可能性があるため注意が必要です。複数の口座がある場合は、それぞれを明確に区別して記載しましょう。
遺産分割協議書の作成も
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
後から相続財産が見つかった時の対処法
遺産分割協議後に新たな相続財産が見つかった場合、原則として、その見つかった財産についてのみ改めて遺産分割協議を行う必要があります。(遺産分割全体をやり直す必要はありません)
新たな財産についての遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印が必要です。
将来のトラブルを避けるためには、最初の遺産分割協議書に「本遺産分割協議書に記載のない相続財産が後日発見された場合は、別途協議のうえ分割する」といった条項を加えておくことが一般的です。これにより、後から見つかった財産についても、スムーズに協議を進めることができます。
合わせて読みたい:遺産分割協議書に記載がない財産が出てきたら?後日判明した遺産の扱い・手続を行政書士が解説!
遺産分割協議書の作成は行政書士へのご相談がおすすめです
本記事では不動産と預貯金に関する遺産分割協議書について、作り方と注意点を中心に行政書士が詳しく解説しました。不動産と預貯金は遺産分割協議を別々に進め、それぞれ遺産分割協議書を作成することが可能です。
一部の財産に関する手続きを先行させ、スピードアップを図れるメリットがあります。
しかし、複数の協議書を作成する手間や、記載の重複・漏れには注意が必要です。特に記載内容に不備があると、後々の手続きで問題が生じる可能性があるためご注意ください。
遺産分割協議書の作成時は専門的な知識が必要です。ご自身での作成に不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめです。横浜市の長岡行政書士事務所でもご相談に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。