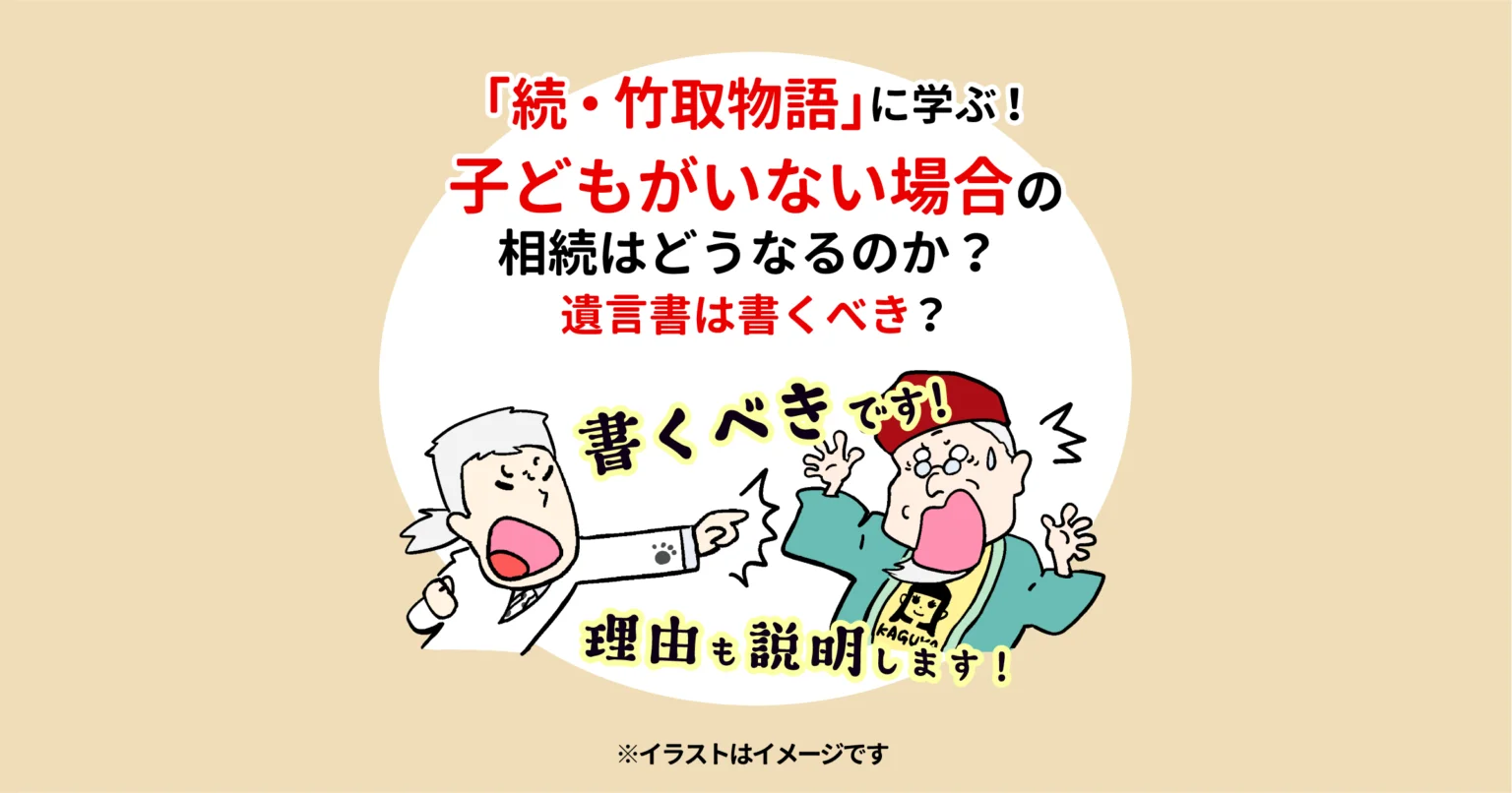相続というと親から子へ財産を継がせるというイメージがあるかもしれませんが、子どもがいない場合も相続は発生します。
しかし具体的にどのような手続が必要となり、誰が財産を引き継ぐことになるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、子どもがいない場合の相続がどうなるのか、竹取物語風に分かりやすく解説します。子どもがいない相続で必要となる手続について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
むかしむかし、あるところに竹取の翁ありけり。
翁がふと竹藪で見つけた光る竹。そこから出てきたのは、「絶対、配信したらバズりまくるわ、このコ」と思えるほどのかわいい女の子、かぐや姫でした。
「これはきっと子供がいない我が家に、神様が授けてくれた子に違いない」
翁と嫗が愛情込めて、「目の中に本当に入れたらやっぱり痛いけど、痛いとは思いたくない我が娘」として育てたかぐや姫でしたが、やがて大きくなると結婚申し込みがわんさかと来るようになりました。
しかし、SNSブロックに等しいほどの無理難題を、結婚条件に出された公家の婿候補たちは、けちょんけちょんにあしらわれて全滅。
やがてかぐや姫は、イー●ン・マ●ク似の月からの使者とともに、月へと返っていってしまいました。
それから数年がたち、翁は体調を崩してしまいました。
そして、かつての公家からぶんどった…じゃなくて、かぐや姫へと貢がれた金銀財宝(私財)の相続について悩んでいたのでした。
翁は、花咲かじいさんが飼っていた犬であり、人間の姿になって新人行政書士になったばかりのシロに相談することにしました。
子どもがいない場合の相続人
翁「シロや、どうもかぐや姫からは、その後音沙汰がなくてな。仕方がないので、もう娘はおらんものだと思いたいのだよ」
シロ「お気持ちわかります。寂しいですよね。でも実際、自分の娘といっても、そもそも役所に届け出てなかったんでしょ?」
翁「まあ、そりゃ昔話的に役所とか出てきたらややこしいからのう」
シロ「ですから言うなれば、かぐやさんは赤の他人のエイリアンですよね」
翁「いきなり昔話の世界観をぶちこわして都市伝説に走ったな…」
シロ「何が言いたいかというとね。翁には子供がいない。その前提で相続を考えないといけないってわけです」
翁「まあのう…。それはわしも薄々わかっておったんじゃ。でも子供がいないわけじゃから、相続もへったくれもないんじゃないかえ?」
シロ「いえいえ、子どもがいない場合でも、相続は発生しますよ。まず、配偶者は常に相続人です。それ以外の法定相続人は、次のように順位が決まっていますからね。
- 第1順位:子(直系卑属)
- 第2順位:父母などの直系尊属(第1順位がいない場合に限る)
- 第3順位:兄弟姉妹(第1・2順位がいない場合に限る)
シロ「遺言書が残されていない場合は、その法定相続人全員で、法律に則った遺産分割が行われるわけです。子どもがいないとなると、配偶者・父母・兄弟姉妹(甥姪)が相続人になるということですね。
ちなみに遺言書がある場合は、遺言書に沿って相続手続を進めることになります。」
子どもがいない場合は遺産分割協議が大変になりやすい
翁「ふむ、つまり、うちのばあさんと、松取の翁という兄、そして梅取の翁という弟が相続人になるかのう」
シロ「松竹梅とはめでたい兄弟ですね。ということは、おじいさんには妻・兄・弟、合計相続人が3人いるわけです。
もし遺言書があれば、その遺言書に沿って相続手続を進めればいいですが、、、
遺言書を書いてないと、こりゃ血で血を洗ういくさになりますね」
翁「な、なんじゃと!」
翁「それなら普通に話し合ってもらえれば…」
シロ「甘い。シロップをかけすぎたかき氷よりも甘い! 話し合いの内容について相続人全員が合意することが必要で、そのことを証明するものとして相続人全員が署名して実印を押印する遺産分割協議書を作成しなくちゃいけないんです。
特にかぐやさんがらみの遺産は大きい。遺産が相続されることに残されたおばあさんが納得していれば問題はありませんが、遺産分割協議となった場合に紛糾しない保証がどこにあります?」
翁「ない、とは言い切れん…松取の翁も梅取の翁もがめついからのう…ばあさんがうまいこと言いくるめられないか心配じゃ」
シロ「どんな兄弟だよ…。でも、それなら間違いなく遺言書を書くべきですね」
合わせて読みたい:遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
子どもがいない夫婦の相続を遺言書に沿って進める方法
シロ「とりあえずは、配偶者であるおばあさんにすべての財産を相続してもらうための遺言書を用意したほうが安心ですね」
翁「うむ、それこそわしの真意じゃからのう」
シロ「全財産を配偶者に残す場合、こんなふうに記載するのがいいでしょう」
《全財産を相続させたい場合の記載例》
遺言者は、遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、妻〇〇〇(生年月日)に相続させる。
シロ「このような旨の遺言書があれば、遺産分割協議をしなくても、おじいさんの全財産について相続手続を進めることが可能ですよ」
翁「それは便利じゃのぉ」
シロ「ちなみに全財産ではなく、特定の財産を配偶者に相続させる遺言書というのもあります。」
翁「特定のとはどういうことじゃろう?」
シロ「例えば不動産だけとか、『この財産を除いた全部』とかですね。その場合の書き方はこんな感じですね」
《特定の財産を相続させたい場合の記載例》
・遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻〇〇〇(生年月日)に相続させる。
・遺言者は、遺言者の有する預貯金について、弟〇〇〇(生年月日)に相続させる。
シロ「この場合も、遺産分割協議をせず、それぞれ相続手続を進めることが可能です。
子どもがいない相続と遺留分の関係
シロ「ちなみに、遺留分は知ってますか?」
翁「なんじゃろう?」
シロ「ある一定の法定相続人が遺言書によって遺産を取得できない場合、遺産について受け取ることのできる最低限の割合のことです。法律で認められている権利でしてね。要するに、『遺言書には自分への相続内容が書かれてないけど、自分も受け取る権利があるから、その権利分だけの財産をおくれ』というものです」
関連記事:遺留分とは?割合や法定相続分との違いを行政書士がわかりやすく解説!
翁「ありゃ。そんなのがあるんか? あいつら、言いそうじゃのう」
シロ「でも遺留分が認められるのは子どもなどの直系卑属と、両親などの直系尊属になりますから、兄弟姉妹は含まれないんですよ」
子どもがいない相続手続は専門家に相談すると安心
それではここまで紹介した内容をおさらいしましょう。
まず、子どもがいない相続の場合、遺言書の有無を確認します。
遺言書があれば、その内容を実現すべく手続を進めます。
遺言書がない場合は、法定相続人で遺産分割協議をし、財産の分け方を決めます。子がいない場合は、配偶者+配偶者の両親、配偶者+配偶者の兄弟姉妹などで協議することになるため、落ち着いて話し合える環境を用意してみてください。
また、子がいないとなると、高齢者のみで手続をしなければならないこともあります。たとえば今回の物語でいえば、相続人はおばあさん、松取の翁、梅取の翁の3人ですが、全員が高齢者であるため、自分たちだけで相続手続を進めることは大変でしょう。
このような場合は、行政書士などの専門家に相談してみてください。遺産分割協議の作成はもちろん、銀行口座の相続なども任せるため安心です。
横浜市の長岡行政書士事務所でも相続手続をサポートしているため、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。