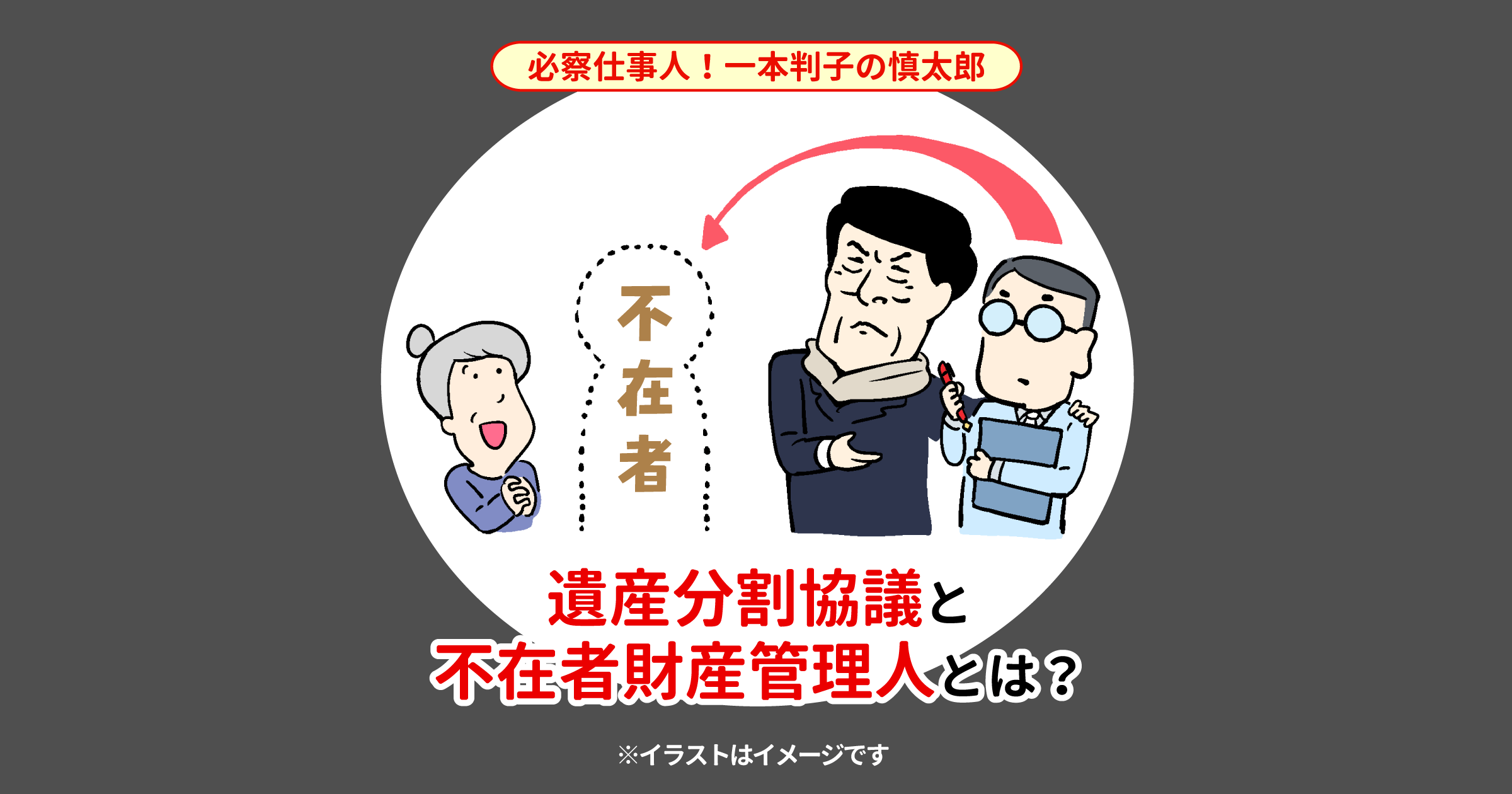被相続人が遺言を書いていなかった場合は、法律で決められた相続人が全員集まって遺産分割協議を行い、遺産の分け方で合意しないといけません。
でも、相続人の中で連絡が取れない人がいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
そんなときは「不在者財産管理人」という制度を使うことになります。
今回は遺産分割協議に不在者財産管理人はどう関係するのか、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が解説します。
難しい法律の話となりますが、分かりやすくするために物語風に見ていきましょう!
この物語は、判子ひとつで相談者を安心させるべく行政書士業務に邁進する、とある人物が夢の中で見た相続問題解決物語です。時代劇の某名ドラマとは、一切関係がありません。
・・・・・
一かけ二かけ三かけて、”士”かけて察して日が暮れて。
夕陽の燃ゆる横濱で、紅い煉瓦に腰下ろし、遥か彼方を眺むれば。
この世はせつねえ事ばかり…。
片手に六法、ペンを持ち。
相続問題お察しし、判子ひと押し、任せてくんねえ。
あたしは必察仕事人、一本判子の慎太郎と申します。
慎太郎「それで今日は、何処のどなたを救ってくれと仰るんで」
依頼人「慎さん、行方不明の相続人がいるんだよ…どうしたらいい?」
慎太郎「ええ、この慎太郎に任せてください」
遺産分割協議は相続人全員がいないと進められない
被相続人が亡くなると、財産はいったん相続人たちの共同所有になります。
ここから話し合いで財産を分けていくことになりますが、遺産分割協議に参加しない相続人がいると大問題。
その人の財産まで勝手に他の相続人で分けることができないからです。
つまり行方不明の相続人がいると、遺産分割協議をまとめられず、相続手続を進められないのです。
相続人が行方不明の場合は不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できる
依頼人「慎さん、協議が進められないなんて困るよねえ…」
慎太郎「そういうときのためにね、不在者財産管理人という制度があるんですよ」
依頼人「なんだい、その不在者財産管理人ってのは?」
慎太郎「ざっくりと言うとね、不在の間に財産を守る人ですよ。財産を保存し、あるいは財産の性質を変えない範囲で利用・改良するんです。あ、投資などで財産を増やすようなことはできませんからね」
依頼人「へえ、そりゃ頼もしいね」
関連記事:不在者財産管理人とは?行方不明の相続人がいる場合の手続き方法を行政書士が解説!
慎太郎「ええ。どれだけの財産があるのかを明確にするために財産目録を作成し、その後は家庭裁判所の求めに応じて定期的に財産の状況を報告する、きちっとした役割です」
依頼人「不在者財産管理人は遺産分割協議に参加したりするのかい?」
慎太郎「遺産分割協議への参加は本来の不在者財産管理人の業務範囲ではないんです。もし参加するなら、家庭裁判所に申し立てて権限外行為許可を得なくちゃいけません」
不在者財産管理人は不在者の不利益となる遺産分割協議には合意(参加)できない
不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、遺産分割協議に参加できます。
しかし不在者財産管理人はあくまでも「不在者の財産に関する保存行為、目的の物や権利の性質を変えない範囲における利用や改良行為」をする人です。
つまり不在者財産管理人は、不在者の不利益となる遺産分割協議には合意できないということです。
そのため、遺産分割協議の案が、不在者が法定相続分を下回るような財産しか取得できないような内容の場合、家庭裁判所から原則として許可してもらえません。
したがって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するということは、不在者が法定相続分以上の相続分を取得する内容で遺産分割協議をまとめることになります。
そして不在者財産管理人は行方不明者(不在者)が現れるまで、その取得した遺産を預かることになります。
不在者財産管理人の選任方法
依頼人「そもそも、不在者財産管理人はどうやって選ぶもんなんだい?」
慎太郎「不在者の利害関係人が家庭裁判所に申し立てて選んでもらうんですよ」
依頼人「立候補で誰でもなれるもんじゃないんだね」
慎太郎「そうですね。で、申し立ての為の必要書類はこのあたりですね」
- 申立書
- 不在者の戸籍謄本と戸籍附票
- 不在者財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 不在であることを証明する資料
- 不在者の財産に関する資料
- 戸籍謄本等の不在者と申立人の関係を示す資料
依頼人「ひとつ、不在であることを証明するためにはどうしたらいいんだい?」
慎太郎「警察が発行する行方不明者届受理証明書や、宛先人不明で返送された郵便物を使えばいいんですよ」
依頼人「なるほど、だいぶわかってきて、気が楽になってきたよ。他になにか注意点はあるかい?」
不在者財産管理人に関する注意点やデメリット
不在者財産管理人はあくまで不在者の財産を守るために行動し、申し立てをした他の相続人の利益になることをする代理人ではありません。その点を誤解しないようにしておきましょう。
慎太郎「注意点というより、知っておくべきことという点では2つあります。選任までに時間がかかることと、報酬が発生することです」
不在者財産管理人を選任するまでに時間がかかる
依頼者「不在者財産管理人を選任するまでの時間ってのはどのくらい?」
慎太郎「一概には言えませんが、数か月は見込んでおいたほうがいいですよ。それから大事なのは相続の期限にかからないよう認識しておくことですね。相続を知った日から10カ月以内に相続税の申告・納付を終わらせなくちゃいけませんから」
合わせて読みたい:遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!
依頼者「相続税か。期限を守れないと延滞税が課されたり、税金の軽減制度が使えなくなるのは聞いたことがあるよ。」
不在者財産管理人には報酬が支払われる
依頼者「ちなみに、不在者財産管理人に支払う報酬のほうは…かなり高いのかい?」
慎太郎「基本的に、報酬は不在者の財産から支払われるんです。家庭裁判所の判断が入るので法外な額にはなりません。でも不在者が帰ってきたとき、「減ってるじゃないか」といぶかしむことは実際にあったりしますからね」
行方不明の相続人がいる相続手続も行政書士に相談
依頼者「そうかあ…。手続きも煩雑だし、自分一人でやれるか自信がないよ」
慎太郎「そういうときのために、この一本判子の慎太郎、一番お勧めしたいのが…(チャラリーン、チャララチャラリラ、ラリラリラ~♪)」
依頼人「おおう、どこかで聞いたことがある時代劇のBGMが流れてきた…そして、慎太郎が意味ありげな決めポーズをとっている…! 見せられないのが残念だ!」
慎太郎「…専門家への依頼です!」
依頼人「いよっ、慎太郎! 千両役者!」
行方不明の相続人がいる場合は不在者財産管理人を申し立てることにより遺産分割協議を進めることができますが、様々な判断や手続きをしなければいけません。
また、行方不明者がいる場合の相続手続では、不在者財産管理人を申し立てるのではなく「失踪宣告」という方法も取ることもあります。
失踪宣告は行方不明者を戸籍上死亡したことにする制度であるため、行方不明者が遺産分割協議に参加する必要はなくなり、遺産分割の自由度が増すことは事実です。(関連記事:行方不明の相続人がいる場合はどうする?失踪宣告による相続手続きを行政書士が解説!)
ただでさえ相続手続は負担が多いのに、不在者がいる場合の対応は複雑で、困っている方もいるでしょう。
横浜市の長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、相談者様には印鑑一つで済む負担の少ない相続を目指しています。
もし相続人の中に行方不明者がおり不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。