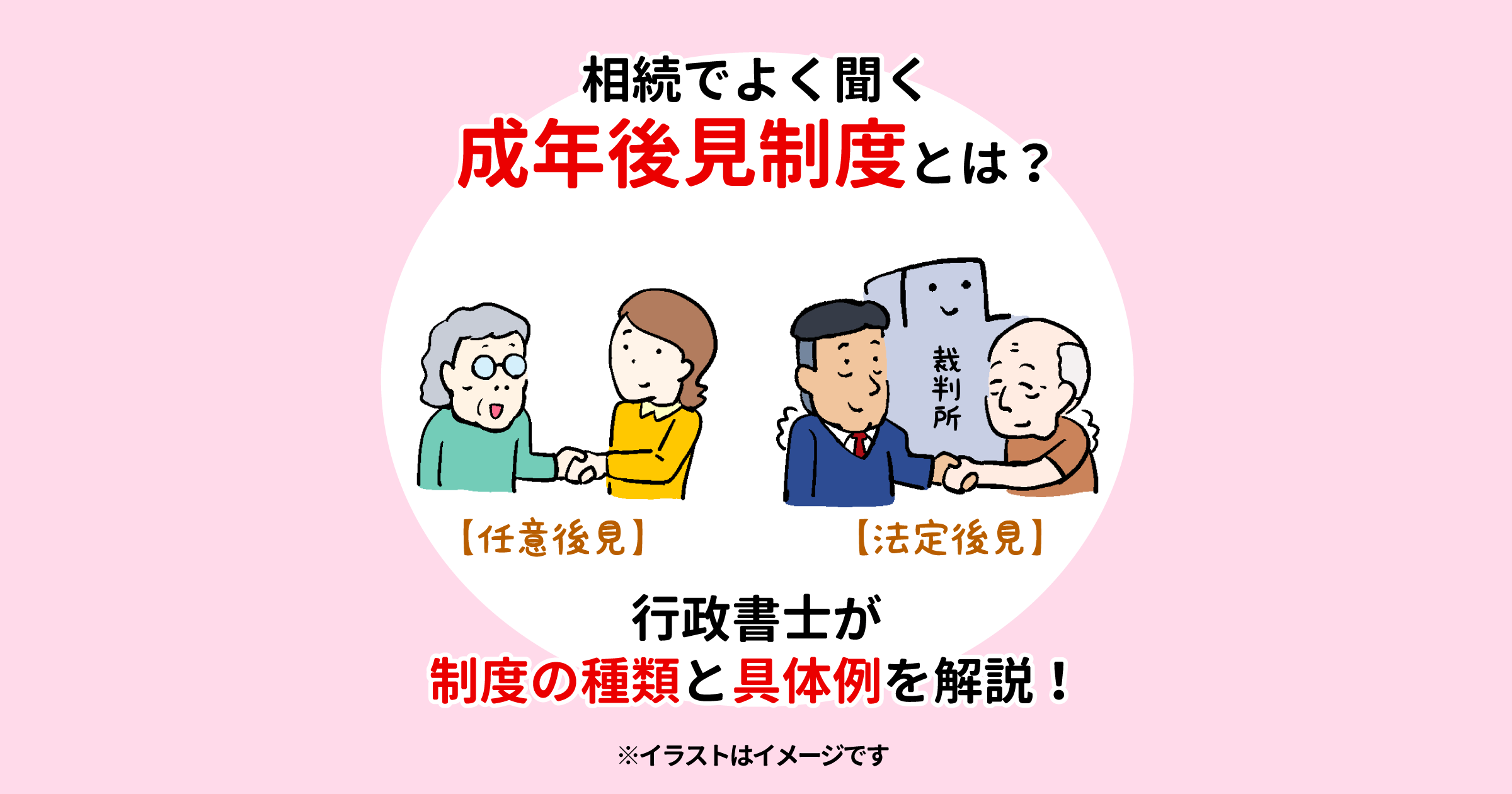「成年後見って聞いたけれど、どういう意味なの?」
「相続人の中に被成年後見人がいるのだけど、相続手続は進められる?」
皆様は「成年後見制度」という言葉を聞いた事がありますか?これは判断能力が低下した方をサポートするための制度です。
では、もし相続人の中に成年後見人からサポートを受けている人がいる場合、相続手続は進められるのでしょうか。
今回は相続人に成年後見人がいる場合の相続手続について、行政書士が解説します。
成年後見制度とは
もし判断能力が低下した方を、誰もサポートしなかったらどうなってしまうのでしょう。
まず真っ先に思い浮かぶのは、騙されて契約をしてしまうんじゃないか、ということです。せっかく家族がその方の今後の為に生活を維持するための財産を用意していても、詐欺師などに騙されて不利な契約をしてしまうかもしれません。
消費者を守るために契約を解除できるクーリングオフという制度もありますが、条件や期限が決められているので詐欺師はその裏をかいて解除できないように仕向けてきます。いかに家族と言えども四六時中騙されないように目を光らせているのは不可能ですから、何とか対策したいものです。
また、騙されなかったとしても自分で財産を管理したり、体の状態にあわせた介護契約を結ぶのは判断能力が低下した方にとっては困難を伴う作業ですから、これにも対策しておきたいですね。
このような判断能力が低下した方を、文字通り後ろから見守ってくれるのが成年後見制度になります。
具体的には本人に代わって法律的な判断や契約といった作業をし、本人に不利益にならないように手配をしてくれる制度です。
また、仮に本人が契約をしてしまっても、そのような契約は原則取り消すことができて安心できます。(ただし、日用品の購入等は取り消すことができません)
先ほどの例でいくと、認知症の方が騙されて土地を格安で売る契約をしてしまっても、この方が成年後見制度で守られていれば契約は無効になり土地を手放す必要はありません。
そして、入院や老人ホームへの入居といった手続きも本人に代わってやってもらえるので、よりスムーズに事が運びます。
このように、成年後見制度は高齢の方や認知症、知的障害、総合失調症の方の財産や生活を守ることに寄与しています。
なお、この成年後見制度は法律行為に限定されており、病院への付き添いや食事の世話、介護などは含まれません。
じゃ、結局守ってもらえないのでは・・・と不安にならないでください。
自分では付き添いや介護はしませんが、そのようなことをしてくれるヘルパーさんを雇う契約(=法律行為)を本人に代わって結んでくれるのが成年後見制度ということです。
結果として本人の生活はきちんと守ることができます。
あわせて読みたい>>>成年被後見人でも遺言書の作成は可能か|万が一に備える遺言書と任意後見制度の有効活用
法定後見制度にはいくつか種類がある
それでは、成年後見制度を少し細かく見ていきましょう。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つあり、そして法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
つまり全部で「後見」「保佐」「補助」+「任意後見」の4種類が存在することになります。
そして「後見」「保佐」「補助」の違いは本人の判断能力低下の度合いによって変わってきます。
それぞれの後見制度について、概要を解説します。
法定後見
自分がやったことがどういう結果を招くかを認識する能力を事理弁識能力といいます。
例えば、道路に飛び出すと危険だという事がわかるかどうか、物を買ったらお金を払わないといけないという事がわかるかどうかといったことです。
この事理弁識能力が欠けていると、契約を結んだり自分の銀行口座を管理するといった行為どころか、普通の日常生活を送ることにも困難を伴ないかねません。
よって一番手厚いサポートとして、「後見」の対象となります。
具体的には、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などからの申し立てにより、家庭裁判所が「後見人」というサポート役を選出します。
この後見人には本人に代わって法律行為を行う代理権や、本人に代わって取り消しができる取消権があります。
本人が法律行為ができなくても代わりにこの後見人がやってあげたり、本人が騙されて契約してしまっても後見人が取り消すことができるので、本人の生活や利益を守ることができます。
後見人は法律で定められている欠格事由に該当しなければ誰でもなる事ができますが、本人を守るという大切な役割があるので実際は法律の専門家や社会福祉士といった職種の方が就くことがほとんどです。
保佐
後見制度の「保佐」とは、日常の事は自分でできるものの、自分で判断して契約などといった法律行為をするのは危ういというレベルです。
中高生の子供をイメージしてください。
自分で買い物もできるし電車にも乗れますが、契約を任せるのは難しいでしょう。
成人が判断能力が低下し、上記のような状態になった場合には、「保佐」制度を利用します。たとえば”うつ病”で入院していた人が退院し日常生活は送れるようになったが、家族が都合により側にいてあげられないので不安が残るという場合なのです。
通常の生活は本人に任せるが、重要な事は保佐人が同意しないといけない、という事です。
この「保佐」も、「後見」と同じように法で決められた利害関係人からの申し立てにより、家庭裁判所がサポートする人間(=保佐人)を選びます。
しかし「保佐」と「後見」には違いもあります。一番の違いは、後見人には民法により「代理権」が必ず付与されるのに対し、保佐人には家庭裁判所の審判により特定の行為に「代理権」が付与されることです。
また、後見人と異なり、保佐人に付与されるのが「同意権」です。保佐人の同意なしに特定の行為を行うと、保佐人はその行為を取り消すことができます。
後見人に同意権の付与が無いのは、仮に後見人が被後見人に同意をしたとしても、事理弁識能力を欠く常況では被後見人が同意どうりに動くか分からないためです。
保佐人の同意が必要となる行為も民法の13条1項に明記されています。ざっくりとどのような行為が特定の同意権の範囲に該当するのか見てみましょう。
民法13条 保佐人の同意を要する行為等(抜粋)
- 元本を領収し、又は利用すること
- 借財又は保証をすること
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
- 制限行為能力者の法定代理人としてすること
1に関しては利息を受け取ることは保佐を必要とする人(=被保佐人)でも保佐人の同意を必要としません。元本に比べて利息は軽微であることが多く、そのような場合は被保佐人が単独でも行えるということがわかります。
ただ、その他2や3のような重要な財産を処分したり、保証人になる事は保佐人の同意が必要とされています。このような行為は本人への経済上のインパクトが大きく、保佐人のしっかりとした判断が必要だということです。
4は例えば未成年の子(=制限行為能力者)の親が被保佐人となった場合は、親としての法律行為に制限がかかると理解しておいてください。
補助
3つある法定後見の最後の「補助」は、日常生活は自分で送れるが契約させたりするのは心もとない、というレベルです。
具体的な保佐との違いは、保佐人には民法13条1項のリストの行為に対し同意権と取消権が与えられていますが、補助人には13条1項のリストのうち家庭裁判所から必要と認められた行為にのみ同意権と取消権が与えらえるという点です。
保佐よりサポートは必要としていないが、いくつかの行為に対してはサポートが必要だと認められる際などに補助が利用されます。
任意後見
前述3つの法定後見は、家庭裁判所がサポートする人を選ぶ制度です。
一方、「任意後見」は、誰にサポートしてもらうのか、判断能力が低下する前に自分で選んでおく制度です。
法定後見は判断能力が低下してから家庭裁判所が手配をするので、ある意味受け身だとも言えます。
対して自分がまだ判断能力があるうちに取り決めておく任意後見は、積極的に自分の老後をデザインしようとする契約だと言えるでしょう。
法定後見との大きな違いは2点あります。
- 自分で後見人を選ぶことができる
- 契約内容を自分で設計できる
法定後見の三種はいずれも家庭裁判所が家族や四親等以内の親族といった近い人からの申し立てにより後見人・保佐人・補助人を選びますが、本人と全く面識のない方が選ばれる可能性があります。
家庭裁判所という公の機関が選んでくれますが、人によっては見ず知らずの人に管理を任せる心理的な抵抗を感じるかもしれません。
他方、任意後見では自分で後見人を選んでおくことができるので、より安心感や納得感を得やすくなります。
また、法定後見の内容は法で定められており一番軽度の補助でも該当する行為を家庭裁判所の判断に委ねる必要がありますが、任意後見ではどの行為にどのような権限を与えておくかの設計を自分で決めることができます。
自分の財産や行為に制約を設けるのは最後まで自分で決めたい、と考える方には任意後見が合っていると言えるでしょう。
相続人に成年後見人がついている場合はどうなる?
それでは、相続人に成年後見人がついている場合はどう相続手続を進めればいいのでしょうか。
まず、故人が遺言書を残している場合は、その遺言内容に沿って相続手続を進めればいいため、相続人に成年後見人がついているからといって支障はありません。
一方、遺言書がない場合、もしくは遺言書で分け方が指定されていない財産がある場合は、相続人で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし相続人の中に認知症や脳死状態の方がいると、法的に有効な合意を行うことができません。
よって家庭裁判所に申し立てて後見人をつけてもらい、この後見人に「本人の代理」として遺産分割協議に参加してもらうことになります。
仮に本人が脳死状態にあっても後見人が本人の利益を代弁してくれますし、また他の相続人にとっても全員の参加と合意が求められる遺産分割協議を進めることが可能となります。
あわせて読みたい>>>相続人が認知症のとき遺産分割協議はどうする?対策と手続きを行政書士が解説!
相続人に保佐人がついている場合はどうなる?
さて、相続人に保佐人がついている場合、相続手続はどうなるでしょうか。
この場合、取りうる方法は次の2パターンです。
- 保佐人に代理権を付与して代わりに遺産分割協議をしてもらう
- 本人が遺産分割協議に参加し、その内容を保佐人に同意してもらう
後見人と異なり、保佐人は本人のために遺産分割を行う権限を当然に有しているわけではありません。なぜなら本人の判断能力は不十分ですが、それを常に欠いているとまではいえないためです。
しかし遺産分割協議は大きな財産が動くものであるため、本人が単独で遺産分割協議に臨むことはできません。
そのため、保佐人に代理権を付与して代わりに遺産分割協議をしてもらうか、本人が遺産分割協議に参加することを保佐人に同意してもらう必要があるのです。
保佐人がついていても、相続人本人が遺産分割協議に参加することは可能ですが、保佐人の同意が必要であるということを覚えておきましょう。
相続人に補助人がついている場合はどうなる?
相続人に補助人がついている場合、相続手続はどうなるでしょうか。取りうるパターンは次の3パターンです。
- 補助人に代理権を付与して代わりに遺産分割協議をしてもらう
- 本人が遺産分割協議に参加し、その内容を補助人に同意してもらう
- 補助人の関与なしに本人が単独で遺産分割協議に参加する
被補助人には、一定の判断能力が残っています。そのため、家庭裁判所の審判の内容によっては、補助人の関与なしに本人が単独で遺産分割協議に参加することも可能なのです。
しかし補助人に「被補助人が遺産分割を行うことに対する同意権」が家庭裁判所から付与されている場合には、補助人の同意を得る必要があります。
後見人・保佐人・補助人が関わる相続手続も行政書士に相談できる
日本人の5人に1人が認知症になると言われています。そのため相続人の中に、被後見人・被保佐人・被補助人がいることもあるでしょう。
この場合、遺産分割協議に後見人・保佐人・補助人が関わることもあります。反対にいうと、後見人・保佐人・補助人に遺産分割協議に参加してもらうよう依頼しなければならないこともあるのです。
もし相続が発生し、後見人・保佐人・補助人の関与が必要なのかどうか分からない場合には、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。相続手続をお任せいただければ、しっかりと関係各所へ連絡し、スムーズに相続手続を進めてまいります。