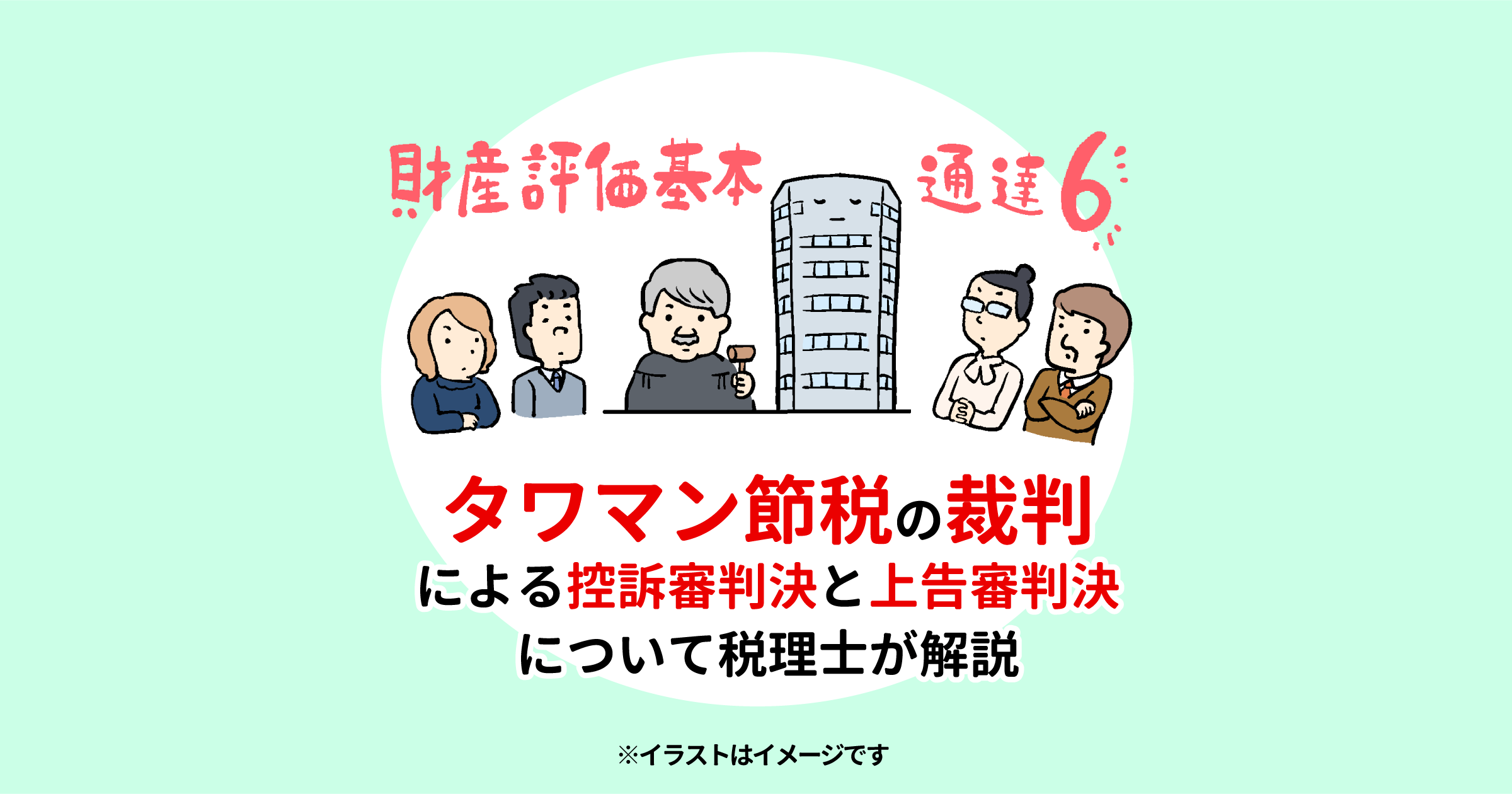相続税の算出のために財産を評価するときは、「財産評価基本通達」に則って評価することが多いです。ただし相続手続きの実務においては、財産評価基本通達による評価(原則)と財産評価基本通達6による評価(例外)のいずれで評価するか、判断しなければなりません。
関連記事:財産評価基本通達とは?「相続税法の時価」との関係や存在意義を税理士が解説
関連記事:財産評価基本通達6で争われた裁判例を税理士が解説【相続税の豆知識】
上記の記事では「財産評価基本通達6項」が適用された裁判例を検証しました。ご覧いただければ、財産評価基本通達6項が適用される局面についてイメージができるでしょう。
さて、「財産評価基本通達6項」に関連して、最高裁まで争われたタワマン節税にまつわる有名な裁判があることをご存知でしょうか。後に「タワマン節税」にメスが入った要因の一つでもある重要な裁判です。
この記事ではタワマン節税の裁判による控訴審判決と、そのあと上告されていますので上告審判決まで詳しく解説させていただきます。(第一審判決については「タワマン節税の裁判による第一審判決について税理士が解説」をご覧ください)
「タワマン節税」裁判の経緯・事案概要
前回の記事ではタワマン節税の裁判で第一審判決について詳しく解説させていただきました。
裁判の概要について、改めて紹介します。
概要
納税者が相続により取得した土地、建物(以下、不動産という。)を評価通達により評価して申告したところ、 課税当局がこの不動産について、評価通達により評価することが著しく不適当と認められるとして、鑑定評価額に基づいて更正処分を行ったことに対し、その取消しを求めた事件
争点
納税者らは、相続税申告で評価通達による評価方法により各不動産を評価していますが、課税当局は評価通達による評価によると著しく不適当と認められる特別の事情があるものとして否認しています。
つまり本件の争点は相続開始時における各不動産の時価です。
そして”評価通達による評価方法”によらない評価が許されるための「特別の事情」の存否が争われています。
関連記事:タワマン節税の裁判による第一審判決について税理士が解説
第一審判決では課税当局の主張である「評価通達6により各不動産は鑑定評価額で評価することが適正である」と裁判所は判断していて、納税者は控訴しています。
「タワマン節税」控訴審判決
まずは控訴審判決について、納税者の主張と課税当局の主張をそれぞれ確認し、最後に裁判所の判断をみていきます。
納税者の主張
納税者の主張は次のとおりです。
租税法律主義について
相続税法に規定する時価として、財産を評価通達によらずに評価する要件である「特別の事情」については、課税当局のみならず納税者においても、その要件にあたる”判断基準”が示されなければ、時価評価の予測可能性と法的安定性を害し、租税法律主義に違反すると主張しています。
特別の事情とは「評価通達による評価額に特殊事情がある財産が持つ固有の事情」をさし、時価評価に影響しない「相続開始前後の事情」や「租税回避又は租税負担の減少の意図」などは、財産を評価通達によらずに評価する要件である「特別の事情」に当たらないとしています。
また、相続税法は「租税回避を防止するための租税回避措置の否認」を個別具体的に規定していることからすると、このような個別の規定が存在しない以上、評価通達6を租税回避措置の否認のために用いることは租税法律主義に反するとしています。
著しい乖離差について
各不動産の鑑定評価額と通達評価額の3~4倍の開差というのは、特に異常なものではなく、各不動産の周辺の類似する物件についても同じく普遍的に存在することからすると、各不動産についての特別な事情とはいえないから、評価通達によらずに評価する要件である「特別の事情」に当たらないとしています。
また、相続税の財産評価は、「土地については路線価」「建物については固定資産評価基準による固定資産評価額」をそれぞれ採用することが合理的であると評価通達が定めているのであって、鑑定評価額とは評価における根本的な考え方が異なるので、通達評価額と鑑定評価額を比較して開差が大きいとすること自体が不合理であるとしています。
相続開始前後の一連の取引について
相続開始前後の各不動産に係る一連の取引は、次世代への事業承継のための経営効率の改善を目的としたものであって、租税回避を目的としたものではなかったとしています。
課税当局の主張
評価通達6の判断基準
そもそも評価通達は相続税の課税財産の全てについて、また稀にしか起こらない事例についてまで、具体的な評価方法や評価額を示すことなく、評価通達5及び6によって評価することとしています。
評価通達6は、適正な時価評価を行うための言わば「評価通達の他の各規定の補完的な役割」を担うものであるから、このような想定していない例外的な場面でのみ適用される評価通達6について、普遍化できる評価基準を具体的に示すことは著しく困難であるとしています。
評価通達によらない財産評価は、「評価通達による評価方法を画一的に適用する」という形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の公平を著しく害することが明らかな場合に認められるものであって、その財産について潜在的な価格変動要因がある場合に限られないとしています。
特別の事情の判断基準
課税当局は「税負担の軽減を結果としてもたらす行為を阻止するための根拠」として評価通達6を適用しているのではなく、「租税回避が行われたとして、それが本来相続税法の予定するところではなく、法の趣旨目的に反するものであって、実質的な租税負担の公平を著しく害する」という場合には、それが特別の事情に該当するとしているにすぎないとしています。
各不動産については「評価通達によらずに評価することが相当」と認められるような特別の事情が認められることから、他の客観的な交換価値と認められる鑑定評価額をその時価として各更正処分がされたのであって、各更正処分が相続税法の規定とその解釈に基づいて行われた適法なものであることは明らかであるとしています。
裁判所の判断
それでは裁判所の判断について見ていきましょう。
租税法律主義に違反するか否か
「相続によって取得した財産の価額は、その財産の取得時における時価による」ということは、相続税法22条によって定められています。
評価通達でも、評価通達1(2)において、財産の価額は、時価によるものされています。時価とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます。
その価額は「評価通達による評価額」とした上で、評価通達6において「評価通達により評価することが著しく不適当と認められる財産については、評価通達により評価されない場合がある」ことを定めています。
そうすると相続により取得した財産について、評価通達による評価方法以外の方法によって評価した価額をその財産の時価とすることについて、それがどのような場合であるかについて評価通達によってあらかじめ示されていなかったからといって、租税法律主義に違反するものとは解されないとしています。
よって、納税者らの主張を採用することはできないとしています。
時価評価の予測可能性について
このタワマン節税の裁判では、次の不動産が問題となっています。
このような事実は、納税者らにおいて「各通達評価額が時価と乖離していることを想定することは可能であった」というべきであり、各更正処分が時価評価の予測可能性を侵害しているとはいい難いとしています。
著しい乖離差による影響について
各不動産に係る鑑定評価額と通達評価額との3~4倍の開差については大きなものと認められるし、それによって生ずる税額の差や、被相続人や納税者らがあえて「各不動産の購入」と「被相続人の相続開始時の残債務に係る借入れが、近い将来発生することが予想される被相続人の相続において納税者らの相続税の負担を減じ又は免れること」を知っていたとしています。
かつ、それを期待して、各不動産の購入と借入れを企画して実行し、その結果、借入れ及び不動産の購入がなければ、相続に係る課税価格は6億円を超えます。
通達評価額を前提とする各申告による課税価格は2,826万1,000円にとどまり、基礎控除により本件相続に係る相続税は課税されないことからすると、各不動産については、評価通達による評価方法によっては適正な時価を算定することができず、評価通達による評価額を時価とすることは、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであると認められるとしています。
よって、納税者らの主張を採用することはできないとしています。
相続開始前後の一連の取引について
納税者らは、「相続開始前後の各不動産に係る取引は、事業承継のための経営効率の改善を目的としたものであって、租税回避を目的としたものではなかった」と主張しています。
しかし、課税当局は、通達評価額と鑑定評価額との間の著しい乖離から、各不動産を評価通達により評価することが著しく不適当であるなどとして、各不動産を評価通達によって評価しないものとしたのであって、単に税負担の軽減を結果としてもたらす行為を阻止するために評価通達6を適用したものとは認められないから、納税者らのこの点についての主張は採用することはできないとしています。
上告審判決について
第一審判決に続いて「納税者らの主張は採用できないと」され、控訴審判決で納税者は敗訴しました。
そして納税者らは上告し、そのうえで上告し受理されましたので、上告審判決までいきました。
裁判所の判断内容を見ていきたいと思います。
相続税法22条
相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは客観的な交換価値をいうものと解される。
そして、評価通達は「時価の評価方法を定めたもの」であるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。
そうすると、「相続税の課税価格に算入される財産の価額」は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。
そうであるところ、本件各更正処分に係る課税価格に算入された各鑑定評価額は、各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるというのであるから、これが各通達評価額を上回るからといって、相続税法22条に違反するものということはできないとしています。
平等原則について
租税法上の平等原則は、租税法の適用に関して、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。
そして、評価通達は相続財産の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税当局がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税当局が「特定の者の相続財産の価額についてのみ」評価通達により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえその価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。
もっとも、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、その財産の価額を評価通達により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。
これを各不動産についてみると、通達評価額と鑑定評価額との間には大きな乖離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない。
もっとも、各不動産の購入・借入れが行われなければ相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるが、これが行われたことにより、各不動産の価額を評価通達により評価すると、課税価格の合計額は2,826万1,000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、納税者らの相続税の負担は著しく軽減されるというべきである。
そして納税者らは、各不動産の購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において納税者らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。
そうすると、各不動産の価額について評価通達による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と本件における納税者らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。
したがって、各不動産の価額を評価通達により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできないとしています。
結論
以上によれば、更正処分において、税務署長が相続税の課税価格に算入される各不動産の価額を各鑑定評価額に基づき評価したことは、適法というべきである。
まとめ
今回の記事ではタワマン節税の裁判で最高裁まで争われた判決を詳しくみてきました。
個人的な意見としては、「特別な事情があるものは不動産を評価通達により評価した価額を上回って評価することについては平等原則に違反するものではない」ということが明確になりました。
ただし、「評価通達による画一的な評価を行ったことによって租税負担の公平に反するというライン」というものがこの判決では明確にはできなかったことで、今後もタワマン節税については注視していかなければならないかと思います。
このような中でタワマン節税について令和6年1月1日以後の取引から税制改正が入りました。
こちらの改正についても実務での情報が増えてきた段階で今後記事にしていきたいと思います。