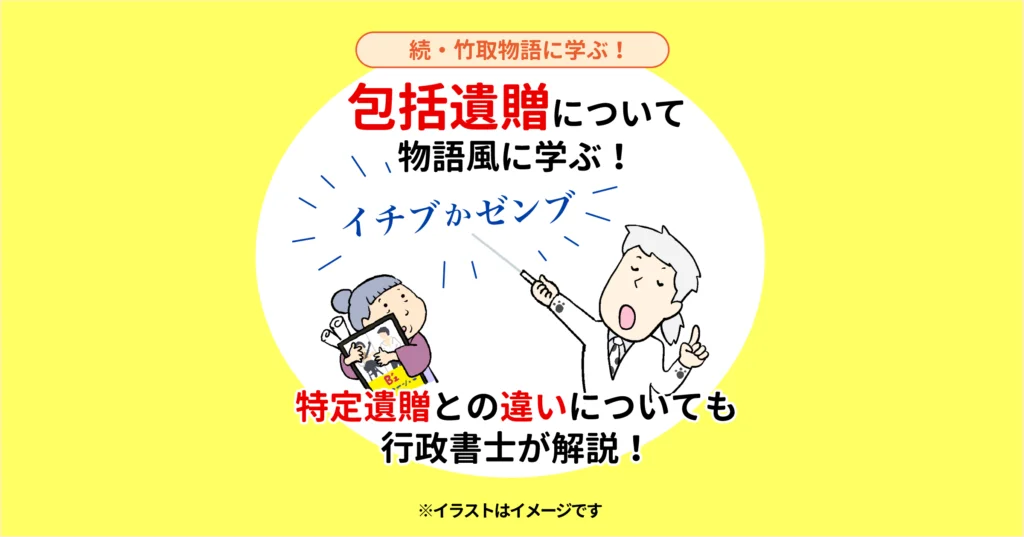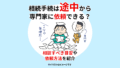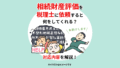遺産の一部か全部を、相続人や、相続人以外の人や団体に無償で譲ることを「遺贈」といいます。
そして遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、それぞれルールが異なることをご存知でしょうか。
遺言書に「遺贈する」と書かれていた場合、このルールを知ったうえで手続しなければなりません。
この記事では、遺言書で遺贈した場合の法律関係について、「物語風」に解説します。
遺贈する種類の違いについて分かりやすく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。
おじいさんとおばあさんの愛犬、シロが「ここ掘れわんわん」と小判を探り当てるやいなや、なんと2人は大金持ちにて大フィーバー。
神様の粋な取り計らいで人間にしてもらうことができたシロは、おじいさんとおばあさんをしっかり看取り、おじいさんの遺言書を見たことがきっかけとなり、行政書士になりました。
今では「シロ行政書士事務所」とし、近隣の村人たちが次々と遺言がらみの相談をしてくるようになりました。
さてさて、今回は、そんなシロのもとに、またひとり、相談者のおばあさんがやってきましたが…。
遺贈とは
おばあ「シロや、ちょっと教えてくれんか。こないだ、隣町の竹取のじいさんが、遺贈はするのかと聞いてきたんじゃ。わしゃ、なんのこっちゃわからんでな」
シロ「竹取のじいさん、きっと昨日今日覚えた言葉を見せびらかしたかったんでしょうね」
おばあ「その前は『エビデンス』とか、『DX』とか、しきりに言っておったな」
シロ「あのじいさん、流行り言葉を使えばモテるとでも思ってるんでしょ。ま、遺贈は流行語じゃないですけどね。
遺贈というのはね、遺産の一部か全部を、相続人や、相続人以外の人や団体に無償で譲ることなんです」
おばあ「『イチブトゼンブ』っていったら、わしの好きなB’z様の名曲じゃないか」
シロ「予想外の角度から来たな…あと、一部「か」全部ね…。遺贈は、相続人以外の人へ財産を承継させたい場合に使うことが多いんですよ」
おばあ「ということは、あたしが息子以外の人に財産をあげたいとなったら、遺贈をすればいいってことかい?」
シロ「まあ、そうなります。たとえば遺言書に、『Aさんに○○を遺贈する』って書けば、息子以外の人に財産をあげることも可能ですよ」
おばあ「どれくらいかかるんだい、その、遺贈費とか、そういう、ほら、ね?」
シロ「要するに、金かけたくないわけでしょ(笑)」
おばあ「まあの(笑) 日々是節約じゃ」
シロ「心配しなくても、遺贈するのにお金はかかりませんよ。有効な遺言書によって遺贈がなされると、効力は遺言者の死亡時から発生します。で、遺贈の対象となっている権利は遺贈の効力発生と同時に受遺者に移転。受遺者ってのは、財産を受け取る人のことね」
おばあ「じゃ、あたしが死ねば、効力が生まれるのか…それって、なんだか死者の呪いみたいだねえ…」
シロ「こええええよ! むしろ意味的には逆だよ!」
包括遺贈と特定遺贈の違い
シロ「遺贈は大きく分けて2種類。特定遺贈と包括遺贈ってのがあってね」
おばあ「なんだか難しそうじゃの…話途中で寝たらすまん」
シロ「そんときはそんときで(笑) 特定遺贈ってのは、ざっくり言うと、遺贈したい財産を具体的に指定する遺贈ね。つまり、Aさんにはこの土地、Bさんには預貯金、Cさんにはばあさん愛用のB’zさんのポスター全部とか」
おばあ「B’z様のポスターは絶対やらん! イチブたりともやらん!」
シロ「目…バッキバキやぞ…。で、包括遺贈ってのは、割合を指定して遺贈することね。例えば、Aさんには財産の半分、Bさんには財産の1/3とか」
おばあ「…ふうむ、要するに特定遺贈は種類で、包括遺贈は割合という違いってことじゃの」
シロ「ま、わかりやすく言えばそうですね。ちょっとまとめるとこんな感じね」
特定遺贈の特徴
特定遺贈では遺贈する財産を具体的に指定する
遺言書に書かれた財産がそのまま受遺者に承継される
遺言者が指定しない限りはマイナスの財産が引き継がれることはない
合わせて読みたい:特定遺贈とは?包括遺贈との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説
包括遺贈の特徴
包括受遺者はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も承継してしまう
財産内容が変わっても遺贈は無効とはならない
遺産分割協議に参加する必要がある
包括遺贈の放棄をする場合、原則として3ヶ月以内にしなければならない
おばあ「おや、包括遺贈だと、問答無用で借金とかも承継してしまうということかい?」
シロ「そこ、けっこう大事なとこでね。包括遺贈をするときは、借金などのマイナスの財産がないかどうか、しっかりと確かめておかないと相手に迷惑をかけちゃうんですよ。
もっとも、相手方にも、遺贈を放棄という選択肢があるのはありますけどね。包括遺贈を放棄したいときは3ヶ月以内にしなければならない決まりもあるので、そこは気を付けてください。」
合わせて読みたい:遺贈は放棄できる?遺贈の放棄と注意点を行政書士が解説
遺言書に書かれた財産内容が変わっても包括遺贈は有効
おばあ「じゃあさ、例えばよ。財産の内容が変わったとしたら、どうなるんじゃ?例えばわしの預貯金が1億だと遺言書に書いていて、死んだときにそれが8000万になったとかしたら」
シロ「けっこうため込んでるんですね…しかも、この先2000万も何に使うんです?」
おばあ「いや、だってこの前知り合ったホストが新しい外車ほしいって…」
シロ「すぐに縁を切れ…。ともかく、財産の内容が変わっても、包括遺贈は無効にはなりませんよ。包括遺贈は、『死亡時における全資産のうちの何割』っていう指定ができるわけですから。
一方、特定遺贈の場合、例えば指定していた不動産を生前に売ってしまったと言う場合、対象が消滅しちゃってますので、受遺者は財産を承継できないんです」
合わせて読みたい:遺言書に書いた財産を生前に処分した場合はどうなるの?その効果について解説!
受遺者が先に亡くなっていた場合の相続手続
シロ「ちなみに、遺言書に包括遺贈すると書いても、受遺者が先に亡くなってしまうこともありますよね。この場合の相続手続がどうなるか、分かりますか?」
おばあ「受遺者が亡くなるってのは、なかなかに盲点じゃな」
シロ「ですよね。たとえば相続人であれば子供に相続権が発生し、代襲相続をすることができます。
でも、遺贈を受け取る受遺者の場合、代襲相続は発生しないんですよ」
おばあ「相続権がないということは、包括遺贈そのものが無効となってしまうわけかの?」
シロ「そうですね。遺言全体が無効となるわけではなく、当該死亡した受遺者に遺贈するはずであった部分についてのみが無効になります。なので、予備的に遺言を遺しておくのがいいんです。例えば、先に受贈者が亡くなってしまった場合には、その受遺者の子供であるAに対して遺贈する…とかね」
おばあ「もし予備的な遺言がなかったら、どうなるんじゃ?」
シロ「予備的な遺言がない場合、亡くなった受遺者にあてた包括遺贈そのものが無効となるので、遺贈されるはずだった財産は法定相続人に帰属します。遺言書に記載がない場合は、遺産分割協議に基づいて相続することになりますね。
ちなみに法定相続人ではない受遺者には、影響はありませんよ。取り分が増えるということもありません」
関連記事:遺言者より先に包括受遺者が死亡した場合に他の包括受遺者の取り分は増加する?
包括遺贈の手続は行政書士に任せられる
おばあ「包括遺贈については分かったが、それを実際に手続するとなると、面倒じゃのう。シロや、包括遺贈の手続は、行政書士のお前さんに任せることはできるのかい?」
シロ「行政書士ですから、できますよ、遺言執行業務の一つとしてお任せいただけます。」
おばあ「そうかそうか、それじゃあ、ひとつシロにお願いするとしよう。報酬はドッグフードでよかったのかの…?」
シロ「…そこについても、協議しましょう」
横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続・遺言執行を承っております。初回相談は無料なので、何かお悩みのことがある方はお気軽にお問い合わせください。