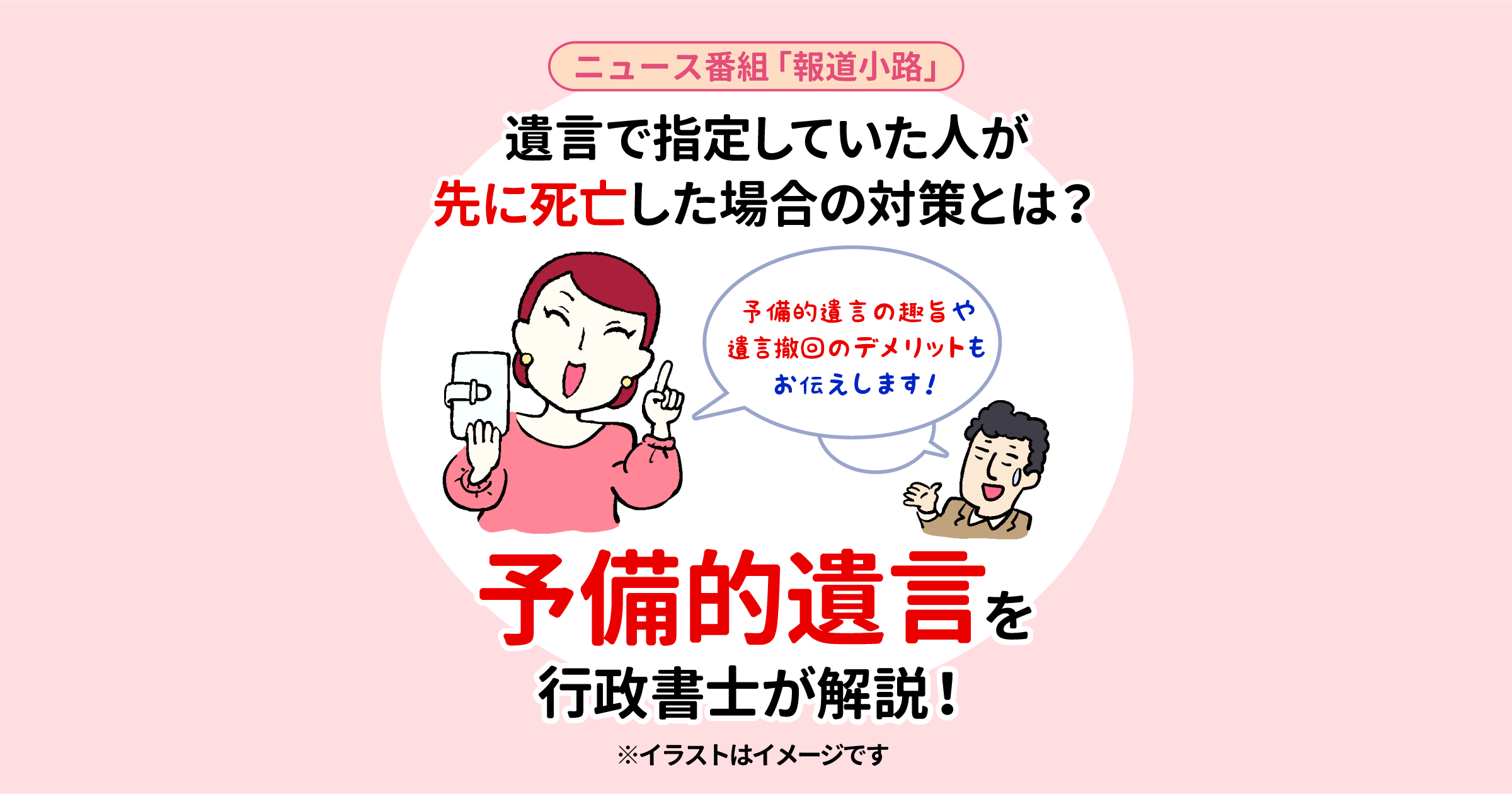遺言書には「○○を長男 横浜 一郎に相続させる」などと記載しますが、もし遺言書で指定した受取人・相続人が、遺言者よりも先に亡くなったら、その遺言書はどうなるのでしょうか。
今回は、遺言で指定していた相続人または受遺者が遺言者より先に死亡していた場合の対策について、「報道ニュース風」に解説していきます。
・・・・・
皆様、こんばんは。社会の構図をわかりやすくお届けするニュース番組「報道小路」のお時間です。アナウンサーの西園寺遺子です。
この西園寺がさまざまな現場を徹底的に取材しており、この合成皮の手帳、通称、白革の手帳にまとめておりますのでご期待ください。
そもそも遺言は、自分が亡くなったあとのことを考えて作成するもの。でも、いつ何がどうなるか正確に将来を予見するのは難しいものです。
もし遺言書で指定した受取人・相続人が、遺言者よりも先に亡くなったら、その遺言書はどうなってしまうのでしょうか?
本日はコメンテーターとして、世美有人さんにお越しいただいております。
では、早速まいりましょう。いつものセリフでスタートです。
「私、調べましたけど!」
遺言者より受取人が先に死亡したら、その部分は無効になる
実は遺言者より受取人が先に死亡したら、遺言書のその部分は無効になります。
遺子「さて、さっそくですが世美さん。遺言者より受取人が先に死亡したら、その部分は無効になってしまうんですね!」
世美「驚きですよね。受取人の相続人が、代わりに財産をもらうことはできないのでしょうか?つまり代襲相続のようなことは、遺言書では生じないのでしょうか?」
※代襲相続というのは、相続人が死亡するより前に法定相続人が亡くなったとき、その法定相続人の子(直系卑属)が親の代を飛び越えて相続人となり遺産相続をしていくというものです。
遺子「はい、代襲相続されません。受け取る人がいない場合、遺言のその部分については無効になるからです。無効になる以上、代襲相続も発生しないということですね」
世美「つまり『遺言では書かれていなかった』という扱いになるわけなのですね。ちなみに、無効になった場合はどのようになりますか?」
遺子「その場合は、誰のものかわからない財産ということになりますので…遺産分割協議をしなくてはいけないんですよね。そもそも遺言を残すときは『遺言書を作れば、遺産分割協議を経ずに円満に相続が終わるだろう』と残された人たちは思っているかもしれません。しかし指定された相続人が先に亡くなっているなどしたら、遺産分割協議が必要なんですよね」
世美「そうなっちゃいますよね」
予備的遺言がある場合は、その内容に従って相続手続する
遺子「しかしですね、もし予備的遺言がある場合は、その内容に従って相続手続することになります」
世美「予備的遺言があれば、遺産分割協議が必要ないということですね!」
遺子「さて、さっそくですが世美さん。予備的遺言の『予備』という言葉が混乱を招くケースも少なくないと聞きますね。予備的遺言とはどんなものか、ご存知でしょうか?」
世美「そうですね、本来予備的遺言は予備の…」
遺子「受取人を指定するものですよね」
世美「…そうですね(さっそくコメントを奪われた…これがコメンテーター泣かせの西園寺さんの悪クセ…)」
遺子「例えば同年代の夫婦がいたとしましょう。夫が遺言を残し、不動産の相続人を妻にしていた。しかし相続が始まった時点で、妻が先に亡くなっていて相続人が不在になる可能性もゼロではありません」
世美「このような場合に…」
遺子「他に不動産を相続させたい人がいるならばその人を予備的に遺言内で指定することができるとおっしゃりたいのですよね?」
世美「…はい。ただし遺贈でも予備的遺言は使えます」
遺子「といいますと?」
世美「相続人以外の人に遺産を受け取ってもらえるような書き方にすると、遺贈という行為になっちゃいますから」
遺子「遺贈は、相続以外で誰かに遺産を遺す手段ですね。遺贈でも使えるとなると、予備的遺言はさまざまな場面で使われていそうですね」
予備的遺言が使われている例
遺子「では予備的遺言が想定している使用例を見ていきましょう」
予備的遺言の目的はどのようなものなのか?どのようなケースに主として使っていけばいいのか?主には3つのケースがイメージできます。
- 遺言者と同年代の人に相続させたい場合
- 遺言を作った時期が早い場合
- 遺言執行者を指定している場合
遺言者と同年代の人に相続させたい場合
遺産を遺す側と遺される側が年齢的に近い場合、もしかしたら遺される側が先に亡くなるかもしれません(もちろん不慮の事故や病気などで若い方でも死亡リスクはゼロではありません)。このような場合、亡くなったら新しい遺言を作るとなると大変になります。
そのため遺言者と同年代の人に相続させたいときに、予備的遺言はよく活用されているのです。
遺言を作った時期が早い場合
例えば「思考がはっきりしているうちに遺言を作成しておきたい」などの理由で、遺言を作った時期が非常に早いというケースでは、その後の状況の変化に、遺言内容自体が追い付かない可能性があります。
そのため若くして遺言書を作った場合にも、予備的遺言はよく活用されています。
遺言執行者を指定している場合
予備的遺言は、遺言の内容を実現する役割の「遺言執行者」に関して使われることもあります。
執行者になるのを拒否する方もいるため、そのような場合に備えて、予備的な条項を用いて次の執行者も指定しておくというケースです。
合わせて読みたい:民法改正!遺言執行者の権利義務とは?明確になった立場を行政書士が解説!
遺言書で指定した受取人・相続人が先に亡くなっていた場合の相続も行政書士に相談できる
遺子「さて、世美さん。ここまで予備的遺言の想定ケースを見てきましたが、予備的遺言は必ず備えなくてはいけないものではないわけですよね」
世美「はい、なので現実的には、遺言書で指定した受取人・相続人が先に亡くなっていて、遺言書のその部分が無効となってしまっているケースも少なくありません」
今まで遺言者より先に死亡した場合の「予備的遺言」について見てきました。
私たち行政書士が遺言書の作成をサポートする場合には、予備的遺言を記載しないことがないほど、大事な条項であると言えます。
しかし専門家に頼らず自分で遺言書を作っていた場合には、予備的遺言がないことも多いです。
この状況で遺言書で指定した受取人・相続人が先に亡くなっていた場合は、遺言書のその部分が無効となっているため、遺言書の執行とあわせて、遺産分割協議を開催する必要があります。
このような事態となり、もし相続手続をどのように進めたらいいのか分からないという場合には、横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。遺言執行とあわせて、遺産分割協議書の作成、その後の相続手続についてもサポートいたします。