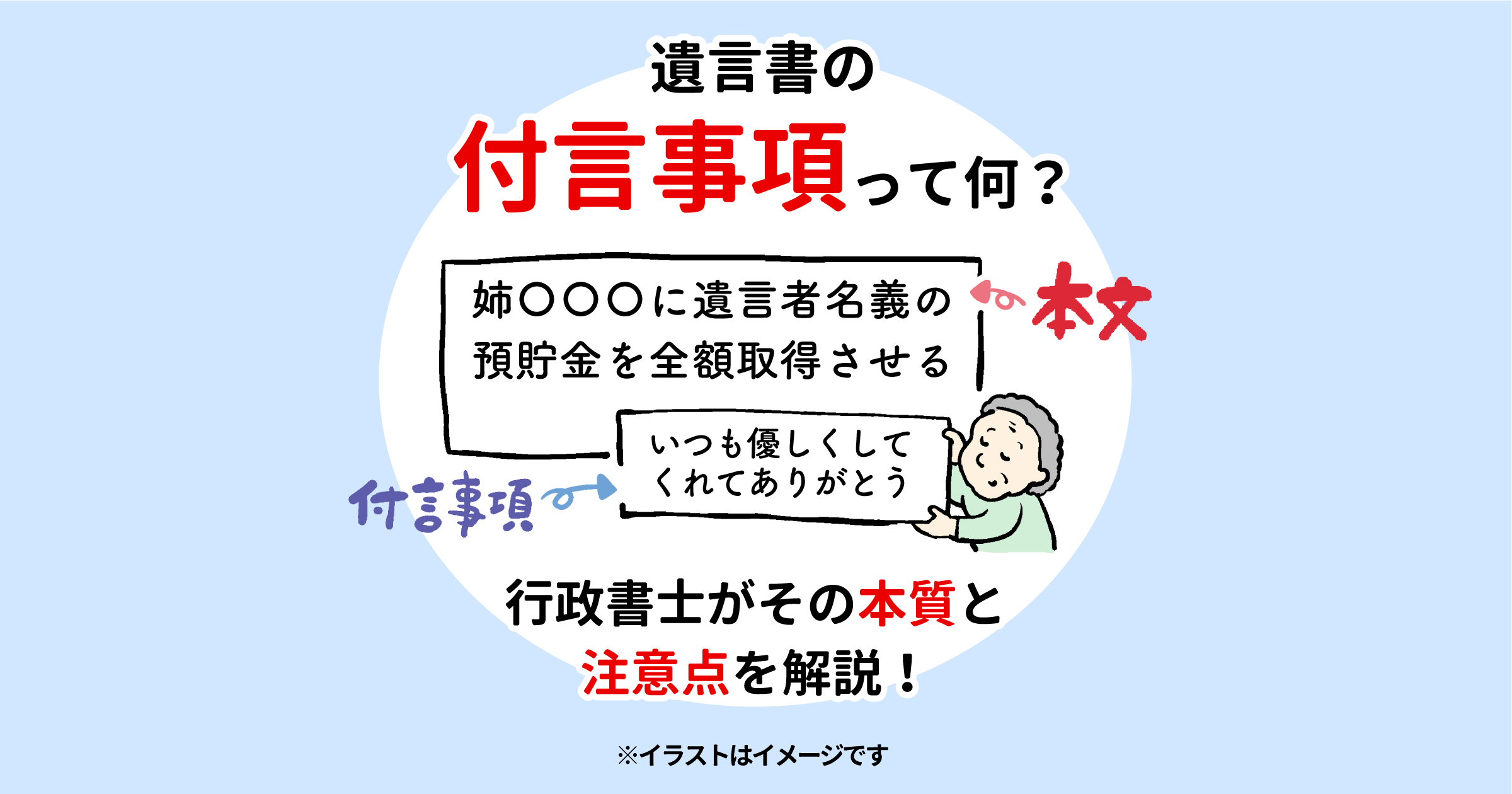「自分の気持ちを遺言に書いてもいいの?」
「遺言の付言事項って何?そこに書かれていることも、相続人は守らないといけないの?」
遺言は法的な行為であって、定められた形式に沿って行う必要があります。また、書くことのできることも決まっています。
しかし、では一体何を書くことができるのかはあまり実際に把握されていないのではないでしょうか。
例えば、遺言には自分の気持ちを書くこともできるのでしょうか。もし遺言書に故人の気持ちが書かれていたら、相続人は必ずそれを守らないといけないのでしょうか。
今回はそんな遺言書にはどんなことまで書けるのか、相続人はどこまで守らないといけないのかというお話をしたいと思います。
遺言書の法的効果
遺言書には書くことによって法的に効果を発揮するものと、法的に効果を発揮しないものがあります。
つまり、書くことによって権利義務が決定してしまうものとそうでないものが分かれている、ということです。
最初に、遺言のうち法的に効果のあるのはどの範囲かを確かめてみたいと思います。
合わせて読みたい:法定遺言事項とは?遺言書に書いて効力が発生する内容を行政書士が解説!
相続に関する事項
例えば相続分を指定したり、遺産分割の仕方を指定したり、あとは例えば自分に対して虐待などをした相続人を廃除したりと、誰が相続するか、どう相続するかを決めることができます。
合わせて読みたい:特定財産承継遺言とは?遺贈との違いや作成時の注意点を行政書士が解説
相続以外の財産の処分に関する事項
相続以外では、やはり遺贈が一番有名だと思います。「相続人以外の人でもお世話になったから、遺産を受け取ってほしい」と遺産を家族でもない第三者にあげてしまうのが遺贈です。
こちらも記入することによって法的な効力を発揮します。
合わせて読みたい:NPO法人に遺贈する旨の遺言を作りたい! 書き方や注意点を教えて!
身分に関する事項
たとえば遺言によって「ある人を自分の子と認める」認知という行為ができたりします。
相手の身分を認めてあげると、それで子となり、相続に影響がありますから重要な行為だといえます。
合わせて読みたい:相続廃除とは?特定の相続人に相続させない方法を行政書士が解説
遺言の執行に関する事項
遺言があっても、現実にそれを実現する人が必要です。
そうやって遺言内容に沿って現実に土地を売ってお金を相続人に分配したりする人を遺言執行者と言いますが、遺言でその執行者を指定することができます。
合わせて読みたい:遺言執行手続きとは?行政書士がポイントを解説!
付言事項とは
先述した法定遺言事項以外で遺言書に書かれていることは、すべて付言事項ということです。
大まかに言えば、遺言書の付言事項とは、権利義務に直接関わることではなく、いわば単なるメモ書きやメッセージのようなものになります。
法定遺言事項と付言事項の決定的な違いは、法的効果があるかないかです。
付言事項には法的効果がないため、たとえ遺言書に書いてあるからといって、それが何か相続人やそれ以外の人の権利義務に影響を与えるわけではありません。
これが一番大きな違いとなります。
ただし、法的効果がないといっても、付言事項は遺言書に任意に書くことが可能です。そして付言事項の書く内容は任意なので、特に所定の記載方法がある訳ではありません。
付言事項によく書かれるのは、やはり家族に対する気持ちや葬儀やお墓に関することなどです。
どちらかといえば、現在の気持ち、あるいは自分が亡くなったあとの事実関係をどうするか、という感じです。
ただし遺言書の重要な点は、やはり相続に関するものなど法的効果がある部分です。ですので、あまり長く付言事項ばかり書いてあると、遺言書自体が長くて、感情的、かつ曖昧なものになってしまい、わかりづらい遺言書になってしまいます。
付言事項がつけられるからといって思ったままに書くのもよくないかもしれません。
エンディングノートと付言事項の違い
最近ではエンディングノートというものも流行っています。遺言書の付言事項とエンディングノートは、権利義務に直接関係のないことを記していく、という点では変わりがありません。
それでも両者とも性質の違いがありますので、少し比べてみましょう。
合わせて読みたい:エンディングノートとは?遺言書と比較してその長所、短所を行政書士が解説!
付言事項は付け加えて書くという感覚
付言事項はそれ自体がメインのものではなく、どちらかといえば付け加えて書いておくという感覚です。
遺言の主役はやはり、相続や遺贈、または遺言執行者に関することであって、多くの場合は付言事項ではないでしょう。
遺言書を作る際、「そういえばこれも言っておいた方がいいな」という感覚で付け加えるのが一般的です。
たとえば葬儀はこうして欲しい、とか、遺産に関してこの人に多く残したのはこんな理由ですよ、とかのように伝えたいことがシンプルでそれほどの量がないのなら、付言事項に書いておけば充分でしょう。
エンディングノートの方が自由度が高い
付言事項と比べると、エンディングノートの方が自由度が非常に高いです。
例えば付言事項はあくまでも遺言書内で書くことですから、絵を描いたりすることはできません。
しかしエンディングノートなら絵を描いてもよし、詩を書いてもよし、とにかく自由に表現ができる場所になります。
本当に書きたいことがあるのなら、何冊作っても構いません。やはり人生の最期に遺すものですから、エンディングノートで納得のいくまでやってみてもいいでしょう。
付言事項に書かれる具体例
それでは、遺言書の付言事項は実際にどんなことが書かれるのでしょうか。
傾向的かつ一般的に考えて、こんなものが書かれる、というようなものがありますのでそれをご紹介したいと思います。
- 葬儀に関する事項
- 遺言内容の理由の説明に関する事項
- 遺留分に関する事項
葬儀に関する事項
例えば、お葬式はどこの宗派のもので、父母の際に執り行われた形式で行って欲しい、というようなことが書かれたりします。
また、葬儀の喪主は誰にする、などを書くこともあります。
遺言内容の理由の説明に関する事項
どうして遺言に定めたように遺産を遺したいのかを説明することも多いです。例えば、遺産を特定の相続人に多く遺したような場合、他の相続人からすると少し不可解かつ不満に映ります。
その理由を遺言内で明示することによって、意図が明らかになって不要なトラブルを防ぐことができる可能性があります。
例えば「これから生活が大変になるだろう妻に多くを遺すようにしました」と説明をすれば、遺族の理解が深まります。
遺留分に関する事項
さきほどの遺言内容の理由ともリンクしますが、他の相続人よりも多くの遺産を特定の誰かに遺した場合、遺留分というものが問題になることがあります。
遺留分とは簡単に言えば、法定相続人であれば最低限もらえる遺産の範囲、になります。
これは多くを受け取った相続人に対し、「せめて最低限の遺産をください」と意思表明し、その権利を行使して初めて遺産をもらうことができます。
しかし、例えば生活に困っている妻を助けたいという理由でたくさんの遺産を遺したのに、遺留分を主張されたらあまり意味がありません。それどころか裁判などで大変になる可能性もあります。
あくまでも相続人同士の関係を考えてですが、こちらも書かれることがあります。
合わせて読みたい:遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!
付言事項が書かれた遺言書を見つけたらどう相続手続する?
付言事項が書かれた遺言書を見つけたら、どのように相続手続を進めればいいのでしょうか。
まずは付言事項の有無に関わらず、その遺言書が有効なものであるのか判断しなければなりません。
公正証書遺言なら、有効である可能性が高いでしょう。
自筆証書遺言なら、勝手に開封してはなりません。検認手続きを経て中身を確認した後、有効かどうか判断します。
関連記事:遺言書の検認申し立てをしないとどうなる?過料や注意点、手続き方法を行政書士が解説!
遺言書が有効なら、法定遺言事項の部分、つまり法的拘束力がある部分については、遺言書の内容に沿って手続を進めます。
そして付言事項の部分は、法的拘束力がないため、従わなくても問題はありません。しかし故人の気持ちを反映することを考え、従う方が多いのも事実です。
もし従ったほうがいいのかどうか迷ったときは、相続手続の実務に詳しい専門家に相談してみてもいいでしょう。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続全般についてご相談を承っております。
付言事項が書かれた遺言書を見つけたものの、どのように手続を進めたらいいのか分からず困っている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。