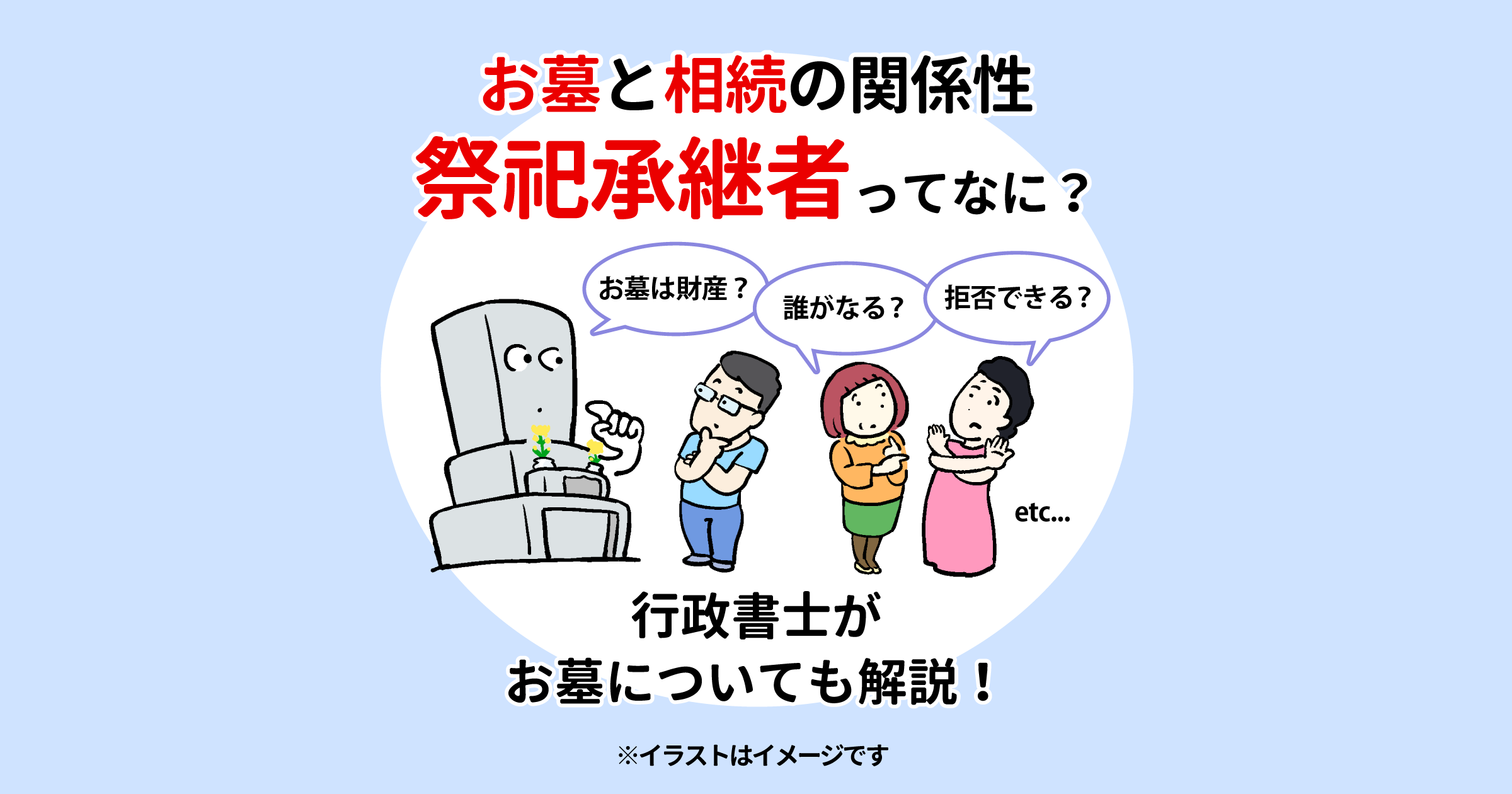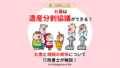「お墓って相続でどのように扱うの?」
「祭祀承継者ってなに?相続でお墓を引き継ぎたくないときはどうすればいいの?」
「墓じまいは誰に相談すればいいの?」
相続手続に伴って、「お墓」の存在が問題になることも少なくありません。
そもそもお墓は、相続人が引き継ぐものなのでしょうか。また、相続でお墓を引き継ぎたくないときはどうすればいいのでしょうか。
この記事では相続とお墓の関係や、お墓を引き継ぎたくないときの選択肢について、行政書士が解説します。
お墓と相続の関係
相続でお墓を引き継ぎたくないときはどうすればいいのか考える前提知識として、まずはお墓と相続の関係について解説します。
ポイントは次のとおりです。
- お墓は祭祀財産
- 祭祀財産は”祭祀承継者”が引き継ぐ
- 祭祀承継者の指定は拒めない
- 祭祀財産は相続財産ではなく、相続放棄もできない
お墓は祭祀財産
意外と考えたことがないのがお墓とはどんな財産なのだろう、ということではないでしょうか。
お墓は祭祀財産といった、あまり聞きなれないものに分類されます。
祭祀とは、神々や祖先など目に見えない存在のためにお祭りのようなことをすることです。
具体的な例を挙げると、お墓の他にも仏壇などは祭祀財産に分類されます。
祭祀財産は”祭祀承継者”が引き継ぐ
祭祀財産は普通の相続財産とは違って、相続分にしたがって共有されるわけではありません。
先祖代々伝わるものですので、一般的にはひとりの人がそれを代表して受け継ぐという形をとることになります。
そしてそういったお墓や仏壇といった伝統的な財産を受け継ぎ、それらを管理したりお葬式などの儀式を主催する人を専門的な言葉では祭祀承継者と呼びます。
祭祀承継者の役割は、主に次のとおりです。
- お墓などの管理
- 行事(祭りごと)
- お墓をどうするかを決める
お墓や他の祭祀財産を管理するのが祭祀承継者の役割となります。管理とはお墓の手入れやお布施も含めて、そのお墓を維持するための費用を払うことなど、やることはとても多いです。
先祖のために法事を主催するのも祭祀承継者の仕事になります。親族をみんな集めて、先祖を供養するための行事を執り行います。
そして、これがとても重要なことですが、祭祀承継者はお墓を受け継いでいて、つまりは所有権があります。
ですから「お墓が遠くにあって大変だ」といった事情がある際に、墓じまいをして先祖のお墓を別の場所に移動することもできます。今は離れて住む人も多い時代ですから、お墓を移動することも多くなるかもしれませんね。
このように祭祀承継者、つまりお墓を引き継ぐ人はやることが非常に多いので、「相続でお墓を引き継ぎたくない」と思う方が多いともいえます。
祭祀承継者の指定は拒めない
それでは、祭祀承継者はどんな風にして決められるのでしょうか。主な例は次のとおりです。
- 長男や長女
- 遺言書で指定された人
- 慣習で決まった人
- 家庭裁判所が決めた人
皆さんもイメージしているようにやっぱり長男や長女といったその家系を直接的に担っていく方がお墓も含めた祭祀財産を受け継ぐケースは多いです。また、長男や長女が遺言執行者(遺言書の内容にそって相続手続を進める人)を兼ねていることもありますので、その場合はついでにお墓に関わることもやってもらえたらと考えるのは自然なことかもしれませんね。
しかし、お墓の新しい所有者は、別に親族でなくてもなることができます。たとえば遺言書ではっきりと「祭祀財産を受け継ぐ人」が指定されているときは、その遺言にしたがってその人が受け継ぐことになります。
※実は祭祀承継者は現在の承継者からの口頭での指定も可能ですが、証拠に残らないためトラブルになることも予想されます。
また、慣習というその地域のしきたり等も祭祀承継者を決める基準になります。
後ほど条文を適示しますが、法律に慣習が根拠になると書かれていますので、慣習も祭祀財産や祭祀承継に関しては非常に強力なのがわかります。
しかし、遺言で指定されていなく、また慣習によって祭祀承継者になる人もいないという事態もあるでしょう。
そういったときは、最後に裁判所に助けてもらうことになります。具体的には家庭裁判所が調停(裁判所を介した当事者の話し合い)や審判(話を聞いてもらったのち裁判所に判断してもらう)をして、祭祀承継者を決めることになります。
以下、根拠となる条文を見てみましょう。
民法897条1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
同条2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
また、墓地によっては使用規則で、お墓の新しい所有権者は親族などに限っていることもあります。法律上では親族でなくても祭祀財産を受け継ぐことはできますが、当事者の取り決めもありますのでそれはチェックをした方がいいでしょう。
前置きが長くなりましたが、祭祀承継者に選ばれた人が「やりたくない」といった理由で拒否することは原則許されていません。
実際に法事などを主宰するかは自由ですが、祭祀承継者という立場を拒否することはできないことになっています。
もし選ばれたら、責任をもって全うすることが必要となります。
祭祀財産は相続財産ではなく、相続放棄もできない
ここから本題に入りますが、祭祀財産は相続財産ではないため、相続放棄ができません。つまり相続放棄したとしても、お墓も引き継がなくていいわけではないのです。
反対に考えると祭祀財産は相続財産ではないため、事情があって相続放棄したとしても、引き継ぐことができます。
そもそも相続財産とは、亡くなった人が持っていた財産であって、一般的には遺産と呼ばれたりもします。
しかしお墓は「個人で所有する財産」というよりも、「先祖からずっと受け継がれてきた財産」と考えられます。そのような観点から考えると、お墓など祭祀財産が相続財産ではないのも、どことなくわかる気がしますね。
繰り返しとなりますが、お墓は相続放棄できません。つまり相続でお墓を引き継ぎたくないにも関わらず祭祀承継者となってしまった場合、なにか別の方法を考える必要があります。
相続でお墓を引き継ぎたくないときにすべきこと
相続でお墓を引き継ぎたくないときにすべきこととしては、次の2つが挙げられます。
- 墓じまい
- 永代供養墓への移転
それぞれ詳しく見ていきましょう。
墓じまい
「お墓じまい」とは、今あるお墓を撤去することです。撤去後は、お墓の使用権を墓地管理者に返還します。
しかし、たとえお墓の所有者であっても、勝手にお墓じまいすることはできません。
お墓じまいは、厳密にいうと「改葬」を行うことになります。
そして「改葬」は、各市区町村の許可を受ける必要があると法律で定められているのです。
墓じまいの流れを見てみましょう。
- 本当にお墓じまい(改葬)をするかどうか、家族・親族で慎重に話し合う
- 墓地管理者にお墓じまいをしたい旨を伝え、了承をもらう
- ご遺骨を移す場所を決定する
- 墓地管理者から埋蔵証明書をもらう(改葬許可申請書に捺印してもらう)
- 墓地がある自治体で改葬許可証を取得する
- 遺骨の移動および墓石などの撤去を行う
- 墓地管理者へ敷地の返還を行う
新しく遺骨を移す場所を決め、改葬許可を経ることで、はじめて墓じまいを進められるのです。
関連記事:お墓じまいとは?改葬方法や相続に併せた手続について行政書士が解説!
永代供養墓への移転
墓じまいするために新しく遺骨を移す場所を決めるとなると、結局お墓はなくならないのではないかと思う方もいるかもしれません。
ここで検討したいのが永代供養墓への移転です。
永代供養墓(合祀墓・合同墓含む)とは、霊園・寺院などが遺族に代り、供養・管理を行ってくれる施設です。
墓じまいをし、移転先に「永代供養墓」を選べば、施設にお墓の管理・供養を任せられます。結果として、親族間で”お墓を継承”する必要がなくなるのです。
なお、墓じまいをした後に散骨する選択肢もあるかもしれません。しかし散骨は法整備が整っているわけではなく、散骨によるトラブルに発展する可能性もあるため、基本的には「永代供養墓」に移転したほうが安心でしょう。
相続でお墓を引き継ぎたくないときは行政書士に相談
長岡行政書士事務所でも日々相続手続をサポートしている中で、お墓が遠かったりして、とてもじゃないがお墓参りや管理ができないという話をときどき耳にします。
お墓を動かすのも大変だし、新しい墓地を探しても受け入れてもらえるのかも不安、という方も実際に見てきました。
あまり知られていないことですが、行政書士はお墓の手続きも代行できます。お墓を動かすときには「改葬許可申請」を役所に提出しますが、行政書士ならそれをお客様の代わりに行うことができます。
新しいお墓を見つけたり、霊園やお寺の方と話し合いをしたり、そういった墓じまいにまつわるとても骨の折れる作業を、当事務所なら書類作成から提出まですべて含めて代行することができます。
永代供養墓を墓じまいした後の移転先に選ぶことで、結果としてお墓の管理を専門施設に任せることも可能です。
「相続したけどお墓を引き継ぎたくない」というときは、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。初回相談は無料です。