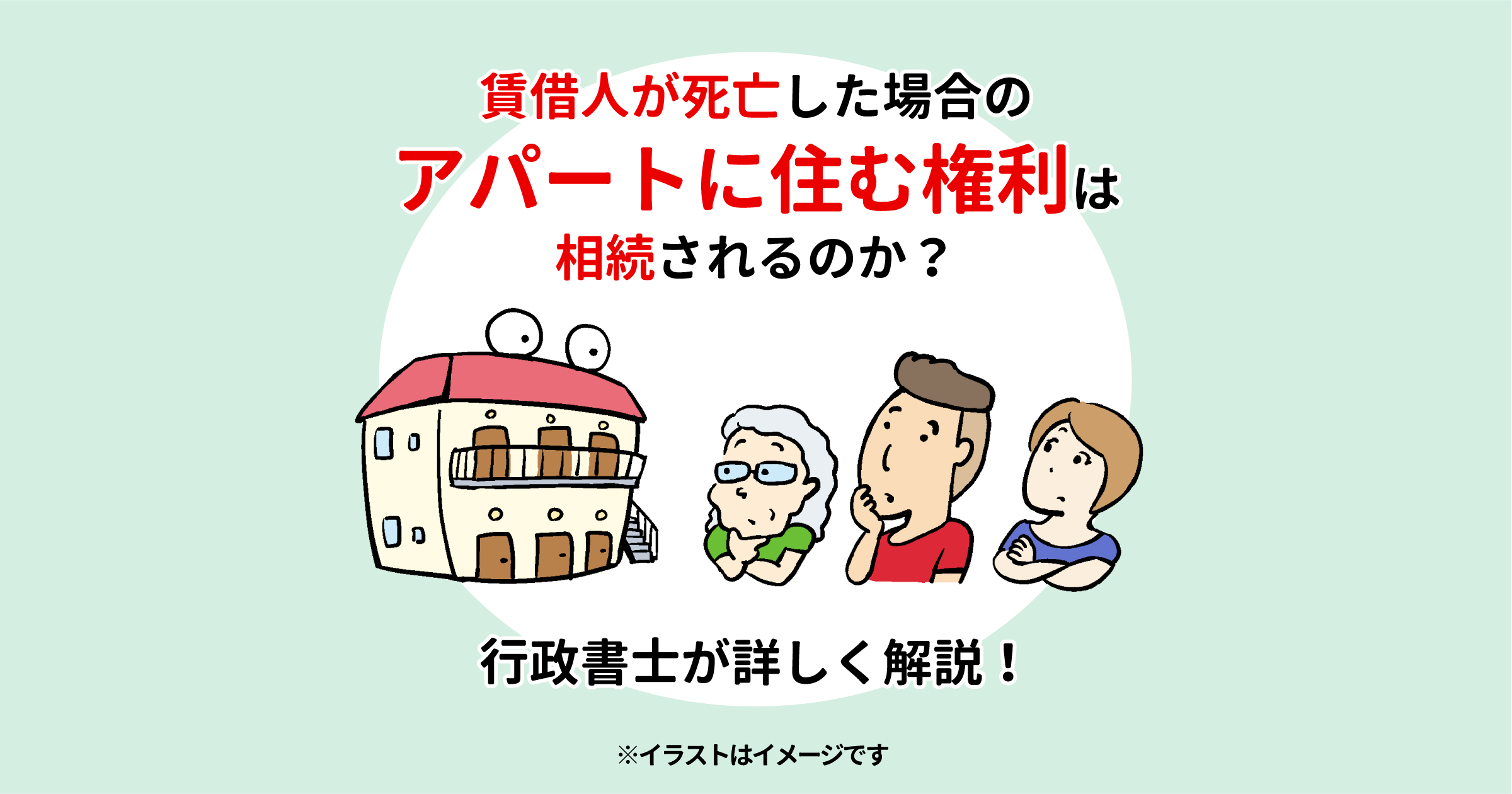「夫が死んだあとアパートに住めるの?」
「相続中の家賃ってどうなるの?」
「内縁の妻だけど、アパートを借りている内縁の夫が亡くなったら、アパートから追い出されてしまうの?」
人の生活は多種多様ですから相続もその時と場合によって、柔軟に考えていく必要があります。
たとえば一家の大黒柱である父がアパートを借りて暮らしていて、その父が死亡した場合、その遺族はそのアパートに暮らし続けることができるのか、あまり考えたことがない問題ではないでしょうか。
普通に考えたら、それじゃ遺族の住むところがないから住んでもいいんじゃないか?となりそうです。
しかし、父が安定してお金を稼ぐことができるとわかっているから、大家さんは安心してアパートを貸すことができたわけです。
それが他の人に変わってしまったら払ってくれるのだろうか?という観点もあります。
こうした場合、相続ではどのようになるのでしょうか。
今回は賃借人が死亡した場合の相続問題を解説していきたいと思います。
アパートの賃貸借契約の法的な性質
それでは「アパートを借りる」という契約である賃貸借契約の基本的な特性を最初に確認していきたいと思います。
物を使用できる代わりにお金を払う
アパートを使わせてもらう代わりにお金を払う。所有者と使っている人が違うというのが大きな特徴です。
お互いの合意によって成立
そしてそれはお互いの合意によって成立します。お互いに「このアパートなら」、「この人なら」という気持ちで契約が成り立ちます。
信頼関係が大切
上記ふたつの特徴からわかるように、賃貸借は信頼関係によって成り立っています。ですから相続において、本人が死亡して他の人に変わっても賃貸借契約は継続するか、ということが問題視されるわけです。
アパートの賃借権も相続される
結論からいえば賃借権、つまりアパートを借りる権利は相続されます。アパートに住んでいる遺族はそのまま住むことができます。
原則的に、相続できないのは亡くなった方だけが持つ権利です。(例えば生活保護受給権など)
賃借権は単にアパートを使える権利ですので、別に他の人が相続しても特に問題はありません。
それに、やはりいきなり住んでいるところを出ていかなくてはならない、というのは大変ですからね。
しかし、もし新しい借主が家賃を払えないならば、それはそのときに契約解除の問題となります。
契約内容によっては賃借権が相続されないこともある
しかし、契約内容によっては、賃借権が相続されないこともあります。
たとえば高齢の方の賃貸の場合、契約が「借りている人が死ぬまで」という条件付きの内容で締結されていることがあるのです。
こういった場合は、死亡によって契約が終了してしまいますので、不安な方は賃貸借契約の内容を確認してみることは必要でしょう。
アパートの賃借権を相続する流れ
それでは賃借権は相続されるとして、それはどのように相続されていくのでしょうか。
この章では賃借権の相続が起こった際の流れを見ていきます。
- 指定がなければいったん共有状態となる
- 相続人全員が賃料を支払う義務を負う
- 遺産分割協議で誰が新たな賃借人かを決める
指定がなければいったん共有状態となる
特に誰がアパートの賃借人となるか遺言などで指定がなければ、相続人間で遺産共有している状態になります。
遺産共有は相続人の協議が確定すれば解消されます。
相続人全員が賃料を支払う義務を負う
遺産共有中の賃料は連帯債務とみなされます。したがって賃料を請求された人が全額を請求された場合、その全額を支払うことになります。
連帯債務ですので賃料を支払った(立替えた)相続人は、他の相続人に対しそれぞれ法定の相続分の範囲で自分に賃料分の財産を支払うことを請求することができます。
遺産分割協議で誰が新たな賃借人かを決める
特に指定がなければ話し合いでアパートの賃借人を決めることになります。現実的には、一緒に暮らしている相続人が相続することになるでしょう。
なお、基本的にはアパートの賃借権は当然に相続されるため、もし誰もアパートの賃借人になりたい人がいなければアパートの解約手続きをしなければなりません。
また、内縁の配偶者は相続人でないため、アパートの賃借権を相続することはできません。内縁の配偶者がどうするべきかについては、記事後半で解説します。
賃借人が亡くなった後の家賃は誰が負担する?
さて、賃借人が亡くなった後の家賃は、誰が負担するのでしょうか?
アパートの賃借権における相続に関して非常に厄介な問題として、賃料の発生時期によってその賃料をどうやって負担するのかが変わってしまうということがあります。
相続開始前に賃料が発生した場合と、相続開始後に賃料が発生した場合について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続開始前に発生した賃料
相続の前に賃料が発生していた場合は、その賃料は相続人間で当然に分割されるとされています。
たとえば、亡くなる前の日に賃料の支払い日は来ていたけれど故人が支払っていなかったなどという場合です。
またこの際、遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う形で死亡前の家賃を負担する方を定めても、それを賃貸人に対抗できません。
最高裁平成21年3月24日判決 上記遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者(相続債権者)の関与なくされたものであるから、相続債権者にはその効力が及ばないものと解するのが相当であるから、相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには、これに応じなければならず、指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできない。
あくまでも賃貸人は何も知らないのだから、想定できる法定相続分で請求できるようにさせてあげようということです。
逆に賃貸人が、賃料が別の形で相続されたことを知っていてかつ承認したのなら、それは特に問題がありません。
相続開始後に発生した賃料
相続開始後に発生した家賃は、遺産ではありません。
遺産とは、死亡時に持っていた財産だからです。
となると、これは賃借人が誰か具体的に定められていない間は、今まで書いてきたように全相続人が賃借人となり、連帯債務を負うことになります。
合わせて読みたい:親や配偶者が亡くなったら家賃はどうなる?相続と家賃の関係を行政書士が解説!
借主である「内縁の配偶者」が亡くなったらどうなる?
先述したとおり、内縁の配偶者は相続人でないため、アパートの賃借権を相続することはできません。
合わせて読みたい:内縁の配偶者は相続人になれるのか?その注意点と対策を徹底解説!
そうなると、借主である「内縁の配偶者」が亡くなったらどうなるのでしょうか。内縁の配偶者はアパートを出ないといけないのでしょうか。
実は故人に相続人がいない場合、内縁の配偶者は賃借権を引き継ぐことができます。
内縁の配偶者と言えど、婚姻に準じた関係であることは間違いなく、一方の配偶者に生計を依存していればいきなり追い出されることになれば、少し酷と言えますよね。
また、故人に相続人がいたとしても、内縁の配偶者が簡単に追い出されないように「賃借権を援用する」という立場で住み続けることはできます。判例では以下のように明示されました。
最高裁判所第三小法廷昭和42年2月21日判決 家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではない。
賃借権を相続するわけではありませんが、賃借権を利用できる立場にしてなんとか住居を確保してあげよう、という裁判所の判断がうかがえます。
アパートの賃借権を相続で譲り受けた際の注意点
さて、アパートの賃借権を相続した場合には、普通にアパートを借りたときとは違ってくるポイントがいくつかあります。
- 新しく賃貸借契約がされるわけではない
- 放置していると家賃が発生してしまう
それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。
新しく賃貸借契約がされるわけではない
相続人が賃借人となってアパートにそのまま住むことになっても、前の契約が続いているだけで新しく契約がされたわけではありません。
そうなると、新しい賃借人(アパートを相続した人)がその契約内容を知らず、不測の事態をこうむることもあります。
賃貸人に確認したりして、契約内容を自分で把握するようにした方が無難です。
放置していると家賃が発生してしまう
さきほどもお話しましたが、アパートの賃借権は前の内容で当然に相続されることになります。
そのため、もし借主が亡くなったのを機に引越そうと思っていても、契約を放置しておいたら家賃が発生して、不測の出費になる可能性があります。
もう誰もアパートに住まないということが決まったのなら、契約を解除するか、あるいは特に遺産も欲しいわけではなくご自身だけの問題ならば相続放棄をしてもいいかもしれません。
アパートの賃借権が関係する相続も行政書士に相談できる
賃借権は相続されます。けれども、それにまつわる独特の問題が存在します。
- 賃貸借契約の内容はなにか
- 誰が家賃を払うことになるのか
- その家賃は故人の死亡前に発生したか、死亡後に発生したか
ということを把握して、動いていかなければなりません。
また、実際には「アパートの賃借権」以外の財産についても相続手続を進める必要があるため、非常に手間がかかります。
もしアパートの借主が亡くなり、その相続手続にお困りの場合は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。相続手続全般をお任せいただけるため、負担なく日常に戻ることができます。初回相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。