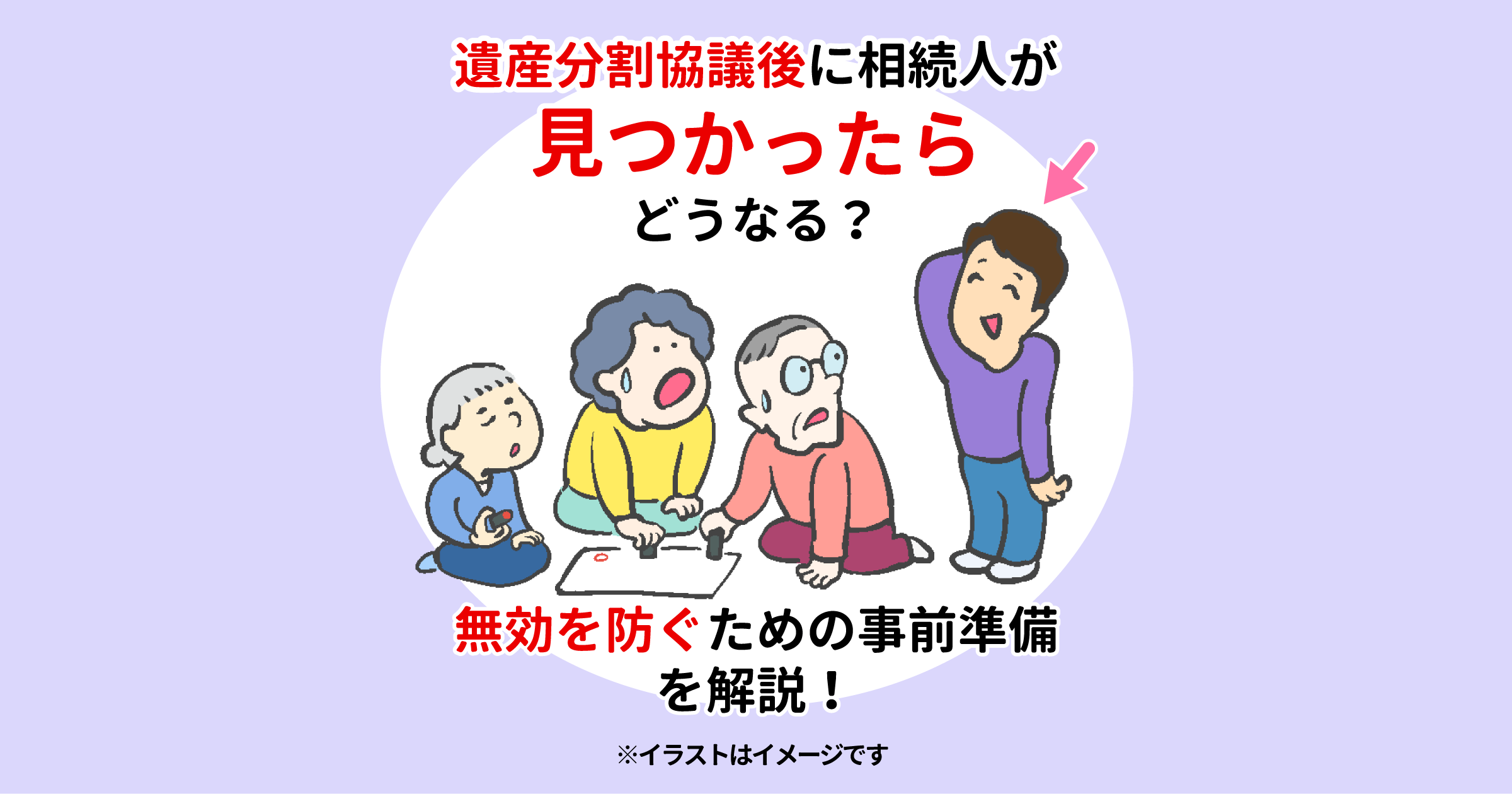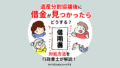遺産分割協議は、被相続人の遺産を相続人間で分け合うための重要な手続きです。
しかし専門家が関与せずに手続を進めた場合、協議が完了した後に「実は相続人がもう一人いた」と判明することもあります。
もし遺産分割協議後に新たに相続人が見つかった場合、当初の協議は無効となってしまいます。
そこで今回は、遺産分割協議後に相続人が見つかったらどうなるのかや、無効を防ぐために必要な事前準備について解説します。
遺産分割協議後に新たな相続人が見つかったら?
民法では、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要とされています。一人でも協議に参加していない相続人がいた場合、その協議は原則として無効です。
具体的には、次のような対応が必要になります。
【再協議の実施】
全相続人を含めて再度協議を行い、新たな協議書を作成する必要があります。
【同意による当初の協議内容の維持】
新たな相続人が既存の協議内容に同意した場合、文書でその意思を明確にすれば、従前の協議書を維持することも可能です。
【家庭裁判所での調停・審判】
再協議が難航した場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる方法もあります。
そのため、スムーズに相続手続を進めるためには、「遺産分割協議後に相続人が見つかった」という事態を防がなければなりません。
そのためには相続手続きを始める前に、「誰が相続人か」を確実に把握することが極めて重要です。
相続人の不参加による遺産分割協議の無効を防ぐポイント
相続人の不参加による遺産分割協議の無効を防ぐポイントとしては、次の3点が挙げられます。
- 遺言書の有無を確認する
- 戸籍調査を確実に行う
- 行政書士などの専門家に相談する
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合、その内容を優先して相続手続を進めます。
遺言書の内容によっては、遺産分割協議が不要ないし限定されることがあるのです。
そのため相続が開始されたら(誰かがお亡くなりになったら)、まず遺言書の有無を確認します。遺言書を探すポイントは次のとおりです。
- 自筆証書遺言:自宅・金庫・信託銀行などを調査
- 公正証書遺言:公証役場での検索や家族に確認
- 法務局の遺言保管制度の有無も確認
参考:遺言書とは?相続手続における効力や注意点を行政書士が解説!
戸籍調査を確実に行う
もし遺言書がなければ、遺産分割協議に沿って相続手続を進めます。
そして先述したとおり、遺産分割協議は相続人全員が合意して初めて有効となります。
つまり、まずは「相続人全員」を把握する必要があるのです。
相続人を正確に把握するためには、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、相続関係を確認する必要があります。特に注意が必要な点は以下の通りです。
- 除籍謄本や改製原戸籍も取得し、抜けや見落としを防ぐ
- 婚外子や認知された子、養子縁組の履歴も確認
- 戸籍の内容を正確に読み解くための知識が必要
参考:相続人はどう確定する?調査方法や広域交付制度の活用方法を行政書士が紹介!
行政書士などの専門家に相談する
過去の戸籍には難解な表記や古い形式の記載もあり、読むのに苦労することもあるため、読み間違いなどの誤解を招く恐れがあります。そのため戸籍を集めてみたものの、相続人が誰なのか判断できないということもあるのです。
このため相続手続は、戸籍の取得手続きや読み解きに慣れている行政書士など専門家へのご依頼をおススメします。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続人調査はもちろん、相続財産調査、遺産分割協議などに対応しております。
提携税理士などとタッグを組んで手続を進めるため、ご相談者様に負担をかけることなく相続手続を完了できることが特徴です。
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
相続人調査や遺産分割協議書の作成は行政書士に相談!
相続人の調査は、遺産分割協議の最も基本であり、最も重要な工程です。「まさか相続人が他にもいるなんて…」という事態は、誰にでも起こり得ます。そうしたリスクを防ぐためには、戸籍を正確に調査し、可能であれば専門家の協力を得ることが重要です。
横浜市の長岡行政書士事務所は、これまでに多くの相続手続をサポートしてまいりました。もし相続手続の進め方が分からず困っている場合は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。