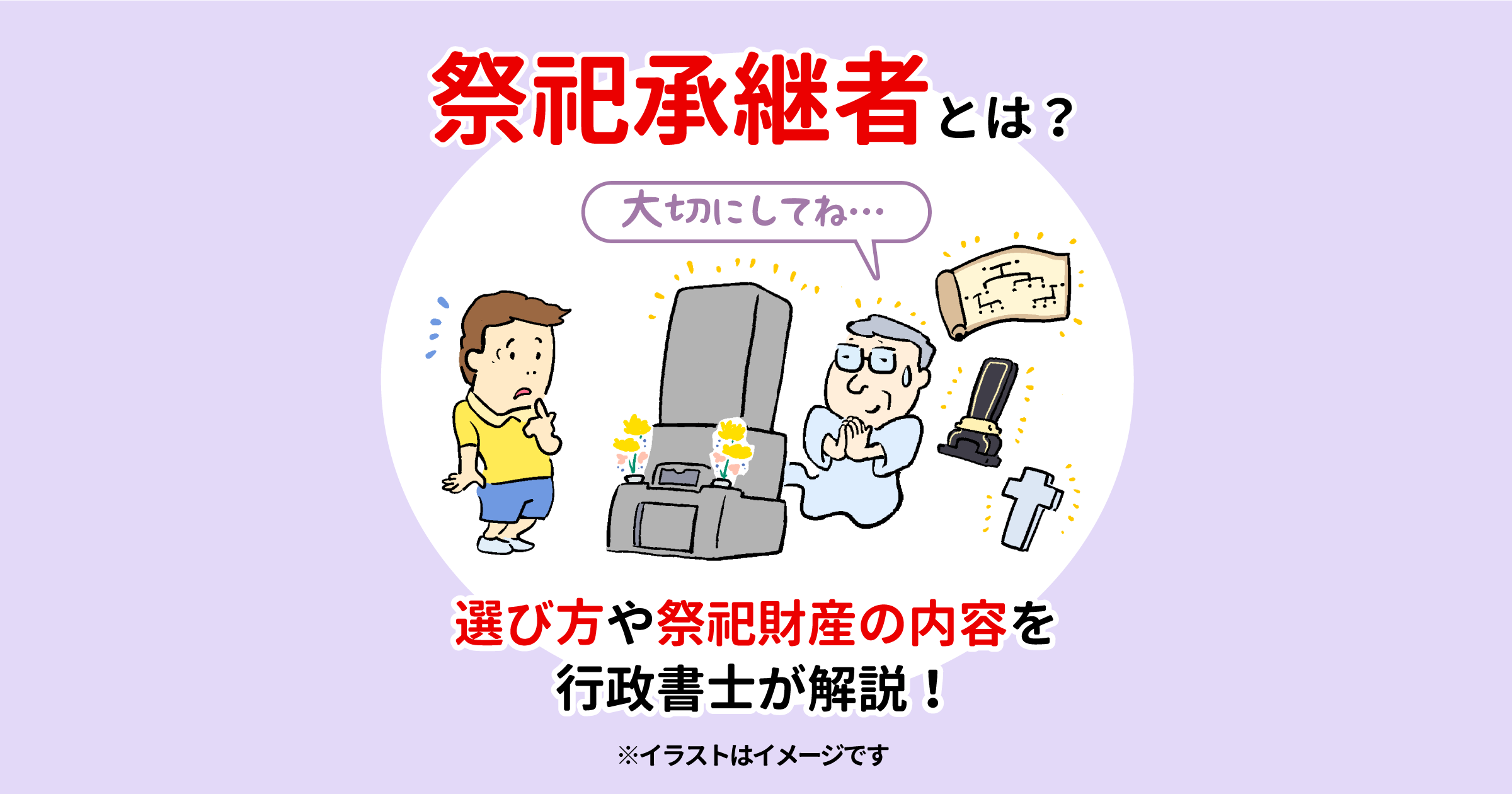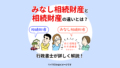「相続手続に伴って”祭祀承継者”という言葉を耳にしたけど、どのような人を意味するの?」
「実家にあるお墓や仏壇は、誰が相続すればいいのだろう」
「お墓や仏壇の相続時の注意点を知りたい!」
祭祀承継者とは、お墓や仏壇などの祭祀財産を承継する人を意味します。祖先からの大切な祭祀にまつわるものを守っていくためには、適切に管理できる人を決める必要があります。
そこで、この記事では祭祀承継者の決め方や役割、承継する財産について、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が解説します!
祭祀承継者とは
祭祀承継者とは、ご先祖から大切に伝わってきたお墓や仏壇など、慰霊や神事・仏事の祀りに関する物を守る人を意味します。
日本では広く仏教が浸透しており、ご家庭に仏壇を祀っている方が多く、亡くなられた後は仏壇に祀られ、遺骨はお墓に入ることが一般的です。(お葬式は神道で執り行うものの、お家に仏壇があるという家庭もありますね)
また、どのような宗教を信仰しているとしても、とくにお墓(墳墓)ご親族が葬られているものであり、大切に管理されていく必要があります。
簡単にいえば、仏壇・お墓を承継する方=祭祀承継者ということです。
祭祀財産とは
祭祀承継者が大切に守り、承継していく財産のことを「祭祀財産」と言います。
祭祀財産は特定の宗教に偏らず、さまざまな宗教や地域の慣習、文化などを反映したものが含まれます。
祭祀財産が民法でどのように規定されているのか見てみましょう。
民法897条第1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
祭祀承継者は民法で、系譜・祭具・墳墓の3つを挙げているのです。なお、宗教・信仰・地域文化などにまつわるものはすべて祭祀財産に含まれます。仏教だけではなく、神事やキリスト教など、他宗教の祭祀にまつわるものも祭祀財産ということです。
| 系譜 | 祖先から伝わる血縁関係が示されたもの 家系図、家系譜など |
| 祭具 | 仏壇や位牌、仏像など 神具やキリスト像、十字架なども含む |
| 墳墓 | 遺体や遺骨を葬る施設のこと お墓やお墓が設置されている墓地など |
祭祀財産は遺産分割の対象にならない
祭祀財産をこれまで管理していた家族が亡くなられた後に、「お墓・仏壇を誰が管理するのか」話し合う機会が持たれるかもしれません。
家族が亡くなったあとに親族で話し合うとなると、遺産分割協議を思い浮かべる方もいるでしょう。
関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!
しかし実は、祭祀財産は一般的な相続財産(預貯金や不動産など)とは明確に分けられており、遺産分割の対象にはなりません。
そのため、遺産分割協議で誰が祭祀財産を相続(承継)するのか争う必要はなく、たとえ祭祀承継者になってお墓・仏壇を引き継ぐとしても、それを理由に預貯金などを相続する割合が減ってしまうこともないのです。
なお、祭祀財産は相続財産ではないため、原則として相続税の対象ではありません。しかし、あまりにも高額の仏具や広大な墓地がある場合、課税対象となるおそれがあります。常識の範囲内でのご購入がおすすめされるでしょう。
祭祀承継者の決め方
さて、祭祀財産は遺産分割協議の対象にならないとしたら、いったいどのように祭祀財産を引き継ぐ方を決めるのでしょうか。
実は祭祀承継者の決め方は、民法で定められています。
民法897条
第1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
祭祀承継者の決め方としては、3通りの方法が挙げられていますね。
- 被相続人が指定する
- 慣習に従う
- 家庭裁判所で決める
| ①被相続人が指定する | 遺言書や口頭、書面などで祭祀承継者になってほしい人を被相続人が指定する |
| ②慣習に従う | 地域やその家ごとのしきたりに沿って決めることができる (例・〇〇家の長男) |
| ③家庭裁判所で決める | 審判を申立て、誰が適任か決めてもらう |
祭祀承継者を被相続人が指名していなかった場合は、「慣習に従う」ことになります。基本的には慣習に従い、長男・長女の方が祭祀承継者となるケースが多いです。しかし、たとえば長男が結婚・就職などを理由に遠くに暮らしている場合は、これまでの慣習に従うことも難しいでしょう。
このような場合、親族の誰が祭祀財産を承継しても、まったく問題はありません。
親族間で祭祀財産を今後どのように扱うのか話し合い、たとえ慣習にそぐわなくても親族が納得していれば、誰が祭祀承継者になっても構わないのです。
祭祀承継者になりたくない場合の対処方法
もしこれまでの祭祀にまつわる行事が、親族の重い負担となっている場合は、あえて自分が祭祀承継者になることで「負担を減らす」方向へ舵を切ることも可能です。
しかし、そうはいっても、祭祀承継者は法事や神事などを仕切る立場の人です。祭祀財産は親族だけではなく、地域に根差しているケースもあります。(地域の祭りに関する神具を預かっている、など)
また、維持や管理に関してはその地域や慣習に沿って適切に行う必要があり、負担感を覚える人もいるでしょう。他の方の意向を無視できない、管理や維持に費用が掛かるといったデメリットもあります。
そのため「祭祀承継者になりたくない」と思う方もいるでしょう。
しかし、祭祀財産が相続財産ではない以上、「相続放棄」によって祭祀財産を放棄することもできません。相続放棄をした後も、祭祀承継者になった方は管理や祭祀を主宰する必要があります。
では、もし祭祀承継者になりたくなかったら、どうすればいいのでしょうか。祭祀承継者になることを断ることはできるでしょうか。
実は被相続人から祭祀承継者に指名された場合、法律上の辞退はできません。
しかし、祭祀財産は相続財産ではないため、たとえ祭祀承継者が処分してしまっても、相続手続きや相続人への影響はありません。
ただし伝統的に受け継がれたものを処分することは、祭祀承継者にとって大きなプレッシャーになるため、役割を放棄したい・財産を処分したい場合にはあらかじめ親族間で話し合いを重ねることが大切です。
なお、祭祀財産は法律的には自由に処分できますが、現実的に仏壇やお墓などを処分することはなかなか難しいものです。では、処分したい場合にはどうすればよいでしょうか。主な方法は以下のとおりです。
墓じまい
墳墓(お墓)の管理が難しくなったら、墓じまいをすることができます。お寺、霊園や墓地管理者など、墓地の管理者に相談しながら撤去をすることになります。撤去費には費用が必要です。また、納骨先をどこに変更するか、選定しておきましょう。
墓石の処分をする場合、墓石ごと引っ越しをすることもできます。この手続きは改葬と呼ばれており、立地や中に入っている遺骨の数によっても相場が変動しています。改葬には見積もりから移送、設置まで時間を要することも多いため、早めに検討することがおすすめです。
なお、改葬をする際は改葬許可申請というものを墓石のある市町村役場にする必要があり、改葬許可証が発行されれば、お墓を異動することができるようになります。
横浜市の長岡行政書士事務所では墓じまいについても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
参考記事:お墓じまいとは?改葬方法や相続に併せた手続について行政書士が解説!
仏壇処分ができる人に依頼する
仏壇・仏具の処分は、菩提寺に依頼をしたり、仏壇・仏具の専門店に依頼する方法があります。また、遺品整理業者なども仏壇処分に対応していることがあります。
閉眼供養や魂抜きなど、ご先祖の魂を供養した上で処分することが一般的ですが、宗派によって対応は異なります。また、神棚やキリスト像などの処分も宗教が異なるため、神具などの専門店に相談してみることがおすすめです。
祭祀の承継に悩んだときも行政書士へ相談できる
この記事では祭祀承継者について、承継者の選び方や祭祀財産の処分方法についても詳しく解説しました。
祭祀承継者は相続人とは分けて考える必要があり、相続開始前からご家族の間で話し合いを重ねておくことがおすすめです。
長岡行政書士事務所では、横浜市を中心に墓じまいや遺言書など、相続にまつわるご相談に広く対応しています。初回相談は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。