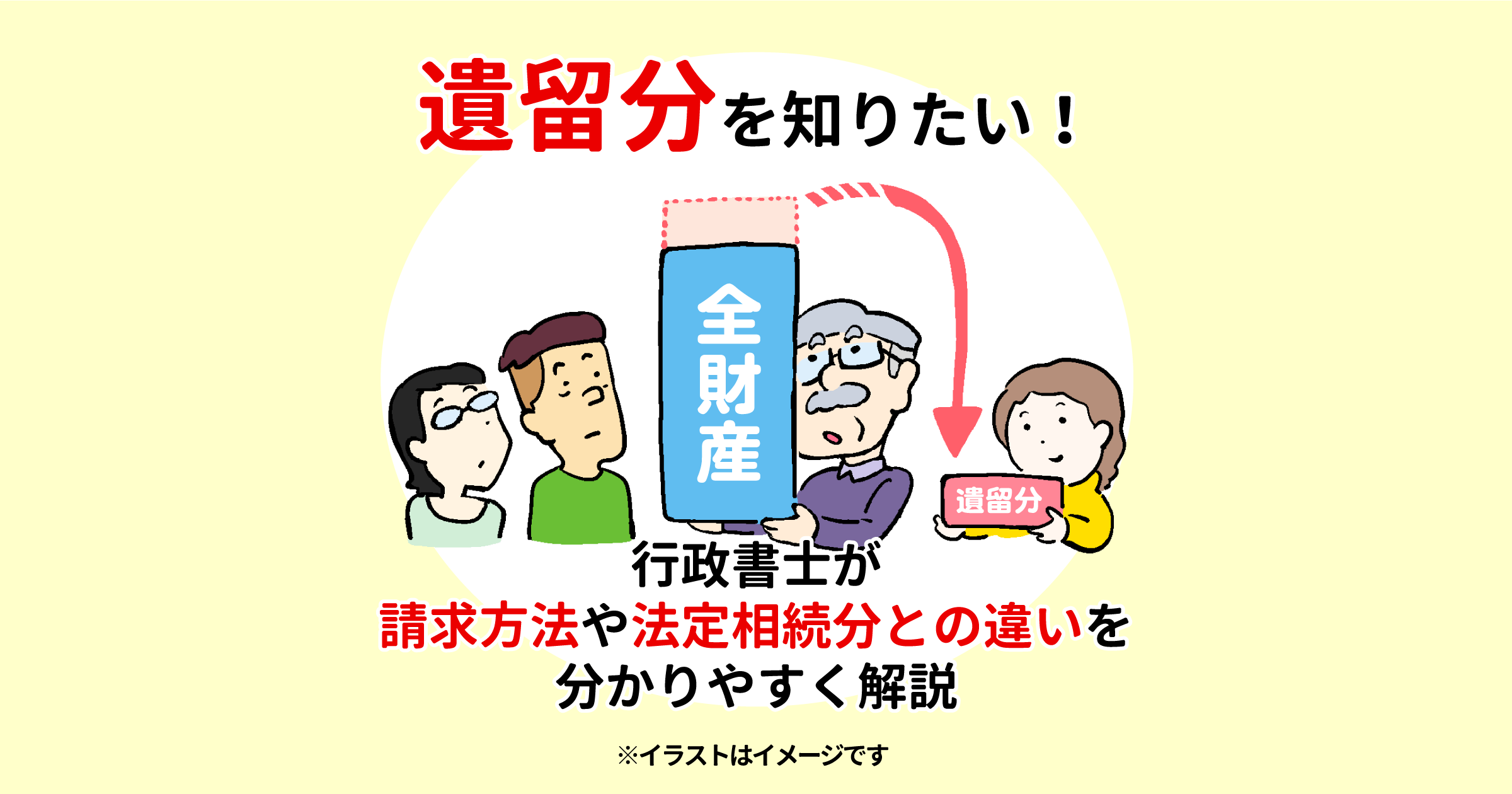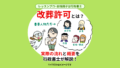「遺留分という言葉を耳にしたけど、結局どういうものなの?」
「遺留分がもらえる範囲をきちんと知っておきたい」
「遺留分と法定相続分ってどう違うの?請求はどうすればよい?」
相続人のために、最低限もらえる財産の割合が保障されていることを「遺留分」と言います。遺留分は法定相続分とは異なっているため注意が必要です。
そこで、本記事では遺留分について、割合や法定相続分との違いを行政書士がわかりやすく解説します!
遺留分とは
遺留分とは亡くなられた被相続人の財産で、兄弟姉妹を除く相続人がもらえる最低限度の割合を意味します。
民法で定められているもので、もしも自分にはまったく財産を渡さない内容の遺言書が残されていた場合でも、遺留分を主張すれば遺産の一部をもらうことが可能です。
たとえば、相続人が子2名の相続で、遺言書に一方の子にすべての財産をわたす、と書かれているとします。もらえなかった子は「どうしてもらえなかったの?」と納得できないのではないでしょうか。
しかし、子には遺留分が認められているためすべての財産をもらう子に、もらえなかった子が「遺留分を渡してほしい」と請求することが可能です。
なぜ遺留分という制度があるのか、疑問に感じる方もいるかもしれません。実は遺留分が定められている理由は、相続人を守るためなのです。
遺言書の内容によっては「財産がまったくもらえない相続人」が発生する可能性があります。
たとえば、専業主婦の配偶者が夫を亡くしたら、夫の遺した相続財産は今後の生活に欠かせないものでしょう。しかし、遺言書で全ての財産を別の相続人(もしくは愛人・指示している団体など)にわたす、と書かれていたら生活が困窮してしまうおそれがあります。
そこで、遺留分を主張すれば最低限の財産はもらえるようなしくみにしてあるのです。遺留分は相続人にとって「生活のセーフティーネット」とも言えるでしょう。
遺留分の割合
そもそも遺留分がもらえる方は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
そして遺留分の割合は、「遺留分を算定するための財産の2分の1、もしくは3分の1」と定められています。
遺留分を算定するための財産とは、いわゆる相続財産のことです。(より詳しくいうと、故人が亡くなったときの財産に、生前贈与した財産を加えた額から、債務を差し引いた額のことです)
この遺産額に、下記の割合をかけたものが、「遺留分」となります。
- 配偶者・子や孫(直系卑属)が相続人になる場合、遺産の2分の1が遺留分
- 親・祖父母(直系尊属)のみが相続人の場合、遺産の3分の1が遺留分
- 兄弟姉妹はなし
上記の遺留分全体を、法定相続分に応じて、各相続人が分け合うことになります。
遺留分と法定相続分の違い
法定相続分という用語が出てきて、混乱している方もいるかもしれません。
そこでここからは、遺留分と法定相続分の違いについて解説します。
法定相続分とは、民法で定められた「遺産を相続する割合」のことです
遺産分割協議で分け方を決めるための目安であり、強制力はありません。
| 法定相続人の構成 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者&子や孫 (直系卑属) | 配偶者:2分の1子や孫:2分の1 |
| 配偶者&親や祖父母(直系尊属) | 配偶者:3分の2親や祖父母:3分の1 |
| 配偶者&兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3兄弟姉妹:4分の1 |
一方で「遺留分」とは、遺産を受け取れる最低限の権利のことです。遺言・生前贈与などで一部の人(もしくは他人)に多くの遺産が譲られてしまった場合に、これを相続人が取り戻すために使われます。
先述したとおり、「相続人全体としていくらの遺留分があるのか」は、民法で定められています。その全体の遺留分に、それぞれの法定相続分をかけることで、各相続人の取り分を決めるということです。
遺留分の計算方法
それでは遺留分をどのように計算するのか、相続人の状況別に見てみましょう。
| 相続人の状況 | 全体の遺留分割合 | 各相続人の遺留分割合 (全体の遺留分割合×個人の法定相続分) |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 |
| 配偶者と子ども1人 | 2分の1 | 配偶者:4分の1 子:4分の1 |
| 配偶者と両親 | 2分の1 | 配偶者:6分の2 両親:6分の1(一人あたり12分の1) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |
| 子や孫のみ(直系卑属) | 2分の1 | 子の数に応じて按分 |
| 父母のみ | 3分の1 | 3分の1(一人あたり6分の1) |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |
遺留分に関連して起きやすいトラブルとは
遺留分は相続時にトラブルとなるケースも多く、遺言書の作成や遺産分割協議時には注意する必要があります。そこで、この章ではよくある遺留分に関連したトラブルを紹介します。
遺言書によるトラブル
遺言書は遺留分に配慮しない内容で作ることができます。たとえば、生前にお世話になった介護施設や、国際的なボランティア団体に遺言書を使って遺贈することも可能です。
しかし、遺留分が侵害される内容だった場合、相続人は「遺留分を渡してほしい」と請求できます。遺贈先によっては遺留分の請求が重い負担となるおそれがあるため、慎重に遺言内容を検討する必要があるでしょう。
合わせて読みたい:遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説
遺産分割協議によるトラブル
遺産分割協議に参加していると、自分の遺留分を別の相続人に請求したいと考える方もいるでしょう。しかし、遺産分割協議と遺留分は別の制度です。
遺留分は遺言や遺贈、生前贈与に対して請求する権利のため、遺産分割協議の中で遺留分を求めることはできません。
合わせて読みたい:遺産分割協議後に問題があった場合とは?一方的に解除ができるのかを行政書士が解説!
相続放棄によるトラブル
生前に被相続人に借金があった場合や、特定の相続人に財産を集中させたい場合などの事情がある場合「相続放棄」をする方がいます。相続放棄をしてしまうと、はじめからその相続人がいなかったことになるため、相続放棄後に遺留分をもらうことはできません。
相続放棄をする際にも、慎重に検討する必要があります。
合わせて読みたい:相続放棄と遺産分割協議書上の放棄は違う!よくある勘違いを行政書士が解説
遺留分の請求方法とは
自身の遺留分がもらえないとわかったら「遺留分の請求」を検討しましょう。遺留分の請求は、以下の方法が考えられます。
- 多く財産を取得した方(遺留分を侵害した方)に話し合いを求める
- 交渉が不成立の場合は調停や訴訟
では以下見ていきましょう。
多く財産を取得した方(遺留分を侵害した方)に話し合いを求める
まずは双方の話し合いを模索します。遺留分の請求には時効があり「相続の開始と、侵害の事実を知った日から1年」とされるため、早期の交渉開始が大切です。
請求者側から支払って欲しい相続人に対して内容証明郵便を送り、交渉を求めます。内容証明郵便を使用する理由は、請求日や請求の事実を調停、訴訟時の証拠として使用できるためです。
合わせて読みたい:遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!
交渉が不成立の場合は調停や訴訟
遺留分が話し合いで解決できない場合、裁判所で解決を求めることが可能です。調停で話し合いを重ねても不成立だった場合に「遺留分侵害額請求訴訟」をします。
調停は家庭裁判所ですが、訴訟は140万円以下の金額を争う場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所で行います。
遺留分は放棄できる?
遺留分は生前に放棄することができるのでしょうか。
結論から言うと、家庭裁判所で一定の手続きを行えば放棄できます。
なお、遺留分の放棄は相続放棄とは異なるため、もしも相続の開始後に被相続人に借金があり放棄したい場合は、相続放棄も行う必要があります。詳しくは以下リンクをご確認ください。
参考URL 裁判所 遺留分放棄の許可
合わせて読みたい:生前に相続放棄はできるのか?生前からできる代替策も行政書士が解説!
遺留分放棄は相続放棄と比較すると、あまり耳慣れた手続きではないでしょう。では、実際にはどのような場面で行われているでしょうか。主な例は以下です。
- 家族が書いた遺言書の内容をあらかじめ聞いており、事業継承などを目的に特定の方に財産を集中させたい場合、財産をもらわない方が遺留分を放棄する
- 今後相続放棄を予定しており、遺留分もあらかじめ放棄しておくことで家族と距離を保ちたい時
遺留分は放棄してしまうと、原則として取消はできません。事情があり取消をしたい場合は家庭裁判所に認めてもらう必要があります。そのため、慎重に検討することが望ましいでしょう。
遺留分は大切な権利です|トラブル防止のためにも割合は知っておきましょう
本記事では遺留分について、請求方法や法定相続分との違いも交えながら詳しく解説しました。遺留分は大切な財産をもらうための権利です。もしも侵害されていたら請求できるため、この機会に割合について知っておきましょう。
また、相続放棄は生前にできませんが、遺留分については放棄ができます。一度放棄してしまうと原則として取消はできないため慎重に判断しましょう。
遺留分や相続でお悩みの方は、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。