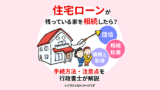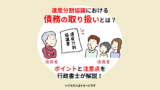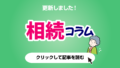亡くなられたご家族に謝金などのマイナスの財産があるとき、相続において困ってしまいますよね。
マイナス財産の相続を避けたい場合は、「相続放棄」が選択肢になりますが、実は遺産分割協議書上の放棄(遺産放棄・財産放棄)という別の制度があることをご存知でしょうか。
今回は遺産分割協議上で放棄するという手段について、詳しく紹介します。
(なお、難しい法律の話を分かりやすくお伝えするために、報道ニュース風の小噺でお伝えいたします)
遺産分割協議書上の放棄(遺産放棄・財産放棄)とは
遺産分割協議上の放棄(遺産放棄・財産放棄)とは、遺産分割協議の中で、「私は被相続人の財産を相続しない」と宣言することです。
また、遺産分割協議書を経て、複数の相続人のうち一人が財産を全部相続する場合、つまり自分以外の相続人が財産を全部相続することに同意するのも「遺産分割協議上の放棄」に当たります。
これは裁判所での手続を経て、被相続人が所有していたプラス・マイナスの財産すべてを放棄する「相続放棄」とは全く別の制度です。
そんな遺産分割協議上の放棄(遺産放棄・財産放棄)をするうえで知っておきたいポイントとしては、次の3つが挙げられます。
- 裁判所の介入がない
- 完全に債務を放棄できるわけではない
- 法的な手続期限はない
裁判所の介入がない
- 相続放棄⇒相続財産の放棄を裁判所に認めてもらうための手続き
- 遺産分割協議上の放棄⇒相続人間で話し合って成立を目指すもの(裁判所は介入しない)
完全に債務を放棄できるわけではない
- 相続放棄⇒債務の放棄が可能
- 遺産分割協議上の放棄⇒債権者は相続放棄をしていない相続人に返済を請求可能
法的な手続期限はない
- 相続放棄⇒原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要がある
- 遺産分割協議上の放棄⇒相続税などの納付期限には配慮が必要だが、法的な期限はない
借金がある場合の「遺産分割協議書上の放棄」は要注意
皆様、こんばんは。社会の構図をわかりやすくお届けするニュース番組「報道小路」のお時間です。アナウンサーの西園寺遺子です。
この西園寺がさまざまな現場を徹底的に取材しており、この合成皮の手帳、通称、白革の手帳にまとめておりますのでご期待ください。
本日の特集は「遺産分割協議書上の放棄(遺産放棄・財産放棄)」についてです。
「亡くなった親に借金があったのだが、『相続放棄』と『遺産分割協議上の放棄』のどちらで手続を進めるべき?」というようなご相談は当番組にも多く寄せられますので、興味深いですね。
本日はコメンテーターとして、シンガーソングライターの逢紀真代さんにお越しいただいております。では、早速まいりましょう。いつものセリフでスタートです。
「私、調べましたけど!」
遺子「では真代さん、よろしくお願いいたします。早速ですが、『相続放棄』と『遺産分割協議上の放棄』の違い、ご存じでしたか?」
逢紀「いやあ、全然知らなかったです。」
遺子「まずは相続放棄ですが、これは一切合切を放棄するということですから、相続財産が債務超過のケースなどでよく行われているんですよ」
逢紀「はあ」
遺子「一方で、遺産分割協議上の放棄は、相続人同士で揉めることを避けるために、『私は被相続人の財産を相続しません』と宣言することなんです」
逢紀「うーん、つまり、『遺産分割協議上の放棄』は、あくまでも相続人同士で決めること、ということですかね?」
遺子「そうなんです。そのため相続放棄のように、裁判所の介入を経て完全に債務を放棄できる手続ではないということなんです。たとえば、親が遺した住宅ローンを、子がどうするかという問題はよく聞かれますよね」
逢紀「親が住宅ローンを返済できないうちに他界するわけですね」
関連記事:住宅ローンが残っている家を相続したら?手続方法・注意点を行政書士が解説
遺子「このとき、相続放棄をすれば住宅も相続できませんが、住宅ローンを支払う義務は無くなります。
一方の遺産分割協議はあくまでも相続人間の話し合いですから、『私は財産はいらない』と宣言しても、銀行(債務者)は『いや、そんなの困りますよ』と、相続放棄をしていない相続人に返済を請求できるんです」
逢紀「ということは、相続放棄のほうが効力は強いということなんですね。そうしたらみんな相続放棄を選んだ方が話は早いじゃないですか」
遺子「そう思えますよね。ところが、実は必ずしもそうだとは言い切れないのです」
「相続放棄」と「遺産分割協議書上の放棄」はどう使い分ける?
「遺産を放棄したい」と感じたとき、相続放棄と遺産分割協議上の放棄のどちらを選ぶべきなのか?
それぞれ、おすすめのケースを見ていきましょう。
相続放棄がおすすめのケース
遺子「まず相続放棄をおすすめしたいのは、こちらに当てはまるケースです」
- 高額の借金引き継がされそう…返済なんてムリ!
- 亡くなった人と生前から付き合いが無いので、財産をもらってもどう管理したらいいか…
- 家族の仲が悪いから、遺産分割協議で顔を合わすなんて冗談じゃない!一切関わりたくない!
遺子「相続放棄ができれば、そもそも相続人ではなかったことになります。つまり、遺産分割協議に参加する必要もないんですね。また、借金も含めて、全部を放棄すいるため、債権者から督促状が届いても、「いいえ、相続放棄が完了していますからお支払いの義務はありません」と、督促を受けなくて済むようになります」
(※)相続放棄の完了後、裁判所に依頼すると、相続放棄受理証明書の発行を受けられる(手数料150円)
逢紀「まあ、そうですよね」
遺産分割協議上の放棄がおすすめのケース
遺子「遺産分割協議上の放棄がおすすめされるケースは、こちらですね」
- 別に債務とかはないけど、相続したい財産も特にないんだよね
- 事業継承で特定の相続人に相続財産を集中させたい
- そもそも債務も含めて円滑に遺産分割協議がまとまるし
逢紀「遺産分割協議上の放棄は、債務の負荷がなかったり、あっても相続人皆で平和に話し合える場合に向いているわけですね」
遺子「そうですね。あとは債務があっても家族が暮らす住まいを守りたいときなどに、こちらを選ぶケースがあるようです」
逢紀「わかりやすい…でも私、今日、ほとんどまともにコメントしてない…」
「遺産分割協議上の放棄」のデメリット
遺産分割協議上の放棄を選ぶときには、そのデメリットも知っておかないと、あとで「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。
今後の生活に大きく影響しないよう、特に注意したい2つのデメリットを把握しておきましょう。
- 借金が消えてなくなるわけではない
- 後順位への相続ができない
遺子「でも、遺産分割協議上の放棄には思わぬ落とし穴があるので気を付けていただきたいんですね。では逢紀さん、ご一緒に?」
逢紀「きた、あのフレーズだ!」
遺子「私、調べましたけど!!!」
借金が消えてなくなるわけではない
- 遺産分割協議上の放棄では、被相続人の借金を放棄したことにはならない
- 「相続人を代表してAさんが支払います」と結論づけても、Aさんが債務の返済に行き詰まったら、請求は別の人に及ぶ
- このとき請求が及ぶのは相続放棄をしていない相続人
関連記事:遺産分割協議における債務(借金)の取り扱いとは?記載例や注意点を行政書士が解説!
後順位への相続ができない
- 相続人という立場を放棄したことにはならないので、後順位の相続人は相続はできない
- 後順位の方に相続させたい場合には相続放棄をしたほうがよい
関連記事:相続人の範囲はどこまで?代襲相続・数次相続・再転相続も考慮して行政書士が徹底解説!
遺産放棄・財産放棄するときの遺産分割協議書の作成も行政書士に依頼できる
ここまで紹介したとおり、「相続放棄」と「遺産分割協議書上の放棄(遺産放棄・財産放棄)」は全く別の制度です。
そのため自分がどちらの手続をすべきか分からない場合は、行政書士などの専門家に相談してみてください。
また、遺産分割協議書上の放棄(遺産放棄・財産放棄)をする場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。この書類作成も行政書士へ依頼できますから、やはり一度相談してみるのが安心でしょう。
横浜市の長岡行政書士事務所でも相続手続のご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。