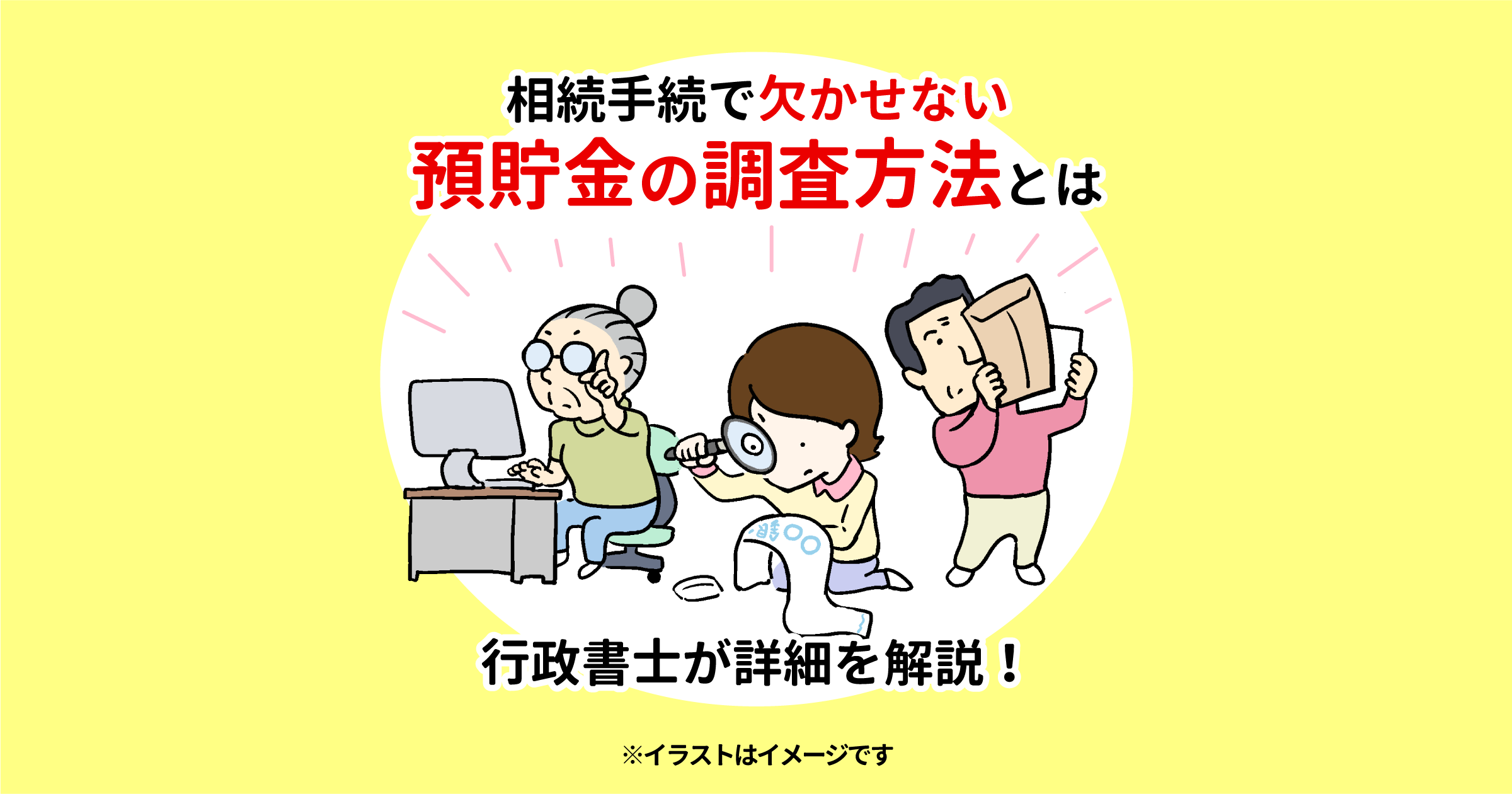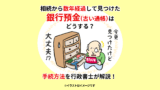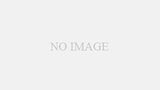「父が亡くなり、相続手続きを進めている。預貯金口座をいくつか持っていたようだけど、どのように調べるの?」
「亡くなった家族の相続財産を調べているけど、知らない預貯金があったらどうしよう」
「預貯金口座の相続財産調査の手続き方法や注意点を知りたい」
ご家族が亡くなられ、相続財産の調査を始める場合、被相続人が有していた財産を特定する必要があります。相続財産にはさまざまな種類がありますが、給与の受取や貯蓄のための定期性預金、公共料金の支払いなどに使う「預貯金口座」は代表的な相続財産の1つです。
しかし故人がどこの銀行で口座を持っていたか、完璧に把握できているとは限りません。
そこでこの記事では、相続手続に欠かせない預貯金の調査方法について、詳細を横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が解決します。
故人の保有する銀行は一括照会できる?
上場株式なら証券保管振替機構(ほふり)を活用すれば一括照会が可能なため、故人の保有する銀行も一括して調査できないか、気になる方もいるでしょう。
実は故人が、預貯金口座にマイナンバーを付番(登録)していた場合には、「相続時預貯金口座照会」という制度を使って、情報を取得することが可能です。
しかし実際には、保有する預貯金口座にマイナンバーが登録されているとは限らないため、この照会制度だけで預貯金口座の調査が完結することはありません。
預貯金口座の調査方法
相続手続のために故人の預貯金口座を調べる方法としては、次の4つが挙げられます。
- 通帳・キャッシュカード
- 銀行名のあるタオルなどの粗品
- アプリ
- 郵便物
それぞれどのようなポイントを重点的にチェックすべきなのか、詳しく見ていきましょう。
通帳・キャッシュカード
まずは被相続人が所有していた、通帳やキャッシュカードを調べてみましょう。財布の中や通帳などの貴重品の保管場所などを探してみてください。
通帳やキャッシュカードが見つかれば、口座のある支店まで分かるため、非常に手続を進めやすいです。
銀行名のあるタオルなどの粗品
銀行の取引があると、景品でタオルやポケットティッシュなどの粗品をもらうことがあります。銀行名のあるグッズがあったら、取引先かもしれませんので問い合わせてみましょう。
アプリ
近年はネットバンキングの利用者も多く、通帳を持たない人も増えています。スマホやパソコンに、ネットバンキング名のアプリがある場合には、取引をしている可能性があります。
また、ネット銀行の場合も通帳がありません。スマホに口座のアプリがある可能性があるため、もしも画面上で確認出来たら、ネット銀行側に問い合わせるようにしましょう。
関連記事:相続時にネット銀行やネット証券の口座はどう見つける?通帳がない場合の調査方法を行政書士が解説!
郵便物
定期性預金の満期など、銀行からは定期的に郵便物が届いていることがあります。
被相続人宛に銀行からの郵便物が保管されている場合は、被相続人名の口座がある可能性が高いため、調査しましょう。過去にネット銀行から届いたはがきに問い合わせたら1000万円近く残高があったことがあります。
預貯金口座の相続手続をスムーズに進めるためのコツ
預貯金口座の相続手続をスムーズに進めるためのコツについても紹介します。
- シェア率の高い地方金融機関も確認する
- 転勤先にある地方銀行なども確認する
- 金融機関からの借り入れ状況も把握する
- 銀行が統廃合されている可能性も考慮する
- 休眠口座となっている可能性も考慮する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
シェア率の高い地方金融機関も確認する
都市銀行だけではなく、各地域ごとにシェア率の高い地方金融機関に口座を保有している可能性も高いです。
そのため念を入れて、通帳などが見つからなくても、シェア率の高い地方金融機関には口座照会しておくと安心です。
たとえば横浜市の方であれば、「横浜銀行」「横浜信金」はチェックしておきたいところです。エリアによっては「川崎信金」「湘南信金」なども調べてみてください。
転勤先にある地方銀行なども確認する
被相続人が過去に転勤や通学などの理由で、今とは違う場所に暮らしていた場合、その地域で使いやすい銀行に口座を開設していることがあります。
相続人にはあまり馴染みのない地方銀行にも、預貯金が残されていることがあるため、心当たりがある場合は調べてみると良いでしょう。
金融機関の借り入れ状況も把握する
相続財産には債務も含まれるため、預貯金口座の調査を進める際には、金融機関から借入の有無も、合わせて確認するようにしましょう。金融機関からの借入には、以下のような種類があります。
- 住宅に関するローン(住宅ローン・リフォームローン・不動産担保ローンなど)
- 車のローン
- 教育ローン
- カードローン など
銀行が統廃合されている可能性も考慮する
銀行は統廃合があり、現在は違う名前となっている場合があります。見つかった通帳やカードが、心当たりがない名前の場合にはインターネットを活用して、現在はどこに統廃合されているのか調べてみましょう。
「一般社団法人 全国銀行協会」にアクセスすると、平成元年以降の提携・合併の歴史がリスト化されています。以下ご参照ください。
参考URL 一般社団法人 全国銀行協会 「最近の銀行の合併を知るには」
休眠口座となっている可能性も考慮する
古い通帳が見つかった場合、現在「休眠口座」となっている可能性があります。休眠口座とは、長期間口座から預金・出金を行わないまま放置している状態の口座を指します。
2018年1月、休眠口座については「休眠預金等活用法」が施行され、2019年1月以降に発生する休眠預金は民間における公益的な活動に活用することになりました。銀行・ゆうちょ銀行における以下の口座は対象となるため、今後の相続時にも注意が必要です。
| 休眠預金の対象となる口座 | 対象にならない口座 |
| 普通預金・貯蓄預貯金・通常預金 | 外貨預貯金 |
| 定期預金・定額預金・定期預貯金 | 仕組預貯金 |
| 当座預金 | 財形貯蓄 |
預貯金口座の相続手続の流れ
それでは預貯金口座を調査したあと、実際に相続する流れについて見ていきましょう。
- 金融機関に相続発生を連絡する
- 必要な書類を確認する
- 払い戻しをうけるか、取引を継続する
金融機関に相続発生を連絡する
まずは口座のある金融機関に、相続が発生したこと、つまり口座所有者が亡くなったことを連絡します。
口座所有者が亡くなったことを知ると、銀行は口座を凍結します。口座凍結後はお金の引出ができなくなるほか、公共料金やスマホ代などの引き落としもできなくなるため注意しなければなりません。
そのため実務的には、ある程度遺産相続の内容が固まってから金融機関に連絡したほうがいいでしょう。
関連記事:口座凍結のタイミングはいつ?相続発生後の死亡届と銀行凍結の関係について行政書士が解説!
必要な書類を確認する
預貯金口座を引き継ぐためには、金融機関側が求める書類用意しなければなりません。
相続手続に必要となる書類は金融機関によっても違いがあり、さらに遺言書で手続するのか、遺産分割協議書によって手続するのかにもよって異なるため、注意しなければなりません。
| 状況 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言書がある | 遺言書 亡くなった方の死亡が分かる戸籍謄本 亡くなった方との関係性が分かる戸籍(受益相続人の場合) 相続する方の印鑑証明書および印鑑 被相続人が使っていた通帳 カード 検認調書もしくは検認済証明書 (必要な場合のみ) 遺言執行者の選任審判書の謄本 (必要な場合のみ) |
| 遺産分割協議書がある | 亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本 相続人全員の印鑑証明書 相続人全員の戸籍謄本 遺産分割協議書 |
| 遺産分割調停・審判を経た | 裁判所が作る調停調書や審判書の謄本 相続する方の印鑑証明書および印鑑 |
| 相続人が1名である | 亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本 相続人の印鑑証明書 相続人の戸籍謄本 |
参考記事:預貯金口座(銀行口座)の相続手続方法を行政書士が解説!
書類集めなどを負担に感じる場合は、相続手続をサポートしている行政書士に相談してみてください。横浜市の長岡行政書士事務所でも、口座の相続手続を代行しています。
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
払い戻しをうけるか、取引を継続する
相続手続に問題がなければ、1〜2週間程度以内に払い戻しされます。
ただし、故人の口座の中には、現在より金利が優れている「定期性預金」があるケースもあります。このような場合は解約して払い戻しを受けるのではなく、口座契約を継続することも可能です。
預貯金口座を見つけた後の注意点
相続手続の実務としては、預貯金口座を見つけた後にも注意すべきことが存在します。
- 口座名義者の死亡を伝えると、口座は凍結される
- 口座を見つけたからといって勝手に引き出してはならない
- 口座が凍結されても「仮払い制度」は活用できる
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
口座名義者の死亡を伝えると、口座は凍結される
金融機関に対して口座名義者が亡くなったことを伝えると、その口座はただちに凍結(入出金が停止)されます。その理由は次のとおりです。
- 不正な引き出しを防ぐ
- 無用な相続トラブルを防ぐ
口座の凍結後は預金の引き出しだけでなく、公共料金などの自動引き落としや、クレジットカードの支払いもすべて停止されます。
また、株式の配当金、不動産の賃料など、入金も受け付けられなくなります。
関連記事:死亡届を提出すると銀行口座は凍結される?行政書士が詳細を解説!
口座を見つけたからといって勝手に引き出してはならない
入院費や葬儀費用を支払うために、「口座が凍結される前に、現金を引き出しておこう」と思う方もいるかもしれません。
しかし他の相続人に無断で、勝手に故人の口座から現金を引き出すと、無用なトラブルの原因となりえます。
なんらかの事情があり、凍結前に現金を引き出したいと考えている場合は、少なくとも全ての相続人から同意を得ておくべきでしょう。
口座が凍結されても「仮払い制度」は活用できる
実は2019年7月から「仮払い制度」が開始されているため、無理に凍結前に現金を引き出す必要はありません。
払い戻し方法には、以下2つがあります。
| 相続人が単独で払い戻しができる額 | |
| 家庭裁判所の判断が不要 | ・同一の金融機関からの払い戻しの上限は150万円 ・相続人単独で払い戻しができる額は預金額×3分の1×相続人の法定相続分 |
| 家庭裁判所の判断が必要 | ・家庭裁判所が取得で認めた額※共同相続人の利益を害さない範囲程度 |
仮払い制度については、下記の記事でも解説しています。
相続時の預貯金払戻し制度とは?遺産分割前に預貯金を引き出す方法・注意点を行政書士が解説!
相続から数年経過してから口座が見つかったらどうする?
相続の実務では、故人が亡くなって数年が経過してから、ようやく口座が見つかったというケースもあります。
このような口座も、凍結解除(相続手続)することは可能です。
10年以上取引がないと休眠預金として扱われ、資金が預金保険機構に移管されることもありますが、口座が消滅するわけではありません。
休眠預金が相続財産であると証明すれば、払い戻しを受けることが可能です。
しかし払い戻し手続が面倒だという場合は、行政書士などの専門家へ手続を依頼してもいいかもしれません。
また、古い銀行口座が見つかると、その預金額によっては相続税申告の修正が必要な可能性があります。この場合は税理士へ相談して、必要な申告手続を進めましょう。
関連記事:相続から数年経過して見つけた銀行預金(古い通帳)はどうする?手続方法を行政書士が解説!
故人の銀行口座の調査・相続手続は行政書士に依頼できる
今回は相続時に触れることが多い被相続人の「預貯金口座」について、相続財産の調査の視点から詳しく解説を行いました。
預貯金口座は身近な銀行だけではなく、今お住まいの地域以外の場所に開設しているケースもあるため、被相続人のライフヒストリーに沿って丁寧に洗い出すことがおすすめです。
しかし口座を見つけたとしても、金融機関ごとに相続手続をしていくのは、なかなか手間のかかる作業です。銀行口座の調査・相続手続を面倒だと感じる方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。
預貯金口座だけではなく、相続手続全般について一貫してサポートいたします。初回相談は無料なので、まずはお打ち合わせをご予約ください。