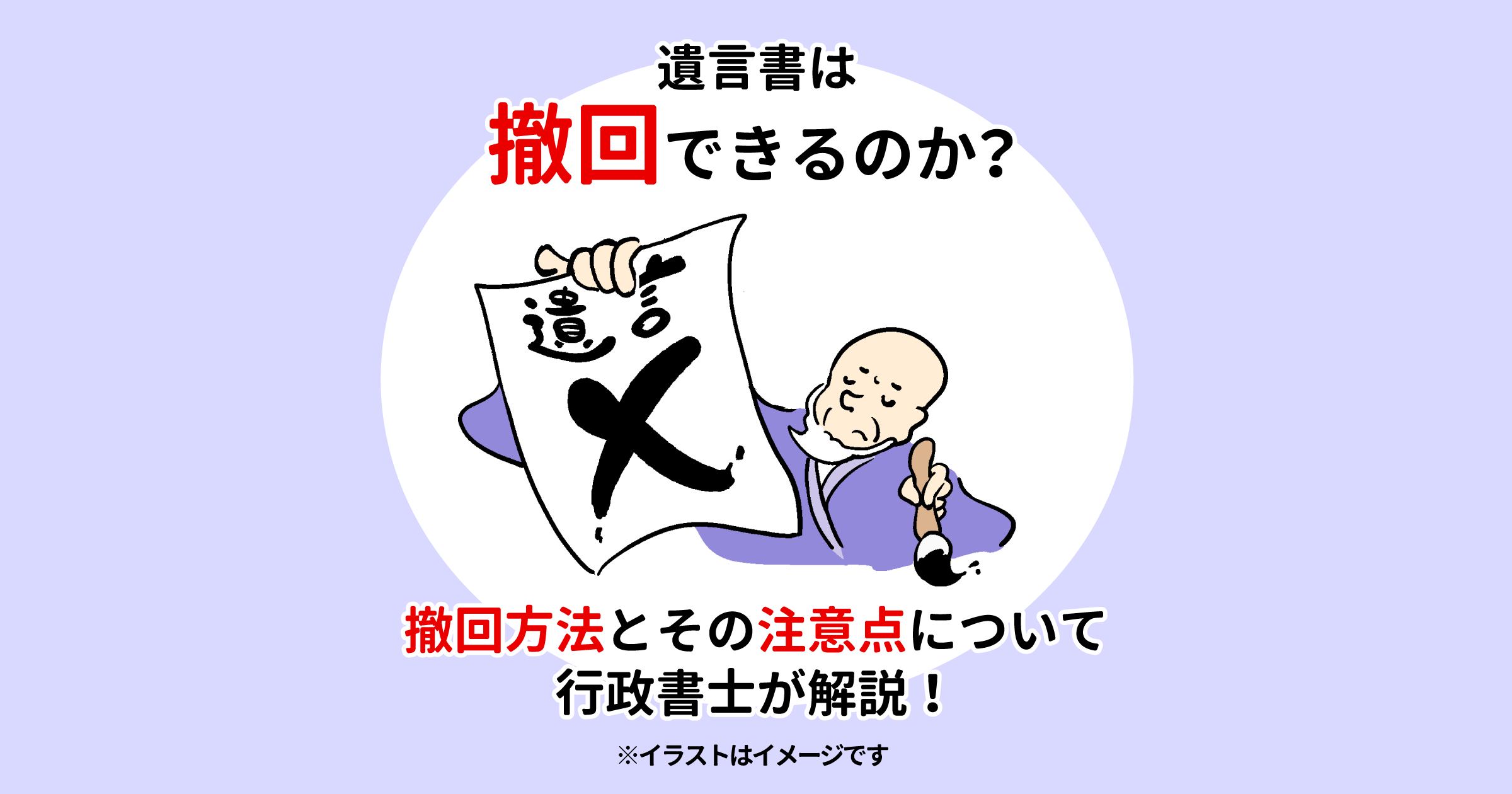「遺言書に記載されている財産がないんですけど、どうやって相続手続を進めたらいいの?」
「遺言の内容に従って相続するのが前提と聞いたけど、書かれている財産がないときはどうする?」
「そもそも遺言書が撤回されることなんてあるの?」
遺言書を見つけて相続手続を開始したものの、書かれている財産が見つからない!ということもあるでしょう。
たとえば遺言書に「A銀行の預貯金は長男に相続させる」とあるものの、故人が生前すべて使ってしまっていた、ということもあります。
「自動車は次男に相続させる」と記載があるのに、故人が生前に売却してしまっていた、ということも珍しくはありません。
これは遺言書が撤回された状態であるといえます。
この記事では、遺言書に記載されている財産がない場合はどう相続手続すればいいのか、詳しく解説していきます。
遺言はいつでも撤回ができる
結論として、遺言は撤回をすることができます。民法にも以下のように書かれています。
民法1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
そもそも遺言というのは、あくまでも個人的な意思表示です。そしてそれは亡くなったあとのことを念頭に作成されるものです。
亡くなる前に事情が変われば、遺言内容も変更するのは当たり前のことでしょう。
ですからいつでも撤回できるというのも非常に納得できると思います。
また、遺言に関しては全部または一部を撤回することができるとされています。
つまり、遺言をすべて作り直すこともできるし、一部だけ(たとえば、土地の相続人だけを変えたり)ということも可能です。
また、何度でも遺言を作り直すことは可能です。
そして、遺言書の種類によって撤回方法が異なります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
それぞれの撤回方法を見ていきましょう。
自筆証書遺言の撤回方法
自筆証書遺言とは、故人が自分で作成する遺言書です。パソコンなどで文章を作成することは認められておらず、自分の手で書く必要があります(財産目録などの部分はパソコンなどで作成することが認められるようになりました)
合わせて読みたい:2018年(平成30年)の遺言・相続の法改正!施行によるの各制度の取り扱いについて解説
すぐに作れたり、費用がかからないなどが自筆証書遺言のメリットです。基本的に自分で保管するものですが、法務局で保管してもらうこともできます。
しかし、遺言には法的に定められた形式があるため、自筆証書遺言を作成してもそれが無効になることもありますので、注意が必要です。
合わせて読みたい:自筆証書遺言とは|効力やその他の遺言書との違いを行政書士が解説!
そんな自筆証書遺言の撤回方法は、大きく分けて二種類あります。
自分で保管している場合:その遺言を破棄すればそれで撤回となる。
法務局で保管してもらっている場合:撤回書を法務局に提出し、返してもらった遺言を破棄すれば撤回となる。
基本的には自筆証書遺言は自分で任意に作成したものであるため、自分で破棄すればそれで遺言は撤回されます。
法務局に預けている場合は、撤回書だけでは遺言を撤回したことにはならず、返してもらったものを自分で破棄しなければならないことに注意しましょう。
合わせて読みたい:自筆証書遺言書保管制度はすべき?法務局へ保管するメリット・デメリットを解説!
また、新しい遺言を作成すれば古い遺言は撤回されたことになります。
公正証書遺言の撤回方法
公正証書遺言とは、公証人という法律のプロが作成してくれる遺言書です。遺言者、公証人のほか、証人が2人立ち会って、それぞれが署名と押印をすることにより、遺言が完成します。
公証人が作成している分、文書の信用性が高く、かつ形式的にも無効になりにくい遺言になります。
また、公証役場という公証人が働いている事務所で一定期間遺言が保管されるため、紛失した際にも安心です。
デメリットとしては、公証役場への費用が発生することでしょう。
合わせて読みたい:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介
公正証書遺言を撤回する場合には、再び公証役場に行って、遺言を作成したときのように、遺言を撤回する本人、公証人、ふたりの証人で遺言を撤回する旨を述べて、それぞれ署名押印することによって遺言が撤回されることになります。
つまり遺言を撤回する旨の遺言書を作るということです。
また、前回作った遺言を撤回する旨の記載をして、新しく遺言を作成するという方法もあります。
どちらも再度手数料がかかるので、注意しましょう。
遺言の撤回とみなされる行為
上記の遺言の撤回方法でも触れたように、「新しい遺言を作成すると古い遺言は撤回されたとみなされる」というような、「ある行為をすると撤回とみなされる」行為は他にもあります。
- 前遺言と後の遺言で内容が矛盾する
- 作成した遺言と矛盾する行為がある
- 遺言者が目的物を破棄してしまった
必ずしも遺言書そのものを撤回しなくても、これらの行為をすることによって、実質的に遺言が撤回されるということです。
「遺言書に記載されている財産がない!」という状態は、これらのケースに該当するといえるでしょう。
なお、これらの行為で遺言が撤回されるにしても、遺言のすべてが無効になるわけではありません。
撤回されるのは新しい遺言や後に行われた行為と矛盾している部分のみです。そのため、遺言書に記載されているAという財産がないとしても、その他の部分まで無効になることはありません。
それでは遺言の撤回とみなされる行為について詳しく解説します。
前遺言と後の遺言で内容が矛盾する
さきほども軽く説明しましたが、新しく作った遺言と以前作った遺言の内容が矛盾する場合、新しい遺言が優先されます。つまり、この場合自動的に前の遺言は撤回されたとみなされるのです。
例えば、車は子に相続させると言いながら、次の遺言では車の相続人は妻としているような場合です。この場合、新しいほうの遺言書に従って相続手続を進めます。
作成した遺言と矛盾する行為がある
遺言を作成したのちに、その遺言と矛盾するような行為を遺言者がしてしまった場合、それは遺言を撤回したとみなされます。
例えば、車は子に相続させるといいながら、まだ生きているうちに気持ちが変わり、自分の友人などに贈与してしまったような場合です。
この場合、作成した遺言と矛盾する行為によって失われた財産については、遺言書が撤回されたということであるため、その財産を相続することはできません。
ただし、その他の部分については有効であるため、撤回されていない部分について相続手続を進めていきます。
遺言者が目的物を破棄してしまった
遺言者が自分の意思で、遺贈や相続の目的物を破棄してしまったりした場合、それは遺言の撤回とみなされます。
例えば、集めていた宝石を妻に相続させると言いながら、生前それを捨ててしまったり売ってしまったりしたような場合です。
この場合も、やはり破棄された財産については、相続手続ができません。(やはりその他の部分については有効であるため、撤回されていない部分について相続手続を進めていきます)
遺言に書かれた金額が足りない場合はどうする?
「銀行口座を見たら、遺言に書かれた金額より少ないお金しか残っていなかった」ということもあります。遺言に書かれた金額が足りない場合、どうすればいいのでしょうか。
たとえば次のようなケースで考えてみます。
- 遺言書には「長女にA銀行の預金1,000万円を相続させる」と記載がある
- A銀行の預金には100万円しか残されていない
- 実家の金庫内には現金900万円ほどある
考えられる方法は次の2つです。
- 他の財産がある場合は充当も可能
- 他の財産がない場合は不足した金額を相続
他の財産がある場合は充当も可能
このように遺言書で「A銀行預金〇〇円を相続させる」と記載されているにも関わらず、実際にはその金額が不足していた場合、ほかの財産で補うことになる可能性があります。
これは遺言書全体の書き方により、仮にA銀の○○円を相続させると書いてあっても、他の記載から不足分を補充すると解釈できるような場合です。
たとえば次のような財産があれば、不足分を補うこともできるでしょう。
- 他の預貯金
- 株式
- 宝飾品
- 自動車
しかし、これらの財産が、遺言書で他の人に相続させると記載されていた場合には、その財産はその指定された人が相続します。そのため不足分として補うことはできません。
不足分を補える財産は、あくまでも特定の人へ相続させると遺言書に記載されていない財産があるときです。
今回の例でいえば、実家の金庫内には現金900万円ほどあるということですから、もしその金庫の現金を相続する人が遺言書で指定されていなければ、充当できる可能性もあるでしょう。
他の財産がない場合は不足した金額を相続
「銀行預金〇〇円を相続させる」と記載されているにも関わらず、実際にはその金額が不足していたときで、遺言書に他の財産から不足分を補うことが書かれていないような場合は、それは遺言者が生前処分により、遺言を撤回したと考えられます。
そのため充当できるような財産がない場合には、遺言で指定された金額に不足するとしても、その範囲で指定された銀行預貯金などを相続することになります。
遺言書に記載されている財産がない場合の相続は行政書士に相談
遺言書を見つけたのに、そこに書かれている財産がない!ということになると、どのように手続を進めたらいいのか分からず困ってしまうでしょう。
もし遺言書に記載されている財産がなく、どのように相続手続を進めたらいいのか分からないという場合には、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。初回相談は無料なので、まずは来所予約をお待ちしております。