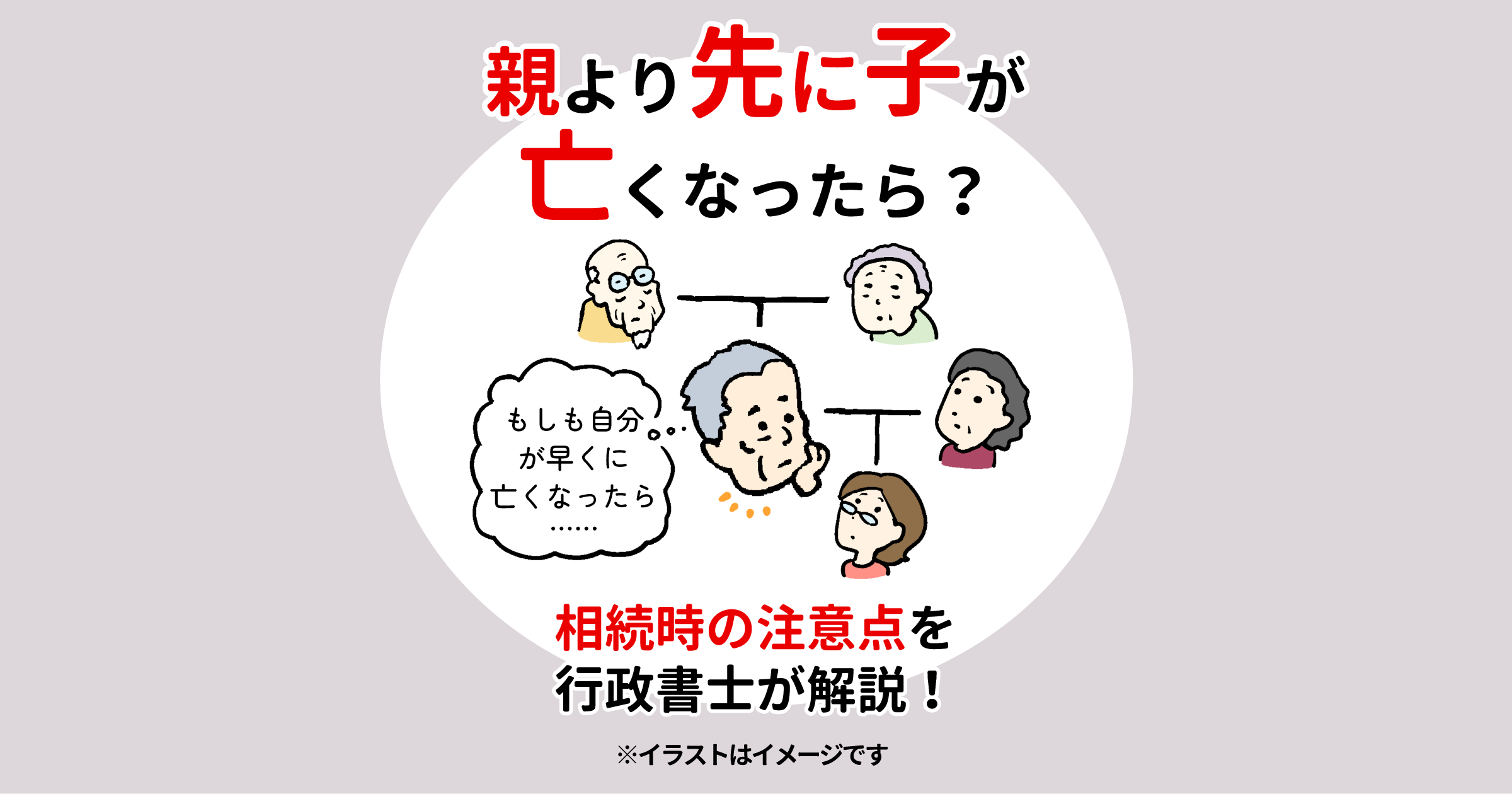「親も子の自分も高齢で、もしも自分が先に亡くなった時に備えて何かしておきたい」
「親より子が先に亡くなると、相続時にはどのような注意点があるのか教えてほしい」
高齢社会の日本では親も子も高齢となり、子が先に亡くなってしまう相続も多く発生しています。令和2年の国勢調査によると未婚率の上昇も続いており、未婚の子が先に亡くなり親が相続人となるケースにも備えておくべきでしょう。
そこで、本記事では親より子が先に亡くなってしまう時の注意点について、相続の視点から行政書士が詳しく解説します。
参考URL 総務省統計局 令和2年国勢調査 調査の結果
親より先に子が亡くなった場合|誰が相続人になる?
ご自身より先に大切な子が亡くなられるという、つらい事態に直面された場合、残された父母はさまざまな手続きや疑問に戸惑うことがあります。
その一つに「子の遺産を誰がどのように相続するのか」という問題が挙げられます。民法では相続人の順位や範囲が明確に定められていますが、親が子の相続をする際には誰が相続人になるのでしょうか。この章で詳しく解説します。
亡くなった子に配偶者や子がいるケース
子に生前、配偶者や子がいる場合、相続人になる人は以下です。
- 子の配偶者は常に相続人
- 子の子(孫)は第一順位の相続人(孫が代襲相続する)
代襲相続とは、相続人となるはずであった者が相続開始以前に死亡していたり、相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合に、その人の子へと相続権が移動することを意味します。
相続人の子の代襲相続は孫となりますが、孫にも代襲相続の原因があるときには、ひ孫と順次下の世代が相続します。子がいる場合、父母は相続人になりません。
合わせて読みたい:代表相続人とは?相続時に定める意味と代表的な業務を行政書士が解説!
亡くなった子に配偶者のみいるケース
亡くなった子に配偶者はいるものの、子(孫)がいない場合、相続人になる人は以下です。
- 配偶者は常に相続人
- 父母が第二順位の相続人
この場合、配偶者と父母が共同で相続することになります。相続割合は配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。父母が両名ともご健在の場合は3分の1を2名で分けるため、それぞれが6分の1を取得します。
合わせて読みたい:両親が相続人になるのはどういう場合?法定相続の「第二順位」を行政書士が解説!
亡くなった子に配偶者や子(孫)がいないケース
亡くなった子に配偶者も子や孫もいない場合、父母のみ相続人となり、子の遺産をすべて相続することになります。もし、亡くなった子の父母が両名ともご健在の場合は、それぞれ2分の1ずつ相続します。
相続人が誰もいないとどうなる?
亡くなった子に民法で定められた相続人が誰もいない場合、子の遺産はどうなるのでしょうか。遺産のゆくえは以下の3つが挙げられます。
① 遺言書がある場合
まず、亡くなった子が有効な遺言書を作成していた場合、その遺言書の内容に従って遺産が分けられます。遺言書があれば、法定相続人以外の人や団体に遺産を遺すことも可能です。
② 特別縁故者がいる場合
もし遺言書がない場合でも亡くなった子と生計を同じくしていた人、療養看護に尽力した人など、特別な関係があった人(特別縁故者)がいる場合、家庭裁判所の審判によってその特別縁故者に遺産の一部または全部が渡されることがあります。
③ 最終的に国庫の帰属
遺言書もなく、特別縁故者もいない場合、亡くなった子の遺産は最終的に国のものとなります。(国庫に帰属)
合わせて読みたい:相続放棄をした後の財産はどうなる?財産の管理方法や注意点を行政書士が解説!
子が亡くなり親だけが相続人となる際の注意点とは
子が亡くなり、父母だけが相続人となる場合は相続手続に注意点も存在します。この章で解説しますので、もしも実際の相続手続に直面している人はぜひご参考ください。
別居期間が長いと、子の相続財産の調査に難航する
子と別居期間が長かった場合、子が生前にどのような財産を持っていたのか、把握する際に時間がかかることがあります。
相続財産を調べる際には銀行口座・不動産・有価証券・加入していた保険などを1つひとつ調査していく必要があり、大きな負担となるおそれがあります。
退職金や死亡保険金の受取も発生することがあるため、漏れのない手続きが大切です。
相続財産調査のお悩みも
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
高齢により遺品整理が進まない
父母が高齢の場合、子の遺品整理をご自身で行うことが困難な場合があります。体力的な問題だけでなく、大切な子の遺品を整理することは精神的な負担も大きいため、専門の遺品整理業者に依頼することも検討が必要です。
また、遠方に別居中の子が亡くなった場合は遺品整理に出向くことが難しく、遺品整理全般を業者へ依頼せざるを得ないケースもあります。
合わせて読みたい:遺産整理と遺品整理の違いとは|相続放棄への影響について行政書士が解説!
一部の相続税の控除が使えない
配偶者や子が相続人となる場合には、相続税の配偶者控除や未成年者控除といった税制上の優遇措置がありますが、父母が子の相続人となる場合にはこれらの控除は適用されません。
そのため、相続税が発生する場合は納税額が高くなりやすく、納税資金に苦慮するおそれがあります。相続税が発生する可能性がある場合は、事前に税理士に相談することがおすすめです。
合わせて読みたい:相続税の基礎控除額とは?計算方法や相続税申告が必要な例を紹介!【税理士監修】
デジタル遺品が見落とされやすい
近年インターネットバンキングの口座情報、ダイレクト型保険やSNSのアカウント、仮想通貨などのデジタル遺品も増えています。こうしたデジタル遺品は通帳や取引履歴、保険証券などの形がないため、見落とされやすい傾向があります。
子のパソコンやスマートフォンなどを確認する場合、画面やアプリにロックがかかっていることも多く、解除を専門家に依頼するケースも少なくありません。
特に高齢の父母がこの遺品を整理する際には、デジタル遺品を見落とす可能性があります。加えて、解約や整理に手間がかかることがあるため行政書士等の相続の専門家に相談した上で相続手続全般を進めることがおすすめです。
合わせて読みたい:デジタル遺品とは何?スマホやPCの相続について行政書士が解説!
親が相続人になる場合|相続開始後にやるべき2つのこと
自身より先にお子様が亡くなるという事態は予測できるものではありません。では、子の相続を迎えたらどのように手続を進めるべきでしょうか。相続開始後の手続にについて、できる対応を2つに分けて解説します。
相続手続の専門家へ相談する
お子様を亡くされた悲しみは計り知れません。加えて、相続の手続は戸籍謄本類の収集や相続財産の特定など、複雑な手続を進めていく必要があります。心身に大きな負担を感じる前に、相続手続の専門家へご相談ください。
例として、行政書士は相続人調査のための戸籍請求、遺産の調査、相続関係図作成などの相続手続をおまかせいただけます。
相続人調査のお悩みも
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
相続手続の期限を把握しておく
相続が発生した場合、さまざまな手続きを行う必要に迫られます。これらの手続きには法律で定められた期限があるものが多いため注意が必要です。あらかじめ期限を把握し、遅れないように手続を進めましょう。
以下に、特に注意しておきたい相続手続期限をまとめています。
① 相続放棄・限定承認の熟慮期間:相続の開始を知った時から【3ヶ月以内】
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切引き継がないという手続です。一方、限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で、亡くなった方の債務を弁済するという手続です。
これらの手続を行うかどうかは、相続の開始を知った時から原則として3ヶ月以内に決定し、家庭裁判所に申し立てる必要があります。財産状況が不明な場合は、この期間内に慎重に検討しましょう。
② 相続税の申告・納付期限:相続の開始を知った日の翌日から【10ヶ月以内】
相続税は、亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合に課される税金です。相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があるため、注意が必要です。なお、準確定申告が必要な場合は「相続の開始から4か月以内」です。
③ 相続登記:相続で不動産を取得したことを知った日から【3年以内】
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
合わせて読みたい:遺産相続の流れや期限について行政書士が解説!
相続手続は横浜市の長岡行政書士事務所へお尋ねください
港南中央駅から徒歩1分の位置にある横浜市の長岡行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況やご希望を丁寧に伺い、最適な相続手続をサポートしています。
印鑑1本で、面倒な調査や書類、各種手続が完了する相続サービスはご高齢の方にも好評です。相続に関する不安やお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。