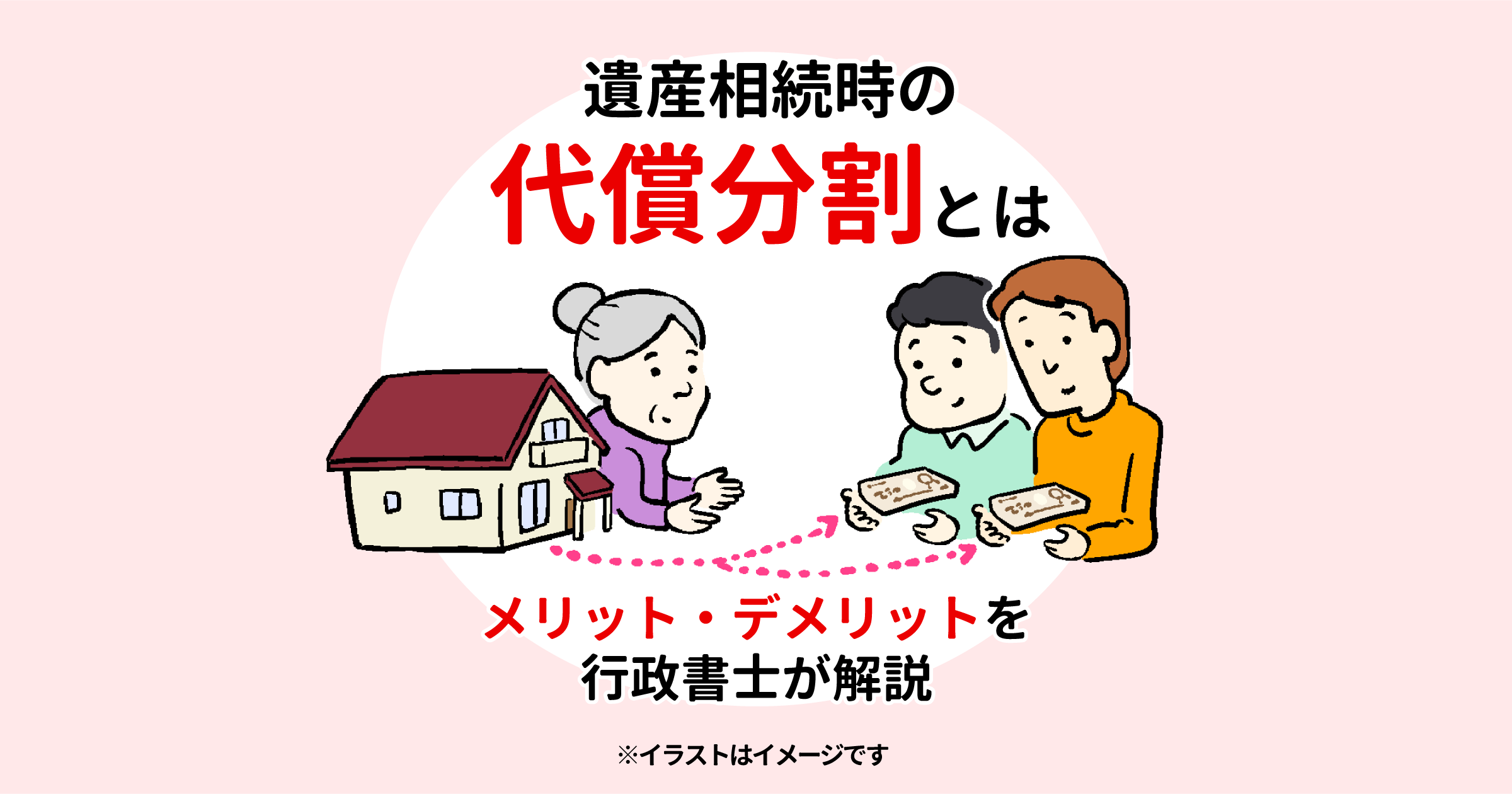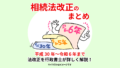「不動産が絡む遺産分割時には代償分割がおすすめと聞いたけど、注意点はあるの?」
「長男が実家の土地と建物を継承する。他の相続人にはどのように財産を分けたら良いか。」
「代償分割を検討しているが、どのようなケースにおすすめの方法か。」
大切な遺産を相続人間で分割する時、「代償分割」と呼ばれる方法があることをご存じでしょうか。代償分割を行う場合、知っておきたいメリット・デメリットがあります。この記事では代償分割の概要や、注意点、おすすめされるケースを行政書士がわかりやすく紹介します。
遺産分割とは
代償分割とは、不動産などの現物を取得する相続人が、現物を取得しない相続人に対して代償金を支払うことを意味します。
たとえば、相続人が子2名、亡父が遺した相続財産は「3,000万円の価値のある不動産」だったと仮定しましょう。遺産分割協議を行った結果、子1名がそのまま住みたい、と希望する場合、住む予定の無いもう1名に対して、代償金として1,500万円を支払うイメージです。
もちろん、現金を仮に500万円しか用意できなくても、もう1名の子が納得していれば、遺産分割協議は成立します。
なお、代償分割が難しい場合には、その他の分割方法として、「換価分割」「現物分割」を検討することもあります。
換価分割とは、分割が難しいケースにおいて、相続財産を売却して現金にした上で分割を行うことを意味します。換価分割は財産を手放してしまうデメリットはありますが、スムーズな相続手続につながるためメリットもある方法です。
合わせて読みたい:換価分割とは
現物分割は、現物をそのまま相続人に帰属させる相続方法です。
わかりやすくいうと、被相続人が現金、預貯金、不動産の3つの財産を遺した場合、現金は長男、預貯金は次男、不動産を妻、のようにそのまま相続することを意味します。売却手続も無いため、スムーズな相続が可能ですが、相続人間で「不公平さ」が生じることがあります。
遺された相続財産の中で、評価が大きく分かれる場合(高額の不動産はあるが、現金はほとんどないなど)現物分割は難航するおそれもあります。
代償分割のメリット
代償分割のメリットとしては、次の3点が挙げられます。
- 不動産などの現物資産を残せる
- 相続税対策になることがある
- 事業承継対策にもなる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
不動産などの現物資産を残せる
不動産などの現物が絡む相続では、相続財産を売却して現金にした上で分割する「換価分割」を選ぶこともあります。
しかし、たとえばマイホームしか相続財産がなく、その家に誰かが住み続けたいという場合には、不動産を売却してしまっては住むことができません。
また、相続財産の大部分をマイホームが占めている場合、現物分割は不公平と感じる相続人もいるでしょう。
このような場合、「代償分割」であれば、マイホームなど現物資産を残しつつ、相続人同士の公平性を保つこともできます。
相続税対策になることがある
また、不動産を残して相続する場合、「相続税対策」につながることもあります。小規模宅地等の特例の要件を満たしていれば、相続税が減額されるためです。
関連記事:相続時の「小規模宅地等の特例」とは?土地の評価額が最大80%減額される制度を税理士が解説
事業承継対策にもなる
加えて、不動産や株式など事業資産をまとめて相続したい方が、代償金を事業承継しない方に現金を支払えば、事業資産が細分化し会社が傾いてしまうような事態を避けられます。
代償分割のデメリット
代償分割には少なからずデメリットも存在します。
まず挙げられるのは、「代償金が重い負担となる」点です。不動産や動産といった現物を取得する場合、それとは別に現金を用意する必要があります。数百万円~1千万円以上の現金を用意しなければならないこともあり、その負担は少なくありません。
また、すべての相続人が代償金の額に納得してくれるわけではありません。「この不動産なら、もっと代償金をもらえるはずだ!」と主張されるおそれもあります。
不動産などの財産評価を適切に行う必要もあり、代償分割の前には専門家に相談をすることもおすすめされます。
横浜市の長岡行政書士事務所では代償分割での相続手続もサポートしているため、お気軽にお問い合わせください。
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
代償分割の活用がおすすめされるケース
代償分割はさまざまなシーンで活用できますが、とくに次のような場合におすすめです。
- 特定の相続人が会社を引き継ぐ時に活用するケース
- 長年暮らした実家を手元に残したいケース
- 代償金は用意できないけど、相続人同士で納得できるケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
特定の相続人が会社を引き継ぐ時に活用するケース
会社の後継者として、相続を機会に事業用店舗や株式をまとめて相続する方の場合、その他の相続人に代償金を支払えば、事業継承が円滑に進むでしょう。
株式がいろんな方の手に渡ってしまうと同族経営が揺らぐケースや、多くの事業資産をまとめて管理したいケースもおすすめです。
関連記事:オーナー経営者の地位は相続できる?経営権・会社所有財産と相続の関係を行政書士が解説!
なお、事業継承が発生する相続では、代償分割を行うことが多くなっています。しかし、より確実に事業継承を進めるために、相続開始後における相続人同士の話し合いに任せるのではなく、「遺言書」が用意されていることもあるため注意してください。
遺言書では代償金の支払いを指定できます。そのため相続手続をスムーズに進めるために、以下のような文言の遺言書が残されていることがあるのです。
| 「第〇条 遺言者は、遺言者の有する以下の不動産を、長男長岡太郎に相続させる」 (不動産の表示) 「第〇条 長男長岡太郎は、前条記載の相続に対する負担として、長女長岡花子に1,500万円を代償金として支払う」 |
代償金の絡む遺言書が残されているものの、どのように手続を進めていったらいいのか分からない場合にも、長岡行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
合わせて読みたい:会社経営者が子に事業を承継させたい!遺言の活用方法を行政書士が解説
長年暮らした実家を手元に残したいケース
実家を継ぐ子や、夫を亡くした後も実家に住み続けたい妻なども、代償分割がおすすめされます。財産を巡って相続人間でトラブルになりそうでも、不動産を売却してしまったら暮らす家が失われてしまいます。
長年暮らした実家を相続時に手放さないためにも、相続の解決方法として検討すると良いでしょう。
代償金は用意できないけど、相続人同士で納得できるケース
実家など特定の財産を取得する代わりに、別の財産を渡す場合、相続人間で同意ができれば必ずしも代償金は用意する必要がありません。
被相続人が遺した実家はもらう代わりに、相続人が所有していた別荘を渡すなどの方法で、相続人間で同意ができれば、代償分割は無事に成立します。
代償分割のご相談は長岡行政書士事務所へ
今回の記事では、代償分割について詳しく解説しました。代償分割は遺産分割の方法の1つであり、換価分割や現物分割とも比較しながら、じっくりと検討されることがおすすめです。
事業継承における代償分割を検討している場合、生前から未来の相続に向けて、遺言書が用意されていることもあります。
代償分割が伴う相続でお困りの方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。初回相談は無料です。LINE・電話などで来所予約を承っております。