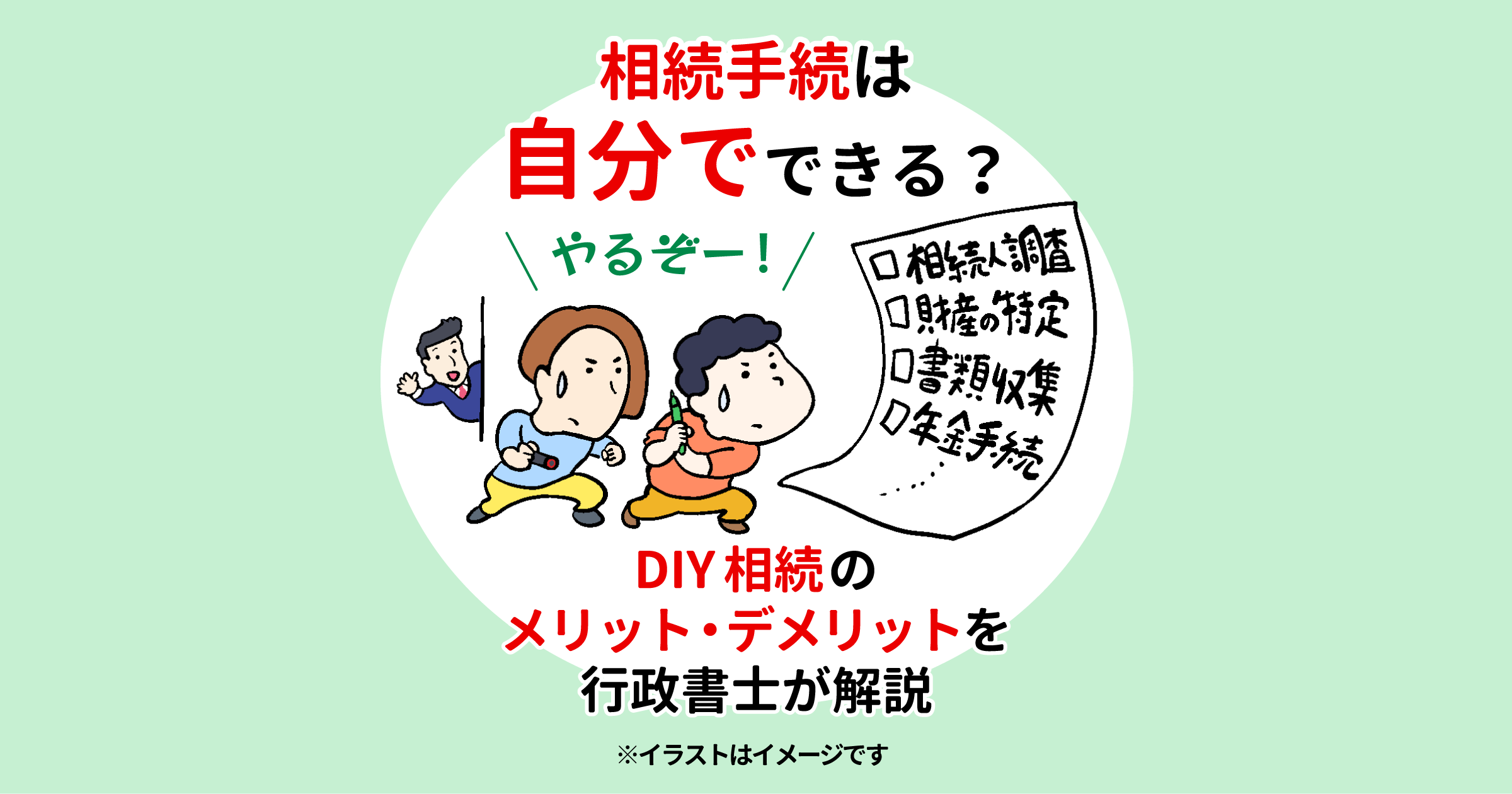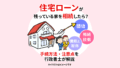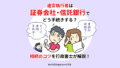「亡母の相続手続を始めるが、自分で進めることは可能か知りたい」
「相続手続を家族で協力してやってみようと思うが、デメリットはあるだろうか」
相続手続は非常に種類が多く、ご自身で進められるものもありますが専門家に相談することがおすすめのケースも少なくありません。
そこで、本記事では相続手続について、ご自身で進める「DIY相続」のメリット・デメリットを行政書士が詳しく解説します。手続上の注意点もあわせて紹介しますので、ぜひご一読ください。
相続手続は自分でできる!主な種類とは
相続手続は相続人自身で行うことが可能です。では、どのような種類の手続を自分で行えるでしょうか。この章で詳しく解説します。
相続人調査
相続を開始すると、さまざまな手続を進めていくために「誰が相続人なのか」を特定する作業が必要です。この作業は被相続人の戸籍謄本類を取得して正確に把握するものです。戸籍謄本類の収集は相続人自身で可能です。
合わせて読みたい:戸籍の広域交付制度とは|利用方法や注意点を行政書士が解説!
相続財産の特定
相続の作業の1つには「相続財産の特定」が挙げられます。被相続人の現金や預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、被相続人が所有していた財産を特定する作業です。この作業は遺産分割協議や相続税申告にも欠かせない作業であり、相続人自身で行えます。
相続財産調査のお悩みも
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
合わせて読みたい:相続で故人の銀行口座はどう調べる?調査方法を行政書士が解説!
必要書類の収集
相続手続にはさまざまな書類を収集する必要があります。相続人調査に必要な戸籍謄本類などはもちろん、相続登記などで必要な書類も多く、ご自身に必要な相続手続にあわせて書類を収集します。この作業も相続人で収集可能です。
| 収集する書類の例 | 書類が必要となる主な相続手続 |
| 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本 | ・相続人調査(出生から死亡まで全ての戸籍が必要) ・不動産の相続登記 ・預貯金の解約 ・名義変更 ・相続税申告 など |
| 固定資産税評価証明書 | ・相続登記 など |
| 財産の相続に必要となる書類 ・預貯金通帳や証書、残高証明書 ・有価証券報告書、取引残高報告書 ・生命保険などの保険証書 ・負債に関する書類(借用書、ローン残高証明書など) | ・相続財産の取得 ・解約時 ・相続税計算 ・遺産分割協議 など |
※上記の書類・手続は一例です。実際の相続時にはこうした作業以外の手続も発生することがあります。
被相続人の健康保険・年金に関する手続
被相続人が亡くなった際、社会保険に関する手続も早急に行う必要があります。
- 健康保険の資格喪失手続
健康保険証を返却し、健康保険料の発生を止めるために行います。被相続人が会社員だった場合は勤務先、国民健康保険に加入していた場合は市区町村役場が窓口となります。
- 年金に関する手続
被相続人が年金受給者であった場合は、受給停止が必要です。停止の手続を怠ってしまうと返還を求められることがあるため注意しましょう。
ご遺族には「遺族年金」や「死亡一時金」などが支給される可能性があります。これらは遺族の生活を支える大切な給付金ですので、受給資格があるかを確認し、速やかに請求手続を行うことが大切です。
健康保険からは「埋葬料」、国民健康保険からは「葬祭費」という名目で葬祭費用が支給されることもあるため確認しましょう。
被相続人の生命保険・損害保険に関する手続
被相続人が生前に加入していた生命保険や損害保険に関する手続も、相続開始後に進める必要があります。
- 生命保険金の請求
一般的には、保険会社に死亡の連絡をし、必要書類(死亡診断書、戸籍謄本、受取人の本人確認書類など)を提出して請求手続を行います。保険金が支払われるまでには一定の時間がかかることがあるため、早めに手続を開始しましょう。生命保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の完了を待たずに受領できます。
- 損害保険への請求や解約、引継ぎ
損害保険には火災保険や自動車保険、傷害保険など多数の種類があります。被相続人が所有していた建物が火災保険に加入していた場合、名義変更の手続が必要になることがあります。
また、事故で亡くなった場合は、加入していた自動車保険や傷害保険から保険金が支払われる可能性もあります。これらの保険についても、まずは契約内容を確認し、保険会社に連絡を取って必要な手続を進めましょう。
合わせて読みたい:故人の生命保険契約の調べ方とは?相続手続で便利な契約照会制度を行政書士が解説!
遺品整理
遺品整理は、被相続人の持ち物の整理を通して大切な人との思い出を偲ぶための作業です。形見分けの作業につながるため相続人が行うことが多いでしょう。しかし、不要品の仕分け作業などは重労働をともなうことも多いため、外部に委託することもできます。
合わせて読みたい:遺産整理と遺品整理の違いとは|相続放棄への影響について行政書士が解説!
DIY相続のメリット・デメリット
ご自身で相続手続を進める「DIY相続」にはメリットもありますが、相続手続の中には複雑なものや、法的な注意点を要するものも多く慎重な対応が求められるケースもあります。
そこで、この章ではDIY相続のメリット・デメリットをわかりやすく整理します。
メリット
① 費用を抑えられる
専門家に依頼する費用がかからないため、相続財産が少ない場合や手続の内容がシンプルな場合に費用を節約できます。
② 次の相続への備えになる
自身で手続を行うことで相続に関する知識や経験が身につきます。次の相続や自身の相続対策にも役立つでしょう。
③ 気持ちの整理につながる
被相続人の財産や書類などを整理・確認し、手続を進める作業は大切な方を失った悲しみを整理する作業でもあります。ご逝去直後はつらいお気持ちを抱えて悩む方も多いですが、相続手続を進める中で気持ちが落ち着くことも少なくありません。
デメリット
① 致命的なミスが起きる可能性がある
相続手続の中には専門的な知識が必要な場面も多く、誤った手続をしてしまうと、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。例えば、相続税の申告漏れや、遺産分割協議の不備などが考えられます。
② 時間がかかる
DIY相続は戸籍の収集や書類の作成など、非常に多くの時間と労力を要する可能性があります。特に平日に動けない場合や、相続財産の種類・金額が多い場合には手続が長期化する傾向にあります。
③ 家族間の争いに発展するおそれ
相続人同士の意見の相違や、感情的な対立が生じた際、専門家がいないと話し合いがこじれてしまい家族間の関係が悪化するリスクがあります。
④ 結局専門家の力が必要になることも
DIY相続を進めていても途中で手続の複雑さに直面したり、トラブルが発生したりすることで、結局専門家に依頼せざるを得なくなるケースも少なくありません。
DIY相続を進める前に|専門家に相談するメリットとは
DIY相続にはメリットもありますが、時間がかかったりミスが起きたりとトラブルが発生する可能性もあります。相続手続をご自身で進めたい場合でも、まずは専門家へ相談することには、多くのメリットがあります。詳しくは以下です。
相続手続の予算や労力が事前にわかる
相続の専門家である行政書士などへ相談すると、手続の全体像を把握し、必要な費用を事前に見積もってくれます。無計画に進めることによる予期せぬ出費や労力を防ぎ、安心して手続を進められます。思いの外労力がかかりそうな場合、そのまま手続を依頼することも可能です。
相続手続の注意点がわかる
相続には法律や税金に関する専門知識が必要です。専門家は個別のケースに応じた注意点や、見落としがちなポイントを教えてくれるため、後々のトラブルを未然に防げます。
依頼後はスムーズな手続で負担が軽減される
専門家へ相続手続を依頼する場合、煩雑な書類収集や複雑な手続を代行してもらえます。
これにより、時間的・精神的な負担が大幅に軽減され、相続によるストレスを軽減できます。財産の相続などもスムーズとなるため、生活への不安なども早期解消を目指せます。
合わせて読みたい:相続手続を依頼する専門家は故人・相続人どちらの居住地で探せばいい?
相続手続に困ったら専門家への相談がおすすめ!
本記事ではDIY相続によるメリット・デメリットについて、専門家へ相談するメリットも交えながら詳しく解説しました。
ご自身で相続手続を行うと費用を抑えられるなどのメリットがある一方で、致命的なミスや家族間のトラブル、そして何より膨大な時間と労力がかかるデメリットも存在します。
相続手続は、大切なご家族の思いを受け継ぎ、家族が新たな一歩を踏み出すための大切な節目です。不安を感じたり、少しでも疑問が生じたりした場合はまずは専門家へご相談ください。横浜市の長岡行政書士事務所では、ご依頼者様の状況に合わせた最適な手続方法を提案し、スムーズな相続をサポートしています。まずはお気軽にお尋ねください。