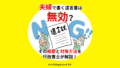「面識がない異母兄弟と亡父の相続手続きをするが、法定相続分は同じ?」
「異父兄弟がいるが、今後来るべき相続には不安がある。気を付けるべきポイントとは?」
「離婚時に前妻が引き取った子、今の婚姻生活で授かった子がいる。自分が亡くなったら相続がどうなるのか心配だが、対策はある?」
異父・異母兄弟がいる場合の相続は、面識がないもの同士が遺産分割について話し合うことになり、時に大きなトラブルに発展することがあります。法定相続分や、気を付けるべきポイントを早くから押さえておくことが大切です。
そこで、本記事では異父・異母兄弟の相続について行政書士がわかりやすくポイントを解説します。
異父兄弟・異母兄弟が同時に相続人となる例
異父兄弟・異母兄弟が同時に相続人となるケースとしては、次のような例が挙げられます。
- 親が亡くなり異父・異母兄弟が「子ども」として相続する
- 兄弟姉妹が亡くなり異母・異父兄弟で「きょうだい」として相続する
いずれかに該当する可能性がある場合は、相続の進め方に注意したほうがいいかもしれません。それぞれの例について、詳しく見ていきましょう。
親が亡くなり異父・異母兄弟が「子ども」として相続する
異父・異母兄弟で相続するケースには「親が亡くなり、子どもとして相続する」ケースがあります。たとえば、以下のようなケースです。
- 亡父に現在の配偶者との子1名だけではなく、前妻との子1名がいる。亡父の相続は現在の配偶者、現在の配偶者との子、前妻との子(異母兄弟)の計3名で相続手続きをする
- 亡母に前夫との子がいる。亡母の相続は現在の配偶者、現在の配偶者との子1名と前夫の子(異父兄弟)の子1名の計3名で相続手続きをする
このようなケースでは、民法上の相続人の順位は以下となります。
- 配偶者…常に相続人となる(離婚した前妻、前夫に相続権はない)
- 第1順位…亡くなった被相続人の子
ただし、認知されていない非嫡出子の場合は相続権がありません。子が相続権を有するためには認知される必要があるのです。嫡出子・非嫡出子については下記記事もご一読ください。
合わせて読みたい:嫡出子と非嫡出子とは|相続における法定相続分について行政書士が解説
兄弟姉妹が亡くなり異母・異父兄弟で「きょうだい」として相続する
兄弟姉妹が亡くなった時に、異母・異父兄弟で「きょうだい」として相続するケースもあります。たとえば、以下のようなケースです。
- 異母兄弟が亡くなったと連絡があった。被相続人には配偶者がいたため、被相続人の配偶者と面識のない被相続人の妹、異母兄弟の自身の計3名で相続する
- 面識がない異父兄弟が亡くなった。被相続人には配偶者や子はおらず、両親も他界しているため、被相続人の兄と自身の計2名で相続する
兄弟姉妹の相続は第3順位のため、第1順位の子や孫がいる場合は相続人にはなりません。また、相続人になるためには認知を受けている必要があり、非嫡出子で認知がなされていない異父・異母兄弟は相続人になれません。
合わせて読みたい:半血の兄弟姉妹の相続分とは?第一順位と第三順位の時の相続の違い
異父兄弟・異母兄弟の法定相続分
法定相続分とは、民法で定められている相続人の相続割合のことです。
この法定相続分は、異父兄弟・異母兄弟だとどうなるのでしょうか。「子ども」として相続する場合、「きょうだい」として相続する場合、それぞれ解説します。
親の遺産を相続する場合の法定相続分は異父兄弟・異母兄弟で平等
亡親の相続を子ども(第一順位)として相続する場合、法定相続分は以下です。
| 配偶者 | 子ども | |
| 亡親に配偶者がいる | 2分の1 | 子ども全員で2分の1 (例・子2名なら、4分の1ずつ) |
| 亡親に配偶者がいない | × | 子ども全員で遺産を均等に分けて相続する |
異母・異父兄弟であったとしても、もらえる法定相続分は同じです。ただし、法定相続分はあくまでも目安です。遺産分割協議の中で話し合いながら、もらう財産の割合を決めます。
兄弟の遺産を相続する場合の法定相続分は半血・全血で異なる
亡兄弟姉妹の財産をきょうだい(第三順位)として相続する場合の法定相続分は以下です。
| 配偶者 | きょうだい | |
| 亡兄弟姉妹に配偶者がいる | 4分の3 | きょうだい全員で4分の1 (例・きょうだいが2名なら8分の1ずつ) |
| 亡兄弟姉妹に配偶者がいない | × | きょうだい全員で遺産を均等に分けて相続する ※ただし、半血兄弟姉妹は法定相続分の半分 |
兄弟姉妹が亡くなった場合、時半血の兄弟姉妹と全血の兄弟姉妹では、もらえる法定相続分は異なっています。民法900条4項を見てみましょう。
引用:民法900条4項
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
たとえば、被相続人に全血兄弟の相続人1名、半血兄弟の相続人1名がおり6,000万円の相続財産を2名で相続する場合は法定相続分は3,000万円ずつではなく以下となります。
- 全血兄弟…3分の2もらえるため、4,000万円
- 半血兄弟…3分の1もらえるため、2,000万円
異父兄弟・異母兄弟が絡む相続が難しい理由と対策
異父・異母兄弟がいる相続は、民法上で定められている法定相続分があったとしても、遺産分割時にトラブルが起きやすくなります。例として、以下のようなトラブルが実際に起きています。
- 遺産分割協議に参加しようとしない相続人がいる
- 遺産を渡したくないと主張する相続人がいる
- 異父・異母兄弟に連絡が取れない
ここからは異父兄弟・異母兄弟が絡む相続が難しい理由と、その対策について見ていきましょう。
遺産分割協議に参加しようとしない相続人がいる
異父・異母兄弟はそもそも「面識がない」というケースがあります。たとえば、亡父に離婚歴があり前妻との間に子がいる場合、子が前妻と長年暮らしていることは珍しいケースではありません。すると、亡父の再婚後に生まれた子と、前妻との子には交流が無く相続時に初めて交流する場合があります。面識がなかった子同士が財産をめぐって協議する場合、冷静な話し合いが難しいことがあります。
実際にあったケースでは、前妻の子が亡父に良い感情を持っておらず「遺産分割協議をしたくない」ということがありました。しかし、遺産分割協議は相続人全員に参加してもらう必要があるため、その他の相続人はどのように遺産分割協議を進めたら良いのか悩んでしまうのです。
このようなケースでは、遺産分割を進めるために家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てしたり、相続放棄をご検討いただくなどの対応を講じる必要があります。
合わせて読みたい:遺産相続で揉めたらどうなる?遺産分割協議や遺産分割審判について解説!
遺産を渡したくないと主張する相続人がいる
亡くなった被相続人の生活を支えるために介護や扶養をしていた相続人と、介護や扶養には一切携わらなかった相続人がいたとしても、法定相続分に影響しません。
たとえば、亡父を長年介護していた子と、前妻の子で亡父とは没交渉だった子であっても、法定相続分は「同じ」なのです。
そのため、遺産分割協議時には苦労をした相続人と、それ以外の相続人の間で財産をめぐって対立することがあります。感情的な対立が起きやすいのです。
何も面倒を見てこなかった異父・異母兄弟に「遺産を渡したくない」と思う気持ちも、分からなくはありません。
しかし法律的に、「遺産を渡さない」ということはできません。たとえ遺言書があったとしても、遺留分を主張される可能性はあります。(兄弟姉妹の財産を相続する場合は遺留分を主張できません)
もし介護や扶養で貢献したから財産を多めに受け取りたいという場合には、「寄与分」を主張する必要があります。そしてそのためには、介護・扶養の事実を裏付ける資料を集めなければなりません。
合わせて読みたい:寄与分の要件とは?親の介護を相続時に考慮する方法を行政書士が解説!
異父兄弟・異母兄弟に連絡が取れない
異父兄弟・異母兄弟と遺産分割協議をしようと思っても、そもそも連絡が取れない・居場所が分からないということもあります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、何とかして連絡を取らなければなりません。
居場所のわからない相続人の住所は「戸籍の附表」というもので調べることが可能といわれていますが、これは、「戸籍に掲載されている方、祖父母・父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)」に該当する方しか取得できません。
兄弟姉妹は同じ戸籍に掲載されていれば附表を取得できますが、連絡の取れない異母兄弟・異父兄弟と同じ戸籍である可能性は低いでしょう。
しかし相続手続き上必要であると市役所側へ証明すれば、戸籍が別の兄弟であっても、「戸籍の附表」を取得することは可能です。
なお、自治体によっては、自身が相続人であることを示す資料を詳しく提出するように求めるケースもあります。もし自分での手続に負担を感じるようなら、行政書士などの専門家へご相談ください。横浜市の長岡行政書士事務所でも相談を承っております。
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
合わせて読みたい>>居場所の分からない相続人の住所はどう調べる?調査方法を行政書士が解説!
異父兄弟・異母兄弟の相続手続も行政書士に相談できる
この記事では異父・異母兄弟の相続について、法定相続分や気を付けるべきポイントをわかりやすく解説しました。
遺産分割協議に参加しようとしない、遺産を渡したくないと主張する相続人がいる場合には、弁護士へ相談しなければならない場面も出てくるでしょう。
一方、遺産分割協議に参加してもらいたいけれど、異父・異母兄弟に連絡が取れないという場合には、行政書士に依頼して「戸籍の附票」を取得し、協議の案内を送ることも可能です。
もし異父兄弟・異母兄弟が絡む相続にお困りの方は、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。必要に応じて弁護士などをご紹介しながら、適切に相続手続を進められるようサポートいたします。