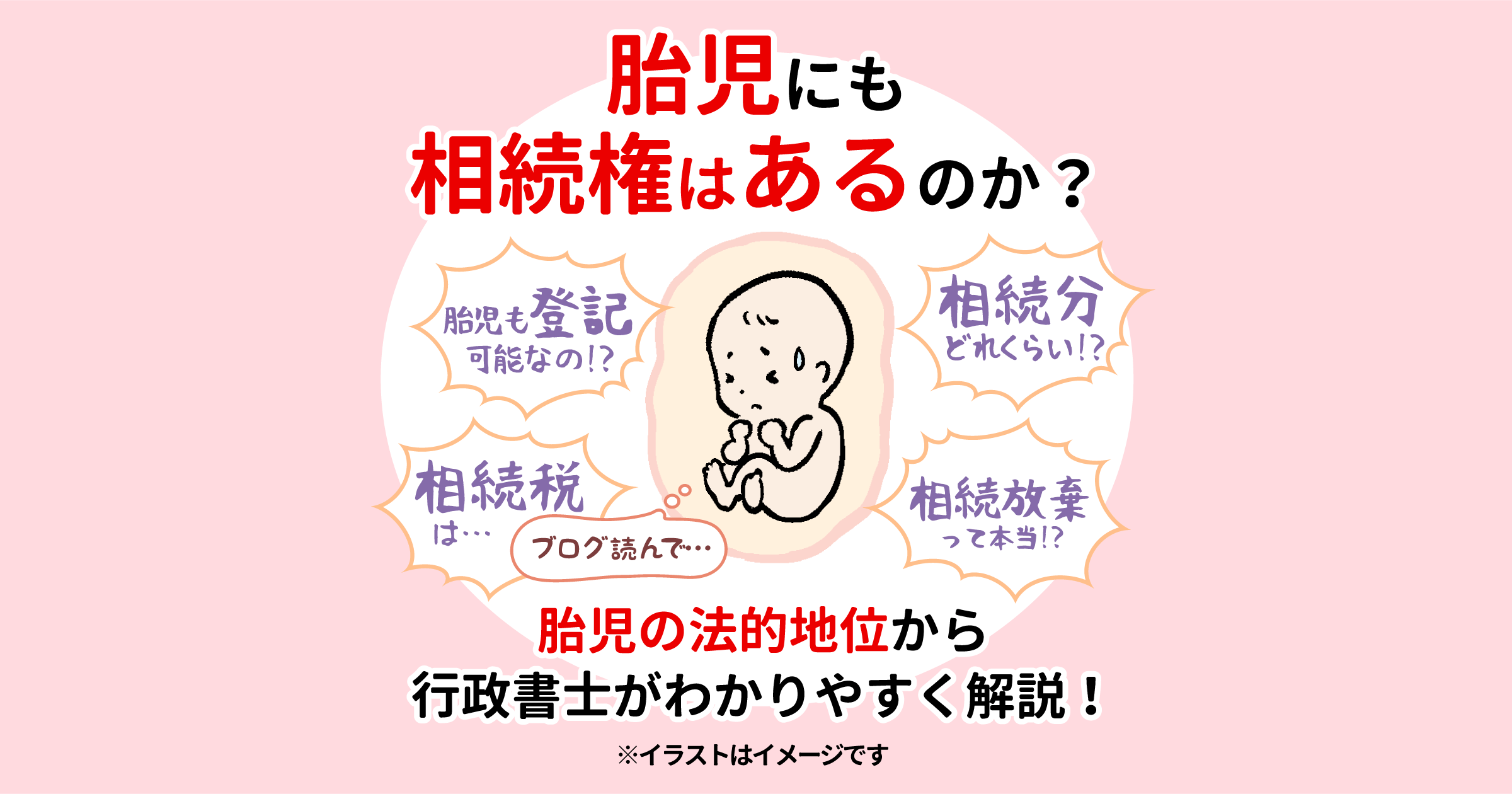「相続のときにお腹に赤ちゃんがいたら、その子って相続できるの?」
「胎児って法律上、どういう存在となるのだろう?」
「相続時に胎児がいる場合、どう手続を進めたらいいの?」
相続発生時に、例えば配偶者のおなかのなかにこれから産まれる赤ちゃんがいた場合、相続手続はどうなるのでしょう。
法律上胎児というのは、まだ生まれてはいないけれどこれから人間としての権利を獲得する存在として非常に微妙な立ち位置に置かれています。
今回はそんな胎児が相続に関わるとどのようなことになるのか、相続手続はどうすればいいのか、判例などの具体的な判断も踏まえてお話したいと思います。
胎児にも相続権はある
結論から言えば、胎児に相続権はあります。胎児の相続権について理解するために、まずは胎児の法律上の位置について見ていきましょう。
原則的に「人」として権利の主体となれるのは、出生からだとされています。つまり母のお腹から出た時から権利の主体となれるということです。
逆に言えば、お腹の中にいるうちは権利の主体になれない、という解釈となります。
民法3条第1項 私権の享有は、出生に始まる。
またこの「お腹から出たとき」というのは、胎児の身体がすべて露出したときというのが通説になっています。
しかし、まだ「人」とは正式にみなされない状態の胎児でも権利を享有することができる場面があります。
たとえば、損害賠償や遺言で財産を受け取る場合などは、権利の主体となることができるのです。
遺言で胎児に遺産を遺すことができるのですから、胎児が相続することができるのも、当然といえば当然ですね。
合わせて読みたい:胎児に相続させる遺言書は有効?胎児の相続権はいつから発生するか行政書士が解説!
胎児の相続分はすでに生まれている子と同じ
また胎児の相続分ですが、それはすでに生まれている子と同じとなります。仮に妊娠している奥さんがいて、夫が死亡したのなら、奥さんが1/2、その後胎児が産まれたのなら1/2、夫の遺産を相続することになります。
合わせて読みたい:配偶者と子供の法定相続人の割合とその範囲とは?
死産では相続権はなくなる
産まれた胎児が生きていなかった、つまりは死産であった場合はもちろん相続権がなくなります。
その場合、元から胎児には相続権がなかったことになる、ということに注意が必要です。「胎児に相続権がある状態で、その相続権が胎児の死亡によってほかの人に移転する」というややこしい事態にはなりません。
つまり胎児が産まれたか否かで、相続内容は大きく変わるのです。
胎児がいる遺産分割協議は特別代理人が必要となる
遺産分割協議とは、遺産をどうするかを決める話し合いのことです。
胎児がいる場合に遺産分割協議はどうなっていくのでしょうか。
まず前提として、遺産分割協議は全員の合意が必要です。
合わせて読みたい:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!
胎児が産まれる前に相続人同士で遺産分割協議をして内容を決めても、いざ胎児が生きた状態で生まれたのなら、胎児が参加していなかった遺産分割協議には意味がなくなってしまいます。
そのため実務的には、胎児が産まれるのを待ってから遺産分割協議をする必要があります。
合わせて読みたい:遺産分割協議の参加方法は?全員集合の必要性・注意点を行政書士が解説!
しかし、さすがに生まれたばかりの子に、遺産分割協議の内容を理解してそれに同意をするというのは無理でしょう。
遺産分割協議書には署名と押印が必要ですが、それも生まれたばかりではすることは間違いなくできません。
そのため遺産分割協議には、その子の代理人が参加することになります。
通常、未成年の子の代理人は親が努めますが、生まれたばかりの子の親が、その子の代理人になることは多くの場合できません。
なぜなら、親自身も相続人となっているかもしれないためです。
子と親は共に相続人となることがあり、その状態で親が子を代理すると、親の都合がよいようにすべてを決めることができてしまいます。これを利益相反行為といいます。
胎児が遺産分割協議に関与してくる場合にはやはり、この代理人の問題が大きいといえます。
ですから家庭裁判所に中立の立場の特別代理人というものを請求することが一般的です。
合わせて読みたい:遺産分割協議に親は子の代理人になれる?相続における利益相反と対処法を行政書士が解説!
相続時に胎児が関係するときの留意点
相続時に胎児が存在する場合に気を留めておくべきポイントはまだあります。
- 胎児も相続放棄ができる
- 遺言書で胎児に財産を遺すこともできる
- 相続税は胎児をいったん除外して計算する
- 胎児も相続登記することができる(生まれてからの登記でもいい)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
胎児も相続放棄ができる
相続権がある以上、胎児も相続放棄をすることができます。
ただし、胎児は財産内容を理解できないからといって、代理人が勝手に相続放棄をすると、利益相反行為に該当してしまう可能性があります。
そのため胎児の相続放棄が必要ならば、特別代理人を呼ぶことにしましょう。
合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!
遺言書で胎児に財産を遺すこともできる
最初の方でも書きましたが、胎児は遺言書で財産を受け取ることができます。しかしそれは「胎児が無事産まれたら」という条件つきで効力があるため、死産だった場合は無効になってしまいます。
無効になった財産は、遺産分割協議で誰のものかを決めることになります。もし、不要な遺産分割協議をさせたくないのなら、万が一胎児が無事に産まれなかったことも想定した予備的条項を備えた遺言にした方が確実だと思います。
長岡行政書士事務所では胎児がかかわる遺言書作成もサポートしているため、もしお悩みでしたらご相談ください。
遺言書の作成なら
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
合わせて読みたい:予備的遺言って何?その性格と注意点を行政書士が分かりやすく解説!
相続税は胎児をいったん除外して計算する
相続税に関しては、いったん胎児のことを除外して計算することになります。
そして胎児が産まれたあと、相続税修正の申告を行う、ということになります。
合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除についても行政書士が解説
胎児も相続登記することができる(生まれてからの登記でもいい)
現在の制度では不動産を相続した場合、それを登記しなければなりません。まだ正式な名前も決まっていない胎児が登記をすることができるのか、という疑問もあるかもしれませんが、実はこれも仮の名前ですることができます。
しかし実際に胎児が産まれて、名前が決まったあとには登記の変更が必要になります。手間がかかってしまうため、不動産の登記は産まれてから行ってもいいかもしれませんね。
登記も相続によって不動産取得を知ったときから3年以内ですので、少なくとも胎児が産まれるまでは待っていてもよいかもしれません。
胎児がいる相続は行政書士にご相談ください
それでは胎児の関わる相続についておさらいしていきましょう。
まず、胎児は原則的には産まれるまでは権利能力はないが、一定の場合には権利能力があるものとみなされています。
相続、遺言の受遺者、損害賠償などです。
つまり胎児も相続できます。
ただし、胎児が関わる相続で一番の問題点は、遺産分割協議における代理人の選任となると思います。
例えば、夫が死亡して、母とお腹の中にいる胎児のふたりが相続人となったとします。のちに母が胎児の代理人となったら、実質的に母が相続のことをすべて決めることができるようになってしまいます。
こういった独特の問題を抱えることになり、自己判断で進めると遺産分割協議などの相続における意思表示が無効になってしまう可能性もあります。
これは利益相反にならないか、ということを頭の片隅にいれて行動する必要が生じてしまいます。
とはいえ、そのようにいちいち細かなところまで配慮して相続手続きを進めていくのは大変でしょう。
相続の専門家であれば注意すべきポイントがわかっていますし、迅速に解決することができます。
横浜市の長岡行政書士事務所は、印鑑1本で相続手続きの完了を目指しています。初回相談は無料なので、ご不安な方はLINEや電話で来所予約の後、お気軽にご相談ください。