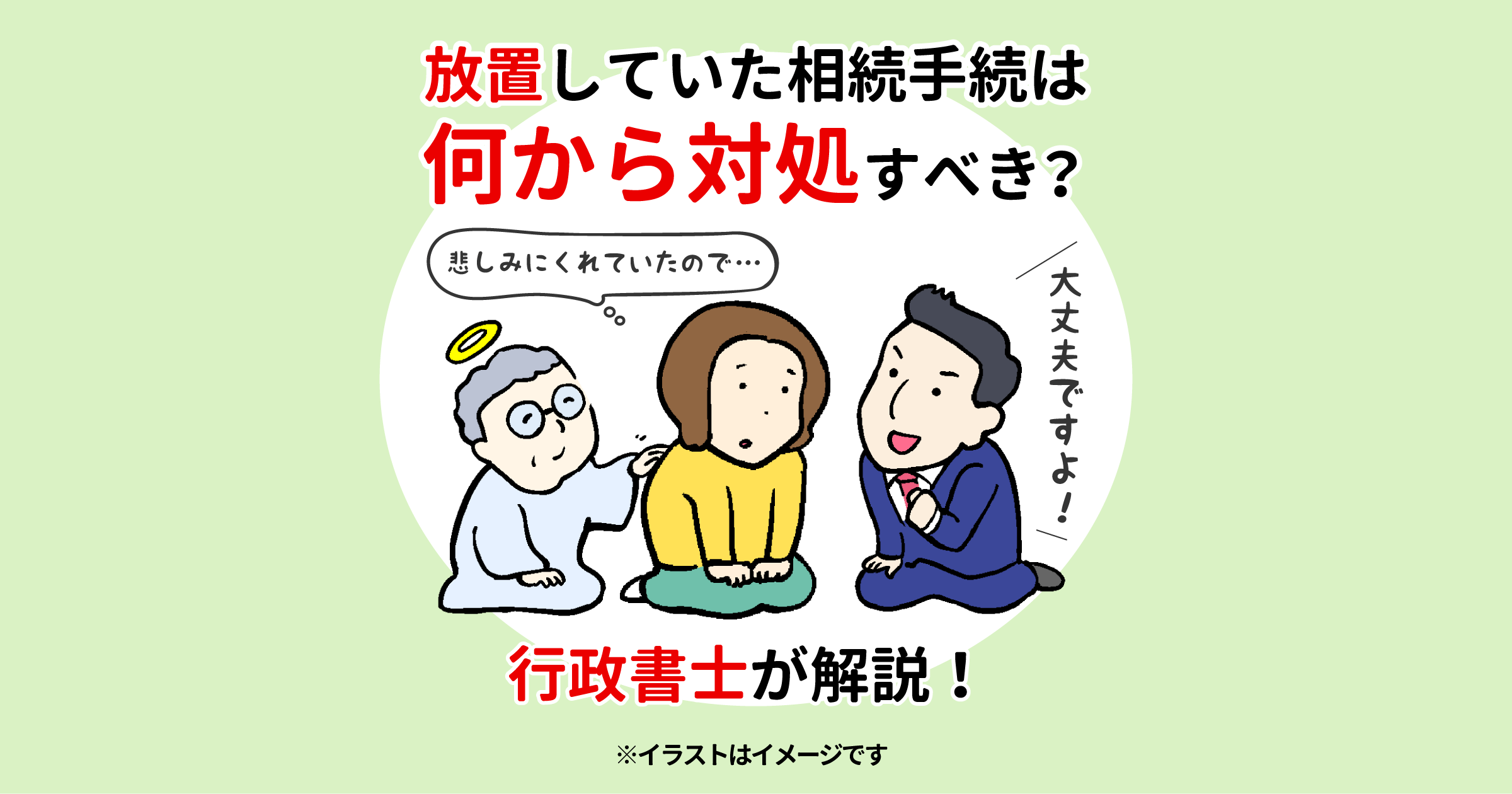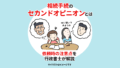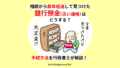親や配偶者など大切な人が亡くなった後、悲しみや生活の変化の中で、つい後回しになってしまうのが「相続手続き」です。
「大切な人が亡くなって気づいたら数年が経っていた」「不動産の名義がそのままになっている」「遺産分割協議をしていない」——こうした声は珍しくありません。
相続手続きを長期間放置してしまったとしても、諦める必要はありません。今からでも対応できる方法はあります。
この記事では、相続手続きを放置していた場合のリスクや対処法、実際に今から手続きを進めるステップを詳しく解説します。
相続手続を放置することによる問題
さて、そもそも相続手続を放置することで、どのような問題が生じるのでしょうか。主なリスクとしては、次の5点が挙げられます。
- 相続放棄や限定承認ができなくなる
- 不動産の売却・担保設定・建て替えなどができない
- 相続税の申告期限に遅れてしまう
- 相続人や関係者が増える可能性がある
- 相続登記義務化による罰則を受ける
まずは、放置のリスクを知っておきましょう。
相続放棄や限定承認ができなくなる
原則として、相続放棄や限定承認は「相続を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
ただし、財産の存在に長期間気づかなかったなどの「正当な理由」があれば、期限を過ぎても認められる可能性があります。
不動産の売却・担保設定・建て替えなどができない
例えば、親名義の家をそのままにして住み続けていると、法律上は「他人の土地に住んでいる」状態になっているため、不動産の売却・担保設定・建て替えなどができません。
相続税の申告期限に遅れてしまう
相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、最寄りの金融機関又は所轄税務署に納めなくてはいけません。これを過ぎてしまうと罰則が科せられてしまうことがあります。
関連記事:遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!
相続人や関係者が増える可能性がある
相続人の1人が亡くなると、さらにその子や配偶者などが新たな相続人になる可能性があります。
この場合、増えてしまった相続人も含めて遺産分割協議をしなければなりません。
関連記事:遺産分割協議の参加方法は?全員集合の必要性・注意点を行政書士が解説!
関係者が増えるほど協議が複雑化し、合意形成が困難になるおそれがあります。
相続登記義務化による罰則を受ける
2024年4月の法改正により、不動産の相続登記が義務化されました。遺産分割が未了でも、相続を知ってから3年以内に登記をしないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
関連記事:相続不動産の相続登記期限はいつまで?法改正による相続登記義務化について解説!
放置した相続手続きを再開するための6ステップ
それでは、今からでも放置していた相続手続きを始めるための具体的な流れを見ていきましょう。
- 相続の事実と時期を確認する
- 相続人を確定する
- 遺言書の有無を確認する
- 相続財産を調査する
- 遺産分割協議を行う
- 名義変更手続きを行う
それぞれのステップごと、詳しく解説します。
相続の事実と時期を確認する
まずは、①誰が、②いつ亡くなったのかを正確に把握しましょう。
死亡届や除籍謄本で死亡日を確認し、その時点からどれだけ時間が経っているかを知ることが第一歩です。
関連記事:相続で戸籍はどこまで必要?行政書士が戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本について解説!
相続人を確定する
相続人を調べるには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式を収集する必要があります。相続人には配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが該当しますが、状況により異なるため、戸籍を基に正確に確定しましょう。
そこから、各相続人の戸籍(被相続人の場合と異なり、現在の戸籍のみ)と住民票を集めましょう。
被相続人の戸籍一式を準備する時は、「いつからいつまでのものか」分かりやすく把握するために付箋やメモで日付を入れておくとよいでしょう。
関連記事:相続人はどう確定する?調査方法や広域交付制度の活用方法を行政書士が紹介!
なお、自分で相続人を調査することが大変で、相続手続を放置してしまっていた場合には、行政書士などの専門家に調査してもらうほうが安心でしょう。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続人調査を承っております。
相続人調査のお悩みも
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
遺言書の有無を確認する
遺言書があれば、相続内容は大きく変わります。自宅や銀行の貸金庫、公証役場などを確認しましょう。
遺言書が見つかった場合、自筆証書遺言なら家庭裁判所での「検認」が必要です(公正証書遺言なら不要)。
※「検認」とは、遺言書の保管者又は相続人が遺言の存在や内容を家庭裁判所が確認し、相続人に知らせることをいいます。
相続財産を調査する
相続対象となる財産には、以下のようなものがあります
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 車や骨董品などの動産
- 借金、ローンなどの債務
プラスの財産(不動産や預貯金などの経済的価値のあるもの)だけでなくマイナスの財産(借金や債務)も相続の対象になるため、財産目録を作成しておくと、協議や税申告の際に便利です。
関連記事:相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!
また、これらの相続財産を自分で把握するのが難しく、相続手続が進まなかったという方もいるかもしれません。そのような場合、財産調査も行政書士などの専門家に依頼可能です。もちろん横浜市の長岡行政書士事務所でも財産調査を承っております。
相続財産調査のお悩みも
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
遺産分割協議を行う
遺言がない場合は、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議を行う必要があります。
協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印を押印、印鑑証明書も用意します。長期間放置していた場合、すでに相続人の一部が亡くなっていることもあり、その相続人の相続人(代襲相続人)を含めて協議をしなければならない場合もあります。
遺産分割協議に誰が参加すべきなのか、遺産分割協議書はどのように作ったらいいのか分からない場合も、お気軽に長岡行政書士事務所へご相談ください。
遺産分割協議書の作成も
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
名義変更手続きを行う
協議がまとまったら、各財産の名義変更を行います。主なものは以下の通りです:
不動産の相続登記(法務局で手続き)
先ほど説明した通り、相続登記が義務化されたため、遺産分割が決まっていない場合は、「法定相続登記」や「相続人申告登記」という簡易的な方法でもとりあえず登記義務を果たすことができます。
銀行預金の解約・払い戻し
各金融機関で必要書類が異なりますが、基本的には、①遺産分割協議書②戸籍③印鑑証明書などが必要です。
関連記事:預貯金口座(銀行口座)の相続手続き方法を行政書士が解説!
株式・証券の名義変更
株式や証券について、被相続人がどこに保有しているのか調べなくてはいけません。そんな時は、「証券保管振替機構(ほふり)」に問い合わせることで株式の保有先を確認することができます。
そして、株式の保有先を特定ができたとしても保有先によって手続き先が異なるので注意が必要です。
上場株式の名義変更の場合は、証券会社で名義変更を行います。相続人がすでに証券口座を持っている場合には、その口座に株式を移管しますが、持っていない場合は新たに口座を開設しなくてはなりません。
非上場株式の名義変更の場合は、株式を発行した会社に対して直接手続きを依頼します。
これらの必要書類は①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本②相続人全員の戸籍謄本③遺産分割協議書④相続人の印鑑証明書⑤株式名義書換請求書などがあります。
関連記事:株式相続の注意点|証券会社と信託銀行の違いや活用方法を行政書士が解説!
長岡行政書士事務所に相続手続をご依頼いただいた場合には、これら面倒な相続手続を印鑑1本で丸投げしていただけます。
私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたしますので、安心してお任せください。
放置していた相続手続も行政書士に相談できる!
相続手続きを放置していたとしても、諦めてはいけません。
重要なのは、事実を整理し、今何をすべきかを把握したうえで正しいステップで進めることです。まずは戸籍と財産の調査から始め、状況に応じて遺産分割や登記、税務手続へと進みましょう。
「そうはいっても、どうしたらいいかわからない」という方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。面倒な相続手続を印鑑1本で丸投げしていただけますし、初回相談は無料で対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。