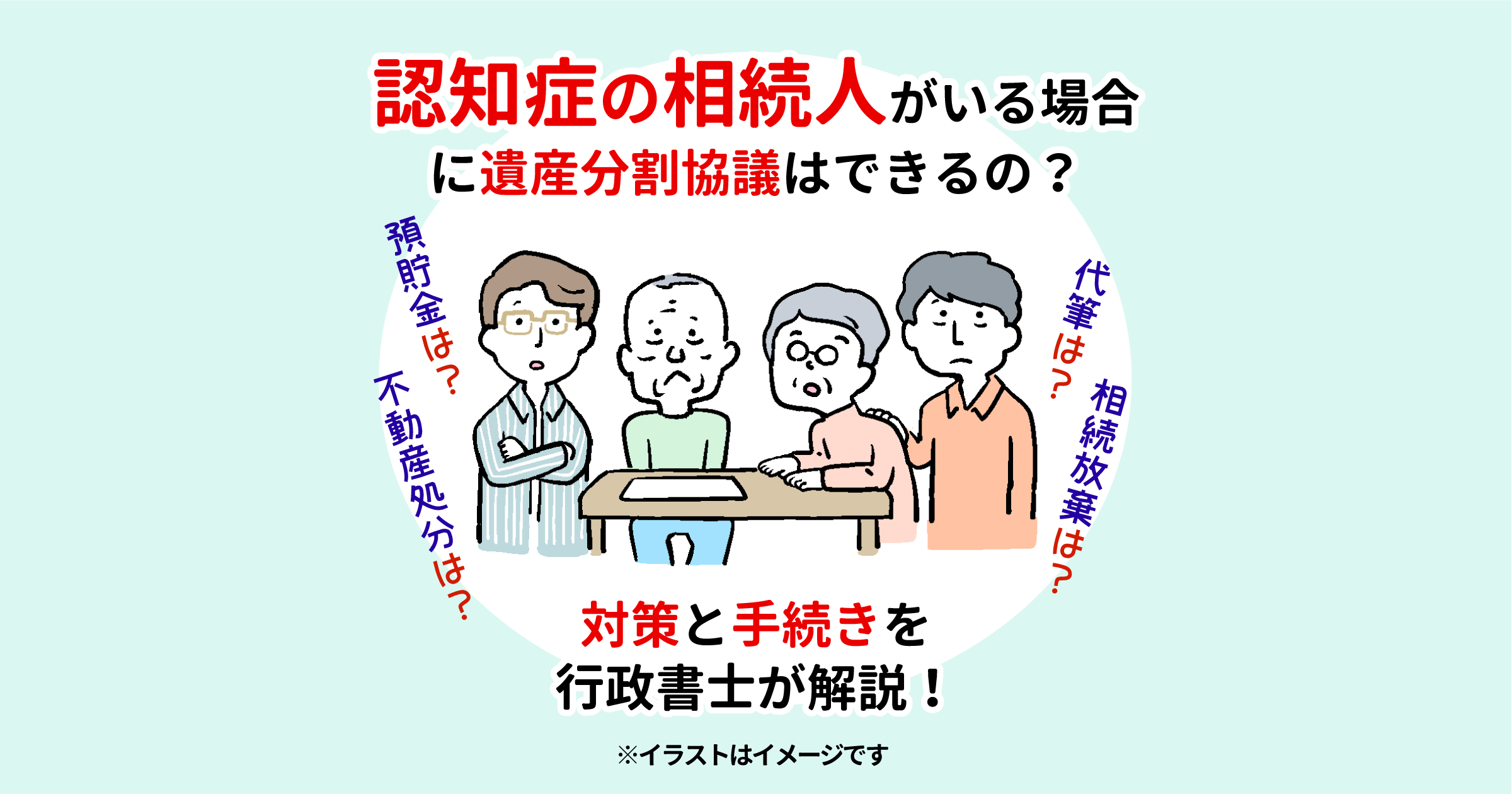先日父が余命宣告をされ、病床に伏しているため、父の代わりに私が相談に参りました。
仮に父が亡くなった場合、認知症と診断を受けている母と、私と弟の3人が相続人となるはずです。
認知症の場合、法的な手続きができないと父は聞いた事があるそうで、心配しています。
相続人の中に認知症の人がいた場合、相続手続きは問題なくできるのでしょうか?
もしできないことがある場合に、父が存命の間に対策できることはありますか?

今回のご相談は、お父様の相続人となるお母様が認知症を患っていらっしゃる場合に、できない相続手続きがあるのか、また生前にできる対策はあるか?といったご相談でした。
認知症の方がいらっしゃる場合、大きな問題として”遺産分割協議ができないこと”が挙げられます。
今回は認知症がの方がいらっしゃる場合に、遺産分割協議ができない理由やその問題点、事前にできる対策や手続きについてご説明します。
相続人が認知症だと遺産分割協議ができない可能性がある
人がお亡くなりになると、死亡届の提出や葬儀、お墓の手配に始まり、故人が残した相続財産をどのように分けるか決めるための遺産分割協議や不動産があれば相続登記手続きなど多くの手続きが必要となります。
これだけでも多くの手続きが必要なことがわかりますね。
この中でも大切な手続きが遺産分割協議です。
遺産分割協議は、故人の相続財産を誰がどのように引き継いでいくかということを決定する大切な話し合いです。
遺産分割協議について、詳しくは以下のリンクをご参照ください。
合わせて読みたい:遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
しかし、相続人が認知症であり、本人の判断能力が不十分であると判断された場合、遺産分割協議を行うはできません。
遺産分割協議が成立するためには、共同相続人全員の同意が必要となることが法律で定められております(民法970条の1)。つまり、相続人全員の同意がない遺産分割協議は、法律上無効とされてしまう可能性があります。
認知症の方は判断能力が低下している恐れがあり、遺産分割協議に必要となる意思表示ができないかもしれません。
仮に判断能力がない相続人が参加した場合、遺産分割協議に必要となる『相続人全員の同意』が成立せず、協議そのものが成立しないことになります。
認知症の相続人がいるときの注意点
認知症の相続人がいるときは、とくに次の点に注意してください。
- 勝手に代筆してはならない
- 相続放棄や限定承認もできない
それぞれ詳しく解説します。
勝手に代筆してはならない
相続人の中に認知症の方がいて遺産分割協議ができず困っているからといって、遺産分割協議書へ他の相続人が署名した場合、私文書偽造の罪に問われる可能性があります
もちろん、偽造した遺産分割協議は無効となります。
いかに困っているからといっても、勝手に代筆してしまうと、知らず知らず犯罪に手を染めてしまう可能性があり、注意が必要です。
相続放棄や限定承認もできない
もし、認知症の相続人がいた場合、『その人に相続放棄をさせれば解決では?』と思われるかもしれません。
しかし、認知症になってしまうと正常な判断能力ができない考えられ、判断能力を必要とする法律行為ができなくなってしまいます。
したがって、相続人が認知症の場合、『相続放棄』や『限定承認』などの行為をすることもできません。
これらの行為も遺産分割協議と同様に、判断能力が必要な法律行為であるためです。
また、本人の意思がないまま他の相続人等が代理人として相続放棄を申し立てても無効となってしまうため注意が必要です。
合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!
認知症により遺産分割協議ができない場合の問題点
ここまで、認知症の相続人ができない相続手続きを見てきました。
では、遺産分割協議ができないと何が困るのでしょうか?
相続人が認知症なら、遺産分割協議などせずに、そのままにしておけばいいと思うかもしれません。
相続についての知識がある方なら、法定相続分にしたがって相続すればいいと考えるかもしれませんね。(法定相続分に従うなら遺産分割協議は不要です)
遺産分割協議ができないと以下の点が問題となります。
- 法定相続分での共同相続ことになる
- 不動産の処分や売却ができなくなる
- 相続した預金の名義変更や引き出しができなくなる
以下で詳しく解説していきます。
法定相続分で共同相続することになる
遺産分割協議を行わない場合、法定相続人による法定相続分での相続をする可能性を探ることになります。
『法定相続分で分けるならば、法律で決まっていることだから異議を唱えることもできないし、大変な話し合いをして揉めるよりもよっぽど円満な手続きができる!』と思われますよね。
しかし!実際には多くの問題があります。
通常、遺産分割協議を行えば、誰が何を相続するのかを決定する事ができます。
遺産分割協議の場では、誰が何を欲しいあるいは欲しくないということを主張し、それぞれの相続人にとって望ましい相続をすることができます。
各相続人の事情を考慮せずに法定相続分で相続手続きを進めると、納得できない相続人が不満を抱えることになるかもしれないため注意してください。
不動産の処分や売却ができなくなる
遺産分割協議ができない場合、金銭のように明確に価値が判断でき、簡単に分けられるものであれば分割して相続できます。
しかし土地や建物などの不動産といった高価な物の価値は明確に判断する事ができませんし、物理的に分けることができません。そのため、相続人で共有して所有することになります。
不動産が相続人同士の共有の持ち物となった場合、当該財産を売却するなど動かしたいと思った際には「共有している相続人全員の同意」が必要となるため、手間が増えたりトラブルとなるおそれがあります。
相続財産である不動産などの財産が、複数の人の共有状態にある場合について定められた条文を確認しておきたいと思います。
民法251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
この条文では、共有物に物理的に変更を加える行為をする場合、他の共有者の同意を得る必要があるということだ定められています。
例えば、共有となっている相続財産が不動産であった場合、売却することはもちろん、賃貸や大規模な修繕が必要となった場合にも共有している全員の同意がなければできません。
合わせて読みたい>>不動産の共有相続のリスクとは?メリット・デメリットと注意点を行政書士が解説!
相続登記ができない
また、不動産については不動産登記ができないという問題もあります。
相続登記がなされないことによって「所有者不明土地」が増加するという問題を解消するために、これまで任意だった不動産の相続登記が令和6年4月1日以降は義務化されることになりました。
参照:備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!法務民事局
相続登記を行う際には、遺産分割協議の提出が求められるため、相続人が認知症で遺産分割協議ができなければ相続登記ができません。(法定相続の登記は単独で登記可能です)
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる場合もあります。
もっとも、金銭的な罰金問題だけでなく相続登記をせず放置をした場合、時間が経てば経つほど手続きは煩雑になりトラブルの元となる可能性があります。
共有状態を放置しておくと、相続登記ができず相続人間のトラブルに発展する可能性があることはもちろん、上記の通り不動産の売却や処分ができないといった凍結状態となってしまいます。
一定額を超える預貯金の引き出しができなくなる
通常、口座の名義人が亡くなったことを銀行が知ると、預金口座が凍結されてしまいます。
相続人の方が手続きをするために銀行に連絡をしたタイミングで、口座名義人の死亡を銀行が知り、口座が凍結されてしまうというのが一般的です。
預金口座は相続手続きが完了するまで凍結されてしまいます。
そして、遺産分割協議ができなければ自分の法定相続分だけを請求するということはできません。
誰かが相続された預貯金を使い込むことを防止するためであり、預貯金を引き出すためには遺産分割協議書を求められる事が一般的です。
なお、”150万円”または”当該銀行にある預貯金×3分の1×法定相続分”のどちらか少ないがくまでであれば払い戻しができます。
これは、”預貯金の仮払い制度”と呼ばれ、葬儀費用などの負担を軽減することを目的としています。
合わせて読みたい:口座凍結のタイミングはいつ?相続発生後の死亡届と銀行凍結の関係について行政書士が解説!
認知症の相続人がいても「成年後見制度」を利用すれば遺産分割協議が可能
認知症の相続人がいて、判断能力が不十分な場合でも遺産分割協議をおこなうには”成年後見制度”を利用する方法があります。
以下で成年後見制度の概要や、利用時の注意点についてご説明します。
成年後見制度とは
成年後見制度には、”法定後見制度”と”任意後見制度”の2種類があります。
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
一方、任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が本人に代わって委任された内容を行う制度です。
合わせて読みたい:高齢者を法律で守る委任契約・任意後見制度・遺言執行者について行政書士が解説!
相続開始時にすでに相続人が認知症であった場合は”法定後見制度”を利用することになるかと思います。
法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人を選任し、後見内容を決定します。
その審判が下り、所定の手続きを経ると、成年後見人による本人の財産や日常生活の支援などが開始され、同時に遺産分割協議も行えるようになります。
後見制度を利用することで遺産分割協議の問題も解消され、さらに本人の支援もしてもらえるなんていいことばかり!と思われるかもしれませんが、意外とそうでもありません。
成年後見制度を活用するときの注意点
一見メリットがあるように見える成年後見制度にもデメリットがあります。
- 成年後見の申立てから後見開始までに手間や時間がかかる
- 柔軟な遺産分割協議ができない可能性がある
- 被後見人(本人)が亡くなるまで続く
- 後見人への報酬が発生する
- 相続人となる親族が成年後見人になった場合は特別代理人の選任が必要
成年後見制度のデメリットについて、以下で詳しくご説明します。
成年後見人の申立てから後見開始までに手間や時間がかかる
まず、申立てから後見開始までには通常1〜2ヶ月かかると言われており、状況次第では3〜4ヶ月、それ以上もかかるケースもあるため遺産分割協議が早急にできないと言えます。
柔軟な遺産分割協議ができない可能性がある
成年後見人が決定されたとしても遺産分割協議では自由な分割はできない可能性があります。
なぜなら、成年後見人の任務は本人の財産や権利を保護することになるからです。
したがって、遺産分割協議において相続人それぞれの事情を考慮した柔軟な分割は難しいかもしれません。
被後見人が亡くなるまで続く
遺産分割協議をすることを目的として成年後見制度を利用したとしても、成年後見制度は被成年後見人、つまり認知症と診断された相続人であるご本人がお亡くなりになるまで続きます。
つまり、一度後見が始まってしまうと後見人は遺産分割協議に限らず、本人の日常生活や契約行為に関する代理権を持つことになり、被相続人が相続した財産はもちろん、すべての財産について成年後見人が管理することになるため、自由に財産を使うことができなくなる危険性もあります。
後見人への報酬が発生する
法定後見制度を利用する場合、誰が後見人となるかは家庭裁判所が決定します。
家族を成年後見人に指定したとしても外部の弁護士などが選任される可能性もあります。
その場合、成年後見人に対する報酬を支払う必要があります。
相続人となる親族が成年後見人になった場合は特別代理人の選任が必要
成年後見制度では外部の専門家が選ばれる事が多いようですが、申し立ての際に子や兄弟などの親戚が後見人として選任される場合もあります。
ただし、成年後見人である親族が共同相続人であった場合、その親族は自分の相続分の話し合いをしながら被成年後見人の相続分の話し合いをすることはできないため注意が必要です。
成年後見人が同時に遺産分割協議に参加することは利益相反行為になるためです。
合わせて読みたい:遺産分割協議に親は子の代理人になれる?相続における利益相反と対処法を行政書士が解説!
成年後見人である立場と、自らが相続人である立場とが重複してしまうため、成年後見人の利益を守る役割を果たす事ができないためと言われています。
このように利益相反行為となってしまう人が成年後見人となった場合、利益の相反しない第三者を”特別代理人”として選任して遺産分割協議を行う必要があります。
認知症の相続人がいる場合にあらかじめできる生前対策
認知症の相続人がいる場合、成年後見制度を利用して後見人をつける、あるいは特別代理人を選任することで遺産分割協議をする事ができます。
一方で、成年後見制度はデメリットも多く存在します。
そこで最も得策といえるのは、生前対策を取ること!
残される認知症のご家族はもちろん、残された相続人等が困らないよう事前にできる対策をご紹介します。
遺言書を作成する
有効な対策の1つは”遺言書を作成すること”です。
遺言書を作成し、本人が亡くなった後に遺産を誰がどのように相続するのかについて指定しておくことで遺産分割協議をする事なく、不動産や預貯金について凍結を解除し相続手続きをすることができます。
遺産分割協議が不要となれば、相続人に認知症の方がいたとしても相続人間でトラブルにならない限り、遺言書の通りに財産を承継することができます。
ただし、遺言書的なものであればなんでもいいわけではありません。きちんとルールに則った有効な遺言書でなければなりません。
長岡行政書士事務所では遺言書の作成についてもサポートしているため、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。
合わせて読みたい:認知症の家族がいた場合の相続はどうなるの?その対処法について行政書士が解説!
生前贈与をする
不動産や預貯金などの財産を生前贈与することも対策の一つといえるでしょう。
生前贈与についてもデメリットがないわけではありません。
実施する際は税金関係で注意しなければならないこともあるため、税理士に相談したほうがいいでしょう。
長岡行政書士事務所では、提携する税理士事務所を紹介することも可能です。
合わせて読みたい:生前贈与は相続財産の対象になる?特別受益と持ち戻し免除について行政書士が解説
相続人に認知症の方がいるときの手続きも行政書士に相談できる
ご家族に認知症の方がいらっしゃるような場合、様々なご不安があると思います。
この記事で紹介した「成年後見制度」についても、認知症の方を保護をできる反面、時間やコストなど、様々なデメリットがあるという事が従来より指摘されてきました。そこで、成年後見制度は以下のように見直しに向けた検討が行われているようです。
- 本人にとって適切な時機に必要な範囲・期間で利用できるようにする
- 一度決定したら終身的なサポートではなく更新制度にする
- 本人が必要とする保護や意思決定支援の内容やその変化に応じて後見人を円滑に交代できるようにする
現在の成年後見制度はご本人はもちろん、親族の方にとっても負担が少ないとは言えません。成年後見制度をより利用しやすい制度にし、多くの人に利用してもらう事ができるように法改正が検討されています。
ただし成年後見制度の法改正は具体的に法改正が決定されているわけではありません。現状の基本方針としては、2026年に民法改正案を国会に提出する予定で動いているようですので、今後の改正が期待されます。
いま現在、相続人の中に認知症の方がいて困っている方は、まずは相続手続きに詳しい専門家に相談してみてください。横浜市の長岡行政書士事務所でも、後見制度や相続手続きに多々対応しているため、最適な方法をアドバイスいたします。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。