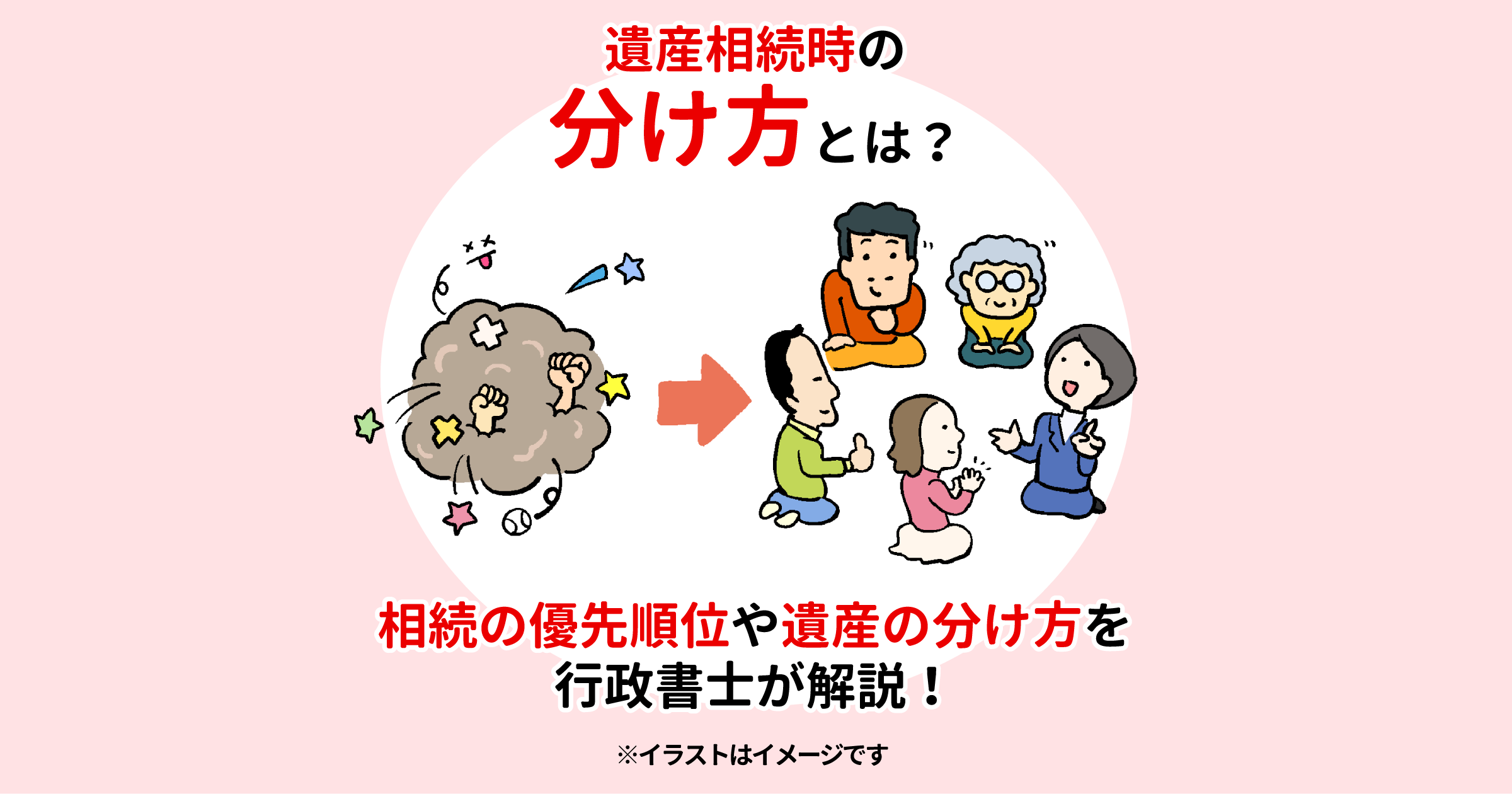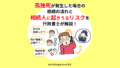「父が亡くなり、遺産を相続人3人で分けるが、どのように分けたらいいの?」
「遺産を分ける目安はあるのか知りたい」
「安全に遺産分割するためには、何を大事にするべきかヒントが欲しい」
ご家族が亡くなり相続が開始されたら、遺産を相続人の間で分けることになります。では、遺産を分ける際にはどのように進めていけば良いでしょうか。そもそも遺産は、自由に分けることができるのでしょうか。
この記事では横浜市で遺産相続手続をサポートしている行政書士が、遺産分割のルールや分け方について詳しく解説します。
遺産の分け方は遺言書の有無によって変わる
大切なご家族(以下 被相続人)が亡くなり相続が開始されたら、被相続人が所有していた相続財産を相続人間でどのように分けるのか決める必要があります。
では、遺産分割の進め方・分け方にはどのような方法があるでしょうか。
遺産分割は「遺言書の有無」によって進め方が異なりますので、この章でわかりやすく解説します。
遺言書がある場合
被相続人が遺言書を残している場合、遺言書の記載内容に沿って相続財産を分けていきます。
遺言書には主に以下の3つの種類があり、被相続人が残した遺言書の種類によって必要な手続が異なります。見つかった遺言書に合わせて必要手続を進めましょう。
| 自筆証書遺言 | 被相続人が自筆・保管していた遺言書。 家庭裁判所で検認してもらう必要がある。 無効の遺言書も多いため要注意 (法務局で保管される自筆証書遺言書保管制度の利用なら検認不要) |
| 公正証書遺言 | 家庭裁判所の検認不要、原本は公証役場に保管されている。 無効の可能性が低く、遺産分割しやすい |
| 秘密証書遺言 | 家庭裁判所の検認必要、公証役場では保管せず本人保管であるが、作成記録は公証役場に記録されている。 |
合わせて読みたい:公正証書遺言と自筆証書遺言の2通を見つけたら相続はどうなる?注意点を行政書士が解説!
なお、基本的には遺言書に沿って相続手続を進める必要がありますが、例外もあります。
次のような場合には、遺言書があったとしても、遺産分割協議をすることも可能です。
- 遺言書に一部の遺産についてのみ記載されている場合
- 遺言によって遺産分割が禁止されておらず相続人・受遺者・遺言執行者の同意がある場合
関連記事:遺言がある場合の遺産分割協議はどうすればいい?手続き方法や注意点を行政書士が解説
遺言書がない場合
もし遺言書がない場合は、法定相続分に従って分けるか、遺産分割協議を行って相続財産の分け方を決めます。
法定相続分とは、民法で定められた、各相続人の相続割合のことです。
| 法定相続人の構成 | 法定相続分 |
| 配偶者&子や孫 (直系卑属) | 配偶者:2分の1子や孫(全員で):2分の1 |
| 配偶者&親や祖父母(直系尊属) | 配偶者:3分の2親や祖父母(全員で):3分の1 |
| 配偶者&兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3兄弟姉妹(全員で):4分の1 |
■法定相続人の順位
・常に相続人 配偶者
・第1順位 子や孫(直系卑属)
・第2順位 親や祖父母(直系尊属)
・第3順位 兄弟姉妹
合わせて読みたい:遺産分割協議書は法定相続分どおりの相続でも作るべき?不要・必要なケースを行政書士が解説!
法定相続人は上記の順位に基づいて決定します。たとえば亡くなった方に配偶者と子供がいれば、その方々のみが相続人で、後順位の兄弟姉妹などが相続人となることはありません。
なお、相続人の範囲は上記の順位に基づいて決まりますが、分割割合はあくまでも目安のひとつです。そのため相続人同士で合意すれば、法定相続分と異なる割合で財産を分割することもできます。(相続人が1名の場合は協議をせずに1人ですべての相続財産を受け取れますが、2名以上いる場合は話し合った上で分割内容を決定する必要があります)
ここまでの話しをふまえ、遺言書がない場合の遺産相続の手続は以下の4ステップです。
- 相続人調査を行い、法定相続人を確定させる
- 相続財産を確定させる(債務も含めます)
- 法定相続人全員で遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作り、決まった内容に沿って各相続人へ財産を分ける
合わせて読みたい:遺産相続の流れや期限について行政書士が解説!
遺産の分け方を決める時のポイント
さて、遺産をどのように分けるのか決める時は、次のポイントを意識してみてください。
- 遺産分割協議に参加できる人は限られている
- 財産の共有はなるべく避ける
- 法定相続分にこだわらず柔軟に協議する
- 介護・扶養で貢献した相続人へ配慮する
- 話し合いがまとまらない場合は弁護士へ相談する
- 相続手続の期限を意識して進める
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
遺産分割協議に参加できる人は限られている
遺産分割協議に参加できるのは、法定相続人のみです。たとえば、以下に該当する方は参加できません。
- 内縁の方
- 法定相続人以外の親族(たとえば相続人の配偶者など)
- 知人や友人、元配偶者など
たとえば妻が相続人となっているからといって、「妻の配偶者」が協議に参加することはできません。無用なトラブルを避けるためにも、遺産分割協議は相続人だけで実施することを意識しましょう。
なお、法定相続人が認知症などを理由に判断能力が低下している場合、その方は遺産分割協議に参加できません。代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。
合わせて読みたい:相続でよく聞く成年後見制度とは?行政書士が制度の種類と具体例を解説!
財産の共有はなるべく避ける
遺産分割が揉めていると、早く終わらせるためにも法定相続分どおりに相続するケースがあります。
この場合、不動産など物理的に分割できない財産の権利を、相続人が法定相続分に従って分割することも可能です。いわゆる「共有」という状態です。
遺産分割を進める際には、共有化を避けた方が良い財産もあります。
とえば不動産などを共有状態にしてしまうと、その後の売却・賃貸化などの手続が複雑になったり、次の相続の発生により共有者が増えてしまうことがあります。
合わせて読みたい:不動産の共有相続のリスクとは?メリット・デメリットと注意点を行政書士が解説!
財産の共有はなるべく避け、換価分割・代償分割などの方法も検討するといいでしょう。
関連記事:遺産分割時の換価分割とは|押さえておきたい4つのポイントを行政書士が解説
横浜市の長岡行政書士事務所は、清算型遺贈、換価分割等の不動産の売却が発生する相続手続もサポートしています。もし換価分割を検討している場合は、一度ご相談ください。
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
法定相続分にこだわらず柔軟に協議する
遺産分割協議は柔軟に話し合うことで円満に解決できることが多いものです。法定相続分どおりに遺産分割することもできますが、譲り合いをすることで丸くまとまることも多いでしょう。また、相続する方によって「配偶者の税額の軽減(相続税の配偶者控除)」のように相続税申告時に節税効果がある特例や控除が使えます。
財産を巡って激しい対立が生じることもありますが、以下を目安に柔軟に話し合って、家族の関係に亀裂が入らないようにまとめることがおすすめです。
| ■遺産分割を円満に進めるヒント ・円満な話し合いになるように感情的に話さない ・遺産を隠さず、すべて公開して話し合う ・交流が少ない相続人同士でも丁寧に会話する ・誰が相続すると相続税が節税できるか ・二次相続も見据えて、遺産をもらう人を決めているか |
介護・扶養で貢献した相続人へ配慮する
介護や扶養で被相続人の生前における生活を支えてくれた相続人がいる場合、他の相続人が遺産分割時に配慮をすることで、円満に遺産分割がまとまりやすくなります。
介護や扶養で相続人に貢献した方は、貢献した分(寄与分)を法定相続分に上乗せして相続財産が得られる場合があります。もしも遺産分割協議で寄与分を認めない場合、貢献した相続人が寄与分を主張して調停を申立てする可能性があります。
もちろん、調停の中で意見を交換し合うことも考えられますが、決裂すると審判に移行し遺産分割が長引いてしまうおそれがあります。協議の段階から配慮をしあうことも大切です。
合わせて読みたい:寄与分の要件とは?親の介護を相続時に考慮する方法を行政書士が解説!
話し合いがまとまらない場合は弁護士へ相談する
話し合いがどうしてもまとまらない場合は、弁護士へ相談することを検討しましょう。遺産分割の紛争については、弁護士に相談できます。遺産分割協議そのものには期限はありませんが、協議が終わらないとすべての財産が共有状態となっており、売却や収益化などの有効活用もできません。
たとえば、高い価格で売却できそうな株式も、売り時を逃してしまうおそれがあります。遅くなればなるほどデメリットは大きいため、早期の打開を目指すためにも弁護士に依頼しましょう。
合わせて読みたい:遺産分割でもめた場合は代理人が必要?行政書士が教える弁護士の選び方!
相続手続の期限を意識して進める
相続にはさまざまな期限が設けられています。期限を意識して遺産分割を進めることも大切です。主な期限は以下のとおりです。
| 相続放棄や限定承認 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内 |
| 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 相続税申告、納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 |
特に相続税申告までに遺産分割協議が終わっていないと、受けたい特例や控除が利用できなくなるおそれがあります。正しく特例や控除を受けるためには、必要書類や手続が追加されてしまうため、できる限り期限内に遺産分割を終えておくことが望ましいでしょう。
合わせて読みたい:遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!
遺産分割協議の作成・遺産相続手続は行政書士にも依頼できる
本記事では遺産の分け方・決め方について遺言書の有無や、遺産分割協議時のポイントも交えながら詳しく解説しました。
遺産分割を迎えた時、これまで仲が良かったご家族であっても財産を巡って意見が食い違うことがあります。
しかし、生前における相続人と被相続人との関係性や、二次相続、手続の期限などを意識することで円満にまとまる可能性もあります。じっくりと話し合って、できれば円満に遺産分割を進めることがおすすめです。
また、遺産の分け方を決めたら相続手続が終わるわけではありません。遺産の分け方を決めたら、それを遺産分割協議にまとめて、実際に各機関で手続を進めていく必要があります。これは手続に慣れていない方にとっては、少なからず負担になるものです。
横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書に沿った相続手続はもちろん、遺産分割協議の作成・その後の遺産相続手続についても対応しています。初回相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。