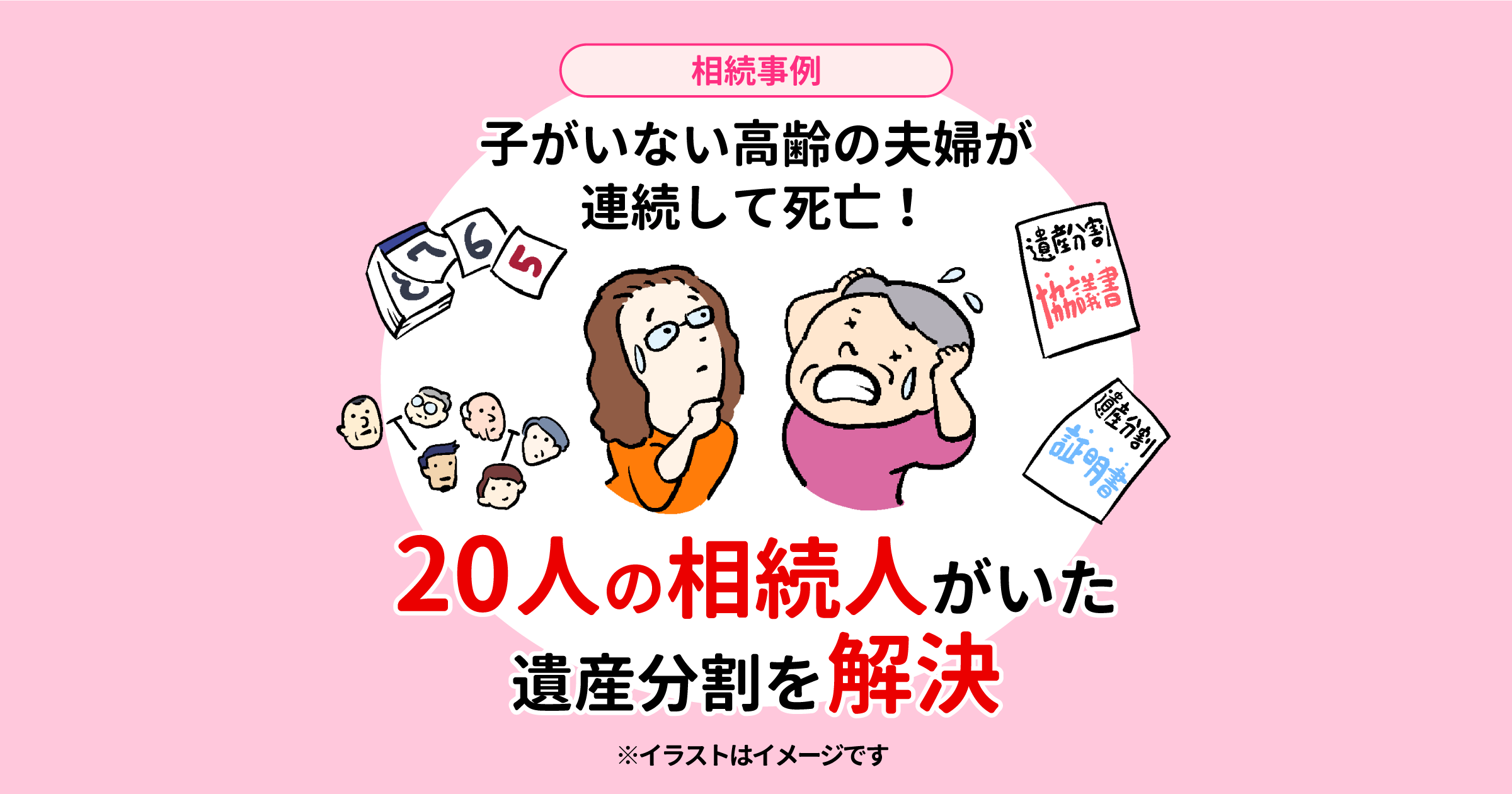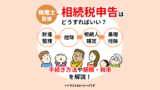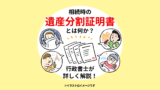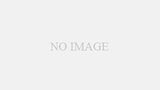「相続人が多すぎて、どのように手続きを進めたらいいのか分からない」
「相続人はどのようなケースだと増える?」
・・・
最近はビジネス誌でも相続特集が組まれていたりと、以前に比べ相続がぐっと身近なものになってきている感があります。
一昔前は「死んだ後の事を考えるなんて・・・」という漠然としたタブー感や、相続なんてお金持ちだけの悩みだという認識が社会に存在したことも否めませんが、最近流行している「終活」は立つ鳥跡を濁さずを良しとする日本人の気質に合致しているのかもしれません。
さて、相続の現場では実際にどのような事が起きているのでしょう。
書籍などで紹介されている相続の事例は簡略化されている事も多く、実際はもっと複雑な事例も少なくありません。たとえば子がいない高齢の夫婦が連続して死亡して、相続人が20人になってしまった、というケースもあります。
このように相続人が多い場合、いったいどのように相続手続を進めればいいのでしょうか。
本日は横浜で行政書士事務所を構え数々の相続のお手伝いをしてきた長岡行政書士様に、記憶に残っている実際の相続事例についてうかがってみようかと思います。
相続人が増える原因
長岡先生、本日はお忙しい中お時間割いていただき、誠にありがとうございます。
長岡行政書士(以下:長岡): いえ、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
早速ですがこれまで長岡先生が担当した相続で、特に印象深いケースはありますでしょうか。
長岡: 特に印象深い・・・ですか(苦笑) 相続自体人の生き死にに関与することですしお金も扱いますから、常に緊張感を持って臨むようにしてます。
そういった意味ではどの相続も記憶には残っているのですが、最近取り扱った案件でちょっと途方に暮れそうになったケースは特に覚えています。
相続人が20人もいる事例があったのです。
相続人が非常に多い事例でしたが、何とか相続手続を無事に完了しました。
相続人がそんなに増えてしまうこともあるんですか!どのような場合に、相続人がそれほどの大人数になってしまうのでしょうか。
長岡:相続人が増える原因としては、次のような例が挙げられます。
- 代襲相続
- 数次相続
それぞれどのようなものなのか、説明しますね。
関連記事>>>相続人の範囲はどこまで?代襲相続・数次相続・再転相続も考慮して行政書士が徹底解説!
代襲相続
たとえば奥様が亡くなった際、ご主人が配偶者として相続人になります。しかしご主人の連れ子がいた場合、もし奥様と養子縁組をしていないのであれば、連れ子は相続人にはなれません。
もし養子縁組をしていれば養子は実子と同じ権利が得られるので、ご主人の連れ子は、奥様の相続人になれます。
このようなケースで、もし奥様の実子がいないとしましょう。
子という第一順位(直系卑属)と両親という第二順位(直系尊属)がいない場合、兄弟姉妹という第三順位に相続の権利が回ってきます。 これだけでは、それほど相続人の数は増えないかもしれません。
しかし、もし兄弟姉妹が亡くなっていると、相続人の数が多くなる可能性が高いです。
法律には代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言って一つ下の代に相続の権利が飛び越える仕組みがあるんです。
子の代襲相続は子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫・・・という風にどこまでも下の代に相続が移っていきますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
よって、たとえば奥様の兄弟姉妹の子達に相続の権利が発生し、法律に則った割合で遺産を分けると、「配偶者のご主人が4分の3」「兄弟姉妹の子達全員で残りの遺産の4分の1」を分けることになります。
兄弟姉妹の子達全員で残りの4分の1を分けるという事は、例えば子が2人いたら8分の1ずつ、子が4人いたら16分の1ずつ、ということですね。
そういうことです。たとえば亡くなられた方を含めて4人いたとしましょう。相続人となる兄弟姉妹は3人です。しかし3人ともが亡くなっており、それぞれに3人ずつ子どもがいれば、甥姪9人が相続人となる、ということですね。一気に相続人の数が増えることがお分かりいただけたでしょうか。
合わせて読みたい:甥や姪が相続人になるときの注意点とは?条件や相続手続きについて行政書士が解説!
数次相続
対してご主人の相続分は4分の3・・・
でも、このケースだとすぐご主人も亡くなってしまいましたが、これが相続にどう影響があるのでしょうか。
長岡:これは法律的にいうと、「数次相続」が発生している状況といえます。
数次相続・・・聞いた事がないです。
長岡: 数次相続とは、複数の相続が同時発生している状態のことです。
遺言がない場合は相続人が全員集まって遺産の分け方を協議する「遺産分割協議」が必要になりますが、その遺産分割協議が終わらないまま他の相続人が亡くなってしまった、というようなケースがこの数次相続です。
奥様とご主人が同時に亡くなってはいない場合、一旦はご主人に4分の3が相続されたと考えます。
そしてご主人も亡くなり、ご主人の相続の相続人は自身の連れ子(ご主人にとっては実子)なので、遺産の4分の3全てをこの連れ子の方が相続することになります。
もし連れ子が複数人いれば、その子たち全員で、ご主人の相続分をさらに分割します。
ご主人一人が相続するはずだったものを、複数人の子たちで分けるわけですから、相続人が増えますね。
子がいない高齢の夫婦の相続は複雑で相続人が増えやすい
長岡: さて、ここまで紹介した基本知識をふまえると、子がいない高齢の夫婦の相続は複雑で、なおかつ相続人が増えやすいのです。
印象に残っている事例を紹介しますね。これは高齢のご夫婦のケースでして、依頼いただいたのは奥様の姪の方からでした。
ご夫婦ともども90歳を超えてらっしゃいまして。奥様が亡くなってから数か月後にご主人も後を追うように亡くなってしまわれました。 つまり「数次相続」が発生したわけです。
そして、夫婦にはお子さんはいなかったのですが、ご主人には前妻との間の連れ子がおりました。
諸々の事情もあり、奥様と再婚なされた時に、奥様とこの連れ子の方との間で養子縁組はされなかったようです。
なるほど、今後高齢化がより進むと言われていますので、もしかしたらこのようにご夫婦が続けて亡くなってしまうという事態も増えるかもしれませんね。
長岡: そうですね、増えるかと思います。
さて、今回の例では、奥様の実子がいないため、両親や兄弟姉妹が相続人となります。奥様も高齢だったこともあり、ご両親や5人いた兄弟姉妹はもう全員他界していました。
しかし、この5人いた兄弟姉妹に子が多数いて、しかも日本全国に散らばっていたのです。
更に奥様の父母は再婚で、5人の兄弟姉妹の内、2人は母が違う異母姉妹だったんです。
うーん、複雑になってきましたね。
そうなんです。ちなみに半分しか血の繋がりがない兄弟姉妹は、「半血の兄弟姉妹」と言います。そして半血の兄弟姉妹は、両親が同じ(全血)の兄弟姉妹と比べ、半分の遺産しか相続できません。
詳しく知りたい>>>半血の兄弟姉妹の相続分とは?第一順位と第三順位の時の相続の違い
ご依頼人である奥様の姪の方が困ってらっしゃったのは、そもそも誰が相続人になるのかがわからず、全部で相続人が何人いるのかわからない、また、相続の手配をどこから手を付けていいのかわからない、という事でした。
奥様の相続に何も手を付けてないうちにご主人も亡くなってしまったので、亡くなられた後のバタバタから回復しないまま次の波が来てしまった。そしてふと気が付くと、どの財産が誰に受け継がれるのかがよくわからなくなってしまったのです。
相続に慣れている方は珍しいでしょうし、2件連続で来たら余計わからなくなってしまいますよね。
長岡: そうですね。 でも、今回はむしろすぐご相談いただいたので良かった、と言えるんです。
なにしろ相続には期限があるので(相続税の申告・納付は相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヵ月以内)、もたもたしていると期限切れとなり加算税や延滞税といったペナルティが発生してしまう可能性があります。
相続人を確定させるだけでも亡くなった方(被相続人)の出生時から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本といった書類を一つ一つ取り寄せて確認していく必要があるので、あっという間に時間なんて過ぎてしまうんです。
うーん、そうなのですか。 相続は時間との戦いという側面もあるのですね。
合わせて読みたい:相続税申告はどうすればいい?手続き方法や期限・税率を解説!【税理士監修】
相続人が多い場合はどうすればいい?
長岡: 相続人が多い場合はどうすればいいのか、ポイントを紹介しますね。
- 戸籍謄本などを徹底的に調べる
- 遺産分割証明書を使用する
- 不動産は売却して現金化する
戸籍謄本などを徹底的に調べる
そもそも誰が相続人なのか確定させるためには、戸籍謄本などを徹底的に調べる必要があります。
亡くなった方(被相続人)の出生時から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本といった書類を一つ一つ取り寄せて確認していく必要があるんです。
また、兄弟姉妹が相続人になる場合は、「亡くなった人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本」も必要です。先述したとおり、半血の兄弟姉妹がいるかもしれませんからね。
さらに、その兄弟姉妹が亡くなっていたら、その代襲相続人(甥姪)も確定させなければなりません。
これらすべての情報を確定させることは非常に大変なので、我々行政書士のようなプロにお任せしてもらったほうがいいでしょうね。
相続人調査のお悩みも
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
遺産分割証明書を使用する
ところで、先ほど相続人の方々が日本全国に散らばっているとおっしゃってましたが、遺言がない場合は相続人全員の同意が必要なのですよね。 どうやって全員の同意を取り付けたのでしょうか?
長岡: そうですね、もし相続人達が近隣に住んでいて集まることが可能であれば、遺産分割協議書という書類に相続人全員の署名・押印をすれば済みます。
しかし相続人がバラバラの場所に住んでいる場合、遺産分割協議書に署名捺印をもらうのは大変です。
そこで活用できるのが「遺産分割証明書」です。遺産分割証明書では相続人ごとにそれぞれ個別の内容で書類を作成して、それぞれの相続人が署名・押印するということになります。
1枚の書類に相続人全員が署名・押印するのが「遺産分割協議書」で、書類を相続人ごとに分けて署名・押印するのが「遺産分割証明書」ということでしょうか。
長岡: その通りです。 たとえば遺産に預金と不動産があって、預金を太郎さん、不動産を次郎さんに分けるとします。
一枚の紙に「預金は太郎さんで不動産は次郎さんに分ける」と書いて、その一枚の紙に太郎さんと次郎さんが署名・捺印するのが遺産分割協議書、預金は太郎さんと書いた紙を太郎さんに送り、不動産は次郎さんと書いた紙を次郎さんに送るのが遺産分割協議書です。
どちらの方法を使う場合でも相続人間の合意が必要な点は変わりはありません。
どちらにしろ、太郎さんと次郎さんは合意してないといけないという事ですね。 わかりやすい例えでありがとうございます(笑)
合わせて読みたい:遺産分割証明書とは?遺産分割協議書との違いや作成方法を行政書士が解説!
不動産は売却して現金化する
長岡: さて、最後になりますが、不動産は売却して現金化するのもおすすめです。
先ほど紹介した事例では、預貯金以外に不動産も遺産に含まれていました。
預貯金は簡単に分割することができますが、不動産は分割できません。 なので不動産を売却して現金化して相続人の間で分割することにしました。
これを「換価分割」と言います。
詳しく知りたい>>>遺産分割時の換価分割とは|押さえておきたい4つのポイントを行政書士が解説
え、売ってしまわないといけないのですか? たしか共有という方法もあると聞いた事がありますが・・・
長岡: はい、共有してはいけない、売らないといけないという事はもちろんありません。 ただ、不動産を共有にすると将来売却するときとか、人に貸すときに共有者全員の同意が必要になってしまうのです。
相続に不満があったり、将来相続人の間で関係がこじれてしまうと、思わぬところでトラブルに発展する可能性があります。 私としては不動産の共有はお勧めしないですね。
いちいち共有者全員の同意が必要では、不便ですよね。 でも不動産を売却するのも一苦労では? 特に依頼者や相続人が高齢であったり遠隔地に住んでいると、難しのではないでしょうか。
長岡: 簡単ではないですね。 このケースでは私が不動産業者さんを見つけて担当してもらい、その地域の不動産価格に照らし合わせて適正と言える価格で売却することができました。
なんと! そんなことまで任せられるんですね!
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
相続人が多い場合は行政書士に相談!
長岡: このケースでは幸いにして相続人の方々が協力的で、各地域、各ご家族のキーパーソンになる方に合意のとりまとめを手伝ってもらったりすることができました。
合意に至った後は先ほどの遺産分割証明書をそれぞれの相続人の方に郵送し、1~2か月ですべての遺産分割証明書を揃えることができたんです。
ラッキーだったという事ですね。 トータルで何カ月くらいかかったのですか?
長岡: 約10ヵ月です、先ほどの相続の期限と照らし合わせるとギリギリでした。
各相続人に手続き終了の通知を発送し終わったあとは、依頼者様とほっと肩をなでおろしたものですよ。
やはり相続人が大人数になるような場合は、相続人調査はもちろん、相続方法についても気を使うことが多いので、行政書士などの専門家に相談していただくのが安心かと思います。
横浜市の長岡行政書士事務所も相続手続に慣れていますから、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。