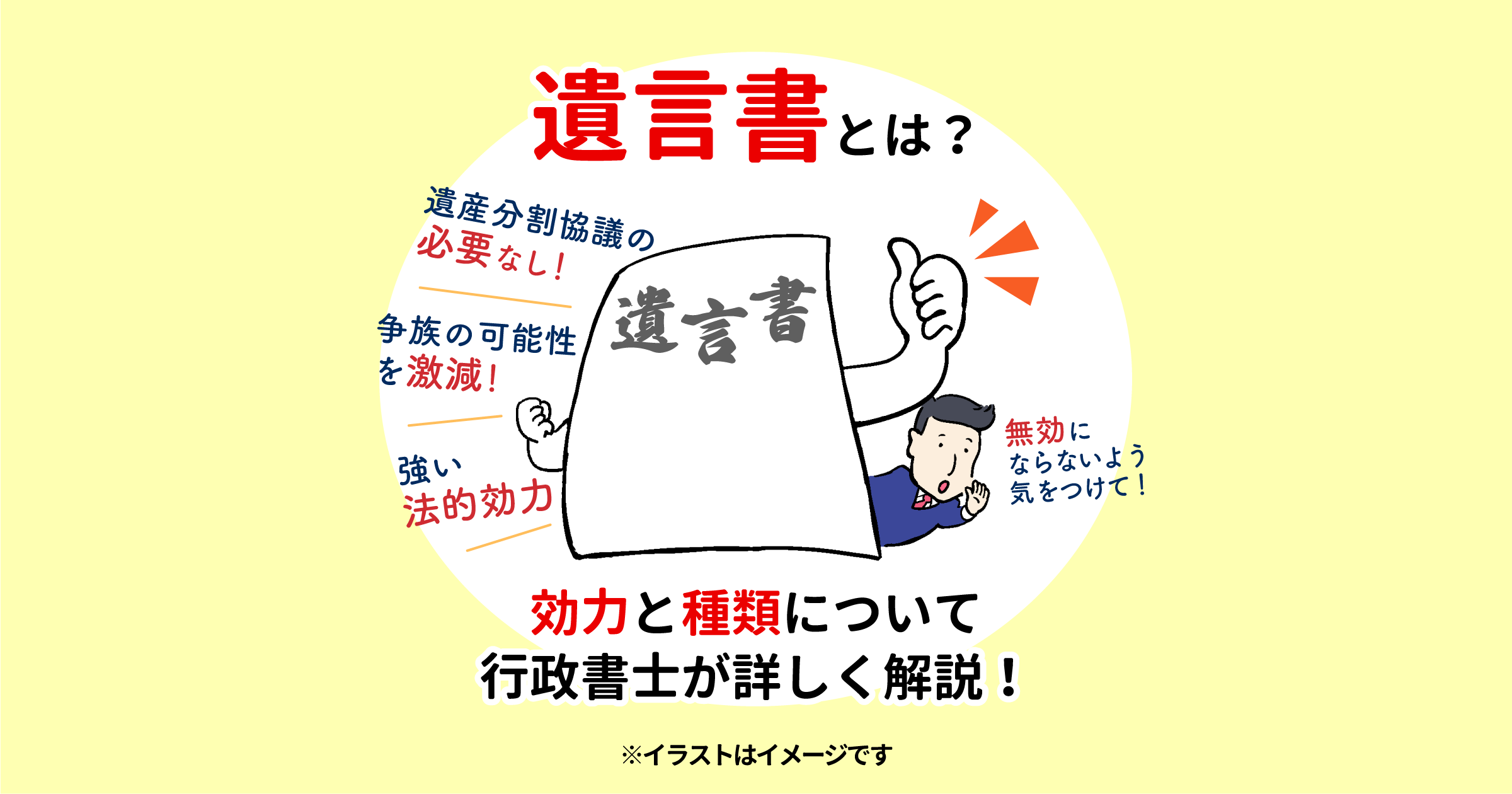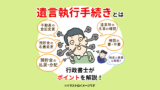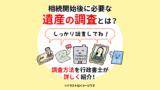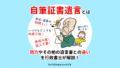「亡くなった父の遺品を整理していたら遺言書が見つかった。どうすればいい?」
「必ず遺言書に沿って相続手続を進めないといけないの?」
遺言書と相続は切っても切れない関係にあります。しかし行政書士など相続手続に日々携わっている専門家でもない限り、遺言書の効力や、手続きにおける注意点を知る機会は少ないでしょう。
そこでこの記事では、これから相続手続を進める方のために、遺言書について知っておきたいことを網羅的に紹介します。ぜひ相続手続の参考にしてみてください。
(この記事を読んでも悩みが解決しない場合には、ぜひ長岡行政書士事務所へご相談ください)
遺言書とは
遺言書とは、ご自身の死後に法定相続分以外の方法で財産を分けたい時に書き遺すものです。遺言書が無い場合、民法の定めにより法定相続人が被相続人の財産を承継します。
なお、遺言書は常に効力があるわけではありません。無効となってしまうケースもあるため注意が必要です。たとえば、以下のようなケースには注意が必要です。
・遺言の内容が読み解けない
・遺言者の氏名や押印がない、日付が無い
・共同で書かれてしまっている
・判断能力に争いがある など
合わせて読みたい:遺言書の作成能力(遺言能力)の判断基準を解説|医学判断と法律判断の違い
遺言書に記載して効力を発揮する事項
遺言書には、色んな事を記載できますが、法的な効力が認められている事項は明確に決められています。
この効力が認められることを「遺言事項」といいます。
| 遺言書の持つ効力 | 主な内容 |
| 財産に関すること | 誰に、どのような財産を分配するかなど |
| 相続人に関するもの | 相続人の廃除・廃除の取り消し |
| 身分に関するもの | 子の認知など |
| 遺言の執行に関するもの | 遺言執行者の指定など |
財産に関すること
遺言書では、誰にどの程度財産を分配するのか指示できます。法定相続分に沿う必要はありません。また、相続させたい財産の内容も決めることが可能です。
たとえば、配偶者には不動産を、子には預貯金を、などのように指定できます。また、遺産の分割の禁止(相続開始後5年以内)、遺贈に関してなども指定できます。
相続人に関するもの
遺言書では、相続人を廃除したり、廃除の取り消しを行ったりすることも可能です。
身分に関すること
また、生前に認知していなかった子を、遺言書の中で認知をしたり、未成年者に関しての後見人を指定することも可能です。また、生命保険の受取についても、遺言書の中で指示することができます。
遺言の執行に関するもの
「遺言の執行」とは遺言書を確認し、その内容通りに遺産を分配する作業のことです。
そして遺言事項を実現する役割を担う「遺言執行者」という人も、遺言書の中で指定できます。
関連記事:遺言執行者は何をやる?遺言執行手続きの進め方や注意点を行政書士が解説!
遺言書には種類がある
実は「遺言書」といっても、その作成方法によって種類が分けられています。それぞれの特徴について、一覧表にまとめてみましょう。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 作る人と作成方法 | 遺言したいご自身が自筆 | 公証人が口述を筆記 | 本人(自筆以外も可) |
| 作成する場所 | どこでも可能 | 公証役場 | どこでも可能 |
| 署名と押印 | 本人のみ 実印・認印・拇印可 | 本人・証人・公証人 本人のみ実印要 | 本人・証人・公証人 本人の印鑑は遺言書と同じものが必須 |
| 費用 | なし | 公証人手数料あり | 公証人手数料あり |
| 検認 | あり | なし | あり |
それぞれの種類について、もう少し詳しく解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご本人が財産目録以外の遺言書を手書きで作成するものです。
自筆で気軽に遺せるメリットがありますが、不備も起きやすく、裁判所での検認が必要となることも知っておく必要があります。なお、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことも可能です。
合わせて読みたい:自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!
公正証書遺言
遺言したい方が公証人役場に行き、遺言書を公証人が記述する方法を「公正証書遺言」と言います。
証人が2名必要であり、費用も発生しますが、その分無効が起きにくく裁判所の牽引も不要となるため、安全性が高い遺言書として知られています。原本は公証役場で保管されます。
合わせて読みたい:公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証人と証人2名以上に遺言書の存在は照明してもらえるものの、内容自体は秘密にしておく遺言書形式のことを指します。
遺言書の存在は知らせたいが、中身は自身が亡くなるまで誰にも知られたくない場合に使う手法です。あまり広くは利用されていません。
合わせて読みたい:内容を秘密にしながら遺言書を作りたい、公証役場で作る秘密証書遺言とは?
遺言書があると相続手続はどうなる?
さて、遺言書があると相続手続はどうなるのでしょうか。知っておきたいポイントは次の2つです。
- 遺産分割協議が不要になる
- 遺留分は請求できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議が不要になる
遺言書がある場合、原則として遺産分割協議は不要です。
合わせて読みたい:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!
たとえば、遺言書では内縁の方やボランティア団体に対して財産を分配するように指示することも可能です。法定相続人にはなれない方や団体に対しても財産の分配を指示できるため、強い効力を持ちます。
遺言書の中で財産の分配が支持されている以上、相続人が覆すことは原則としてできません。
ただし相続人以外の受遺者がおらず、相続人全員・遺言執行者が同意している場合には、遺言書と異なる遺産分割協議も可能です。
遺留分は請求できる
遺言書は強い効力があるものですが、たとえ遺言書であっても効力が及ばない部分もあります。それは「遺留分に配慮が必要」という点です。
たとえば、生前に不仲だった長男には財産を譲らず、同居してくれた長女にすべての財産を遺したい、と考える方もいるでしょう。しかし、すべての財産を長女に渡す、と書き遺した場合は長男がもらえるはずの遺留分を侵害してしまいます。
すると、長男は侵害された遺留分を求めて、長女に対して金銭を支払うように求めることができます。つまり、遺留分を侵害する内容の遺言書は作ることはできても、相続バトルが起きてしまうリスクがあるのです。
合わせて読みたい:遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!
もし自分に不利な遺言書があったとしても、遺留分を請求できることは知っておきましょう。
遺言書を見つけた場合の相続の流れ
それでは最後に、遺言書を見つけた場合の相続の流れについても見ていきましょう。
- 遺言書の検認(遺言書の種類による)
- 相続人の調査
- 相続財産調査
- 遺産分割手続き
遺言書の検認(遺言書の種類による)
もし遺言書があれば、その遺言書の指定通りに相続手続きを進めます。
記事前半で紹介したとおり遺言書には種類があり、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は裁判所に検認手続きを申し立てなければなりません。
まずは遺言書を確認し、検認が必要かどうか判断します。
あわせて読みたい>>遺言書の検認申し立てをしないとどうなる?過料や注意点、手続き方法を行政書士が解説!
※検認手続きまで、遺言書を開封することは禁止されています。「遺言書」などと書かれた封筒が見つかったら開封したくなる気持ちも分かりますが、過料の対象となるため、そのまま検認手続の準備をしましょう。
相続人の調査
先述した検認の申立てには、次のような書類が必要となります。
- 申立書(裁判所のホームページからダウンロードできます)
- 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書が封印されてない場合は遺言書のコピー
相続人全員の戸籍謄本が必要、つまり「相続人が誰なのか」を調査しなければならないのです。
たとえば故人に離婚歴があると、前の配偶者との間に子供がいる可能性もあります。長期にわたって会っていないとしても、子供であるからには相続人です。
そのため遺言書があるとしても、基本的には相続人調査が必要となります。
あわせて読みたい>>相続人全員の戸籍謄本はどうやって集める?注意点やコツを行政書士が解説!
相続財産調査
遺言書にすべての財産が網羅されていればいいですが、必ずしもそうとは限りません。
たとえば「全財産を息子Aに相続させる」と書かれていても、相続手続を漏れなく行うためには、その全財産とはいったい何なのか具体的に明らかにする必要があります。
また、もしかしたら借金などマイナスの財産が存在する可能性もあるため、遺言書があったとしても相続財産調査は必須です。
関連記事:相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!
遺産分割手続き
遺言書が有効で、検認も完了した場合は、遺言書の内容に沿って遺産分割手続きを進めていきます。
財産の種類によって手続き方法は異なるため、下記の記事を参考にしてみてください。
預貯金口座はどう相続する?遺産分割協議書の必要性を含めて手続き方法を行政書士が解説!
株式は相続で名義変更できる?手続き手順や注意点を行政書士が解説!
自動車の相続手続きはどうする?名義変更の必要書類や注意点を行政書士が解説!
遺言書のある相続も行政書士に相談できる
「遺言書が見つかったけど、どうしたらいいのか分からない」という方もいるかもしれません。
まず意識すべきことは、検認手続きまで、遺言書を開封することは禁止されているということです。
「遺言書」と書かれた封筒が見つかったら開封したくなる気持ちも分かりますが、もしそれが自筆証書遺言など検認の必要があるものであれば、開封すると過料の対象となってしまいます。
まずは見つけた遺言書が自筆証書遺言なのか(検認が必要なのか)、公正証書遺言なのか(検認が不要なのか)、これを判断しなければなりません。
そして遺言書があったとしても、各種相続手続には相応の手間がかかります。
もし「見つけた遺言書の種類が分からない」「遺言書はあるけど相続手続を自分で進める自信はない」といった悩みを抱えている方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。
相続手続を全般的に承っておりますので、ご依頼者様に負担がかかることはありません。初回相談は無料なので、まずはLINEや電話での来所予約をお待ちしております。