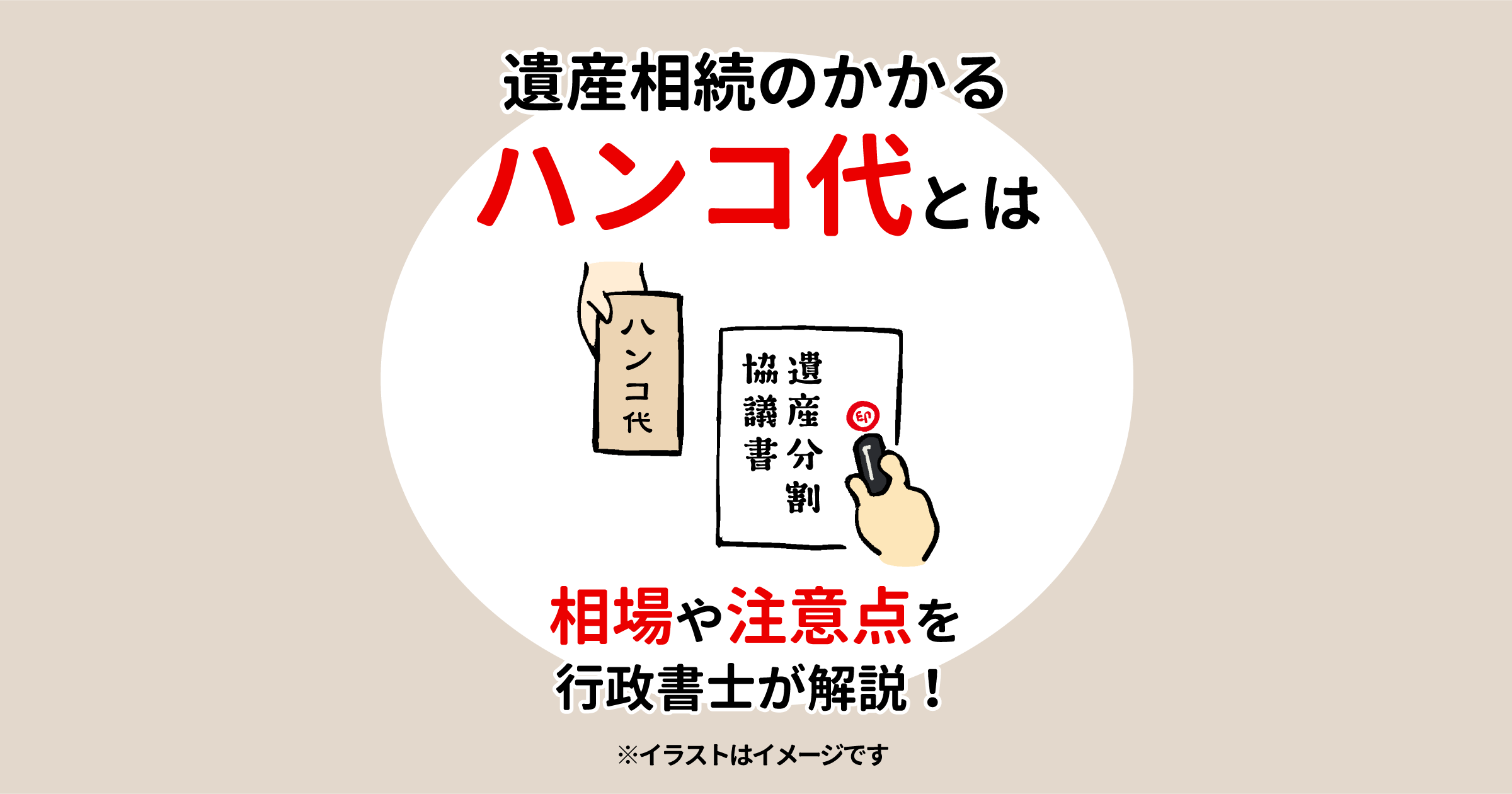「遺産相続協議時にハンコ代というものがあると知った。なぜもらえるの?」
「昔から相続にはハンコ代が欠かせないと聞いたけど、相場はあるのか」
「ハンコ代という慣習の注意点と知りたい」
遺産相続時には、手続きをスムーズに進めるために「ハンコ代を支払う」という慣習があります。この慣習は一体どのようなもので、相場や注意点はあるのでしょうか。この記事で行政書士が詳しく解説します。
遺産相続時に発生するハンコ代とは
遺産分割協議を進めていく際に、「ハンコ代」が発生すると聞いたことはありませんか。
遺産分割を行うのは被相続人の配偶者や子など家族ですが、円満に協議ができるとは限りません。そこで、場合によってはハンコ代を支払うことで協議を円滑に進める方法があります
そこで、この章では遺産相続時に発生する「ハンコ代」について、詳細を解説します。
遺産の取り分が少ない相続人などに支払うお礼
遺産分割協議時に支払うハンコ代には、法的な義務はありません。ハンコ代、と呼ばれているのも慣習の1つです。
合わせて読みたい:遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説
遺産分割協議は相続人全員に実印を要するものです。遺産分割協議は常に法定相続分で終えるものではなく、話し合いで相続人の取り分を決めていくものです。受け取らない人がいても問題ありません。不動産は母、それ以外は子、のように財産の種類別に分配してもOKです。
遺産分割協議の内容によっては、相続人の一部が難色を示すおそれがあります。そこで、あらかじめお礼としてハンコ代を用意しておくことで、円滑に進める方法が検討できます。取り分が少なくてもお礼をくれたから、と納得してくれる相続人もいるでしょう。
遺産分割時におけるハンコ代の相場
ハンコ代には「相場」はあるのでしょうか。結論から言うと、相場は約5万~30万程度の範囲内でしょう。ただし、高額の相続財産があるにもかかわらず、若干の取り分で同意を促す場合はこの金額よりも上回ることも考えられます。
被相続人と相続人の関係性や、遺産総額によって相場は変わるため注意が必要です。
ハンコ代は必ず必要?
ハンコ代はあくまでも慣習の1つです。相場感覚も掴みにくいものであり、支払う側の相続人は「本当に支払うべきなのだろうか」と悩む人もいるでしょう。
そこで、この章ではハンコ代の支払いについて、必要性を解説します。
ハンコ代に法的な義務はない
すでに文中に触れたように、ハンコ代には法的な義務はありません。
必ず必要かとの問いには「支払わなくてもよい」が答えです。しかし、遺産分割協議で財産の取り分について紛争の気配がする場合、あらかじめお礼を提案しておくことで、調停や審判のリスクを回避できるメリットはあります。
特に介護や生活資金などの面で支えてくれた家族が、少ない遺産で相続に同意してくれそうなケースでは、これまでのお礼の意味も込めてハンコ代をお渡しするメリットがあるでしょう。
ハンコ代は紛争予防の効果がある
相続は家族の仲や遺産相続の総額、相続人の性格や被相続人の生前のふるまいなどによって、解決方法が異なります。ハンコ代が無くても円満に相続できるケースもあれば、相続人から別の相続人へお礼を示すことで、円満に解決できるケースもあります。ハンコ代には紛争予防の効果があるのです。
一方で、無理矢理ハンコ代を渡そうとすると、「私の気持ちはお金では買えない」と反発をされるおそれもあります。支払いの有無には慎重な判断が必要でしょう。
ハンコ代を支払う注意点とは
ハンコ代を支払う際には、押さえておきたい注意点もあります。そこで、この章では注意点を次3つのポイントに分けて解説します。
- 贈与と見なされる可能性がある
- 追加の支払いを求められるリスクがある
- ハンコ代の解釈が相続人によって異なってしまう
では上記3つの注意点を以下に見ていきましょう。
贈与とみなされる可能性がある
ハンコ代には相場は無いため、裁判所での解決を回避するために高額を支払ってでも協議段階で解決したいと思う方もいるでしょう。遺産分割調停に進んでしまうと、半年以上解決できない場合もあります。
合わせて読みたい:遺産分割協議や遺産分割審判とは?遺産相続でもめた場合を解説!
しかし、高額のハンコ代金を支払ってしまうと「贈与」にみなされる可能性があります。特に100万円を超える金額を相続人に支払う場合は、暦年贈与の非課税枠である「110万円」を超えてしまう可能性があり、相続以外のトラブルを引き起こすリスクがあります。
ハンコ代の金額は相続人間で、贈与リスクも含めて慎重に話し合うことが大切です。
追加の支払いを求められるリスクがある
円満に遺産分割協議を終えるためにハンコ代を支払った場合、相続人によっては「やっぱりもっと欲しい」と追加請求をしてくる可能性があります。
納得のいく金額を支払わなければハンコは押さない、という相続人の場合、ハンコ代を支払っても円満に解決しないおそれがあるのです。このようなケースでは、以下のような解決方法がおすすめです。
・納得のいく遺産相続がどのようなものか、相続人間で意見を出しあう
・協議が難航したら調停(その後は審判)を検討する
お金を巡るトラブルは、解決後も家族間で尾を引く可能性があります。話し合いが難しい場合は長期化を防ぐためにも、裁判所での手続きも視野に早期の解決を目指しましょう。
ハンコ代の解釈が相続人によって異なってしまう
ハンコ代があれば円満に解決できる、という法的な根拠はありません。そのため、受け取る・支払う相続人の性格に解釈が左右されるため、以下のようなトラブルにつながるおそれもあります。
・支払ってもらって当然、と思っている相続人に支払いをしない場合、怒ってしまう
・支払うのだから言うとおりにしろ、と強硬な姿勢を見せる
・複数の相続人がハンコ代を求めるため、重い負担となってしまう
わずかな金額のハンコ代でも、喧嘩の起爆剤になってしまうおそれがあります。トラブルが予想されるケースでは、ハンコ代ではなく代償分割として協議をするべきケースもあります
合わせて読みたい:遺産相続時の代償分割とは|メリット・デメリットを行政書士が解説
ハンコ代と代償分割の違いとは
ハンコ代は代償分割と類似していますが、以下に挙げるとおり異なっています。
①代償分割とは遺産を多く取得する方が、他の相続人に対して代償金の名目でお金を支払うことを意味します。
②ハンコ代は慣習のため遺産分割協議書には記載しませんが、代償金は遺産分割として行うため、贈与も回避でき遺産分割協議書にも記載できます。
記録に残らないお金のやり取りに不安がある場合は、代償分割を検討することもおすすめです。
円満な相続を進める2つのヒント
ハンコ代以外でも、遺産分割協議によってはトラブルが起きてしまうことがあります。大切な家族が「争族」にならないようにするためには、円満な相続を目指して次の2つのことを実践してみましょう。
- 生前に遺言書を作る
- トラブル時には遺産分割調停を検討
上記の2つの注意点を以下に一緒に見ていきましょう。
生前に遺言書を作る
円満な相続対策の1つ目は、「遺言書」です。生前に被相続人となる方が思いを込めて作っておくことで、相続人間の紛争を防ぐ効果が期待できます。複雑な相続の予感がある場合、遺言執行者を定めておくこともおすすめです。
■遺言執行者を決めておくメリット
遺言執行者は、遺言書の中身を忠実に進めていくための権限を持つ人です。他の相続人の同意を得なくても、相続手続きを進めていけます。相続人になる予定の方から選ぶこともできますが、行政書士をはじめとする士業を選ぶことも可能です。
合わせて読みたい:遺言執行制度と遺言執行者の義務について行政書士が解説
トラブル時には遺産分割調停を検討
遺産分割調停を回避するために、ハンコ代を検討する方もいます。しかし、遺産分割調停は公平な立場の調停委員がおり、冷静な話し合いを進めるためのきっかけにもなります。調停で納得ができなければ、審判に移行することも可能です。
納得できない遺産分割(遺留分を侵害するような内容や、不動産をめぐる意見の対立など)の際には、ハンコ代だけでの解決では難しいため、裁判所での手続きを活用して解決を目指すことも検討しましょう。
調停や審判は解決まで時間がかかり、相続人間に重い負担を強いるものです。しかし、調停員や裁判官といった第三者が介入するため、家族間で話し合っているよりもスムーズに解決できる場合もあります。
ハンコ代は解決策の1つ|生前からの相続対策を始めませんか
今回の記事では、遺産分割協議時に発生する「ハンコ代」について、相場や支払う際の注意点にも触れながら詳しく解説を行いました。
ハンコ代の取り扱いは地域や個人差もあり悩ましいものですが、贈与にならない程度に抑えておくことがおすすめです。また、トラブルを回避したい場合には、代償分割も検討できます。
ハンコ代での円満な相続は難しいことが予想される場合は、遺言書で対策を行うこともおすすめです。詳しくはお気軽に、長岡行政書士事務所にご相談ください。